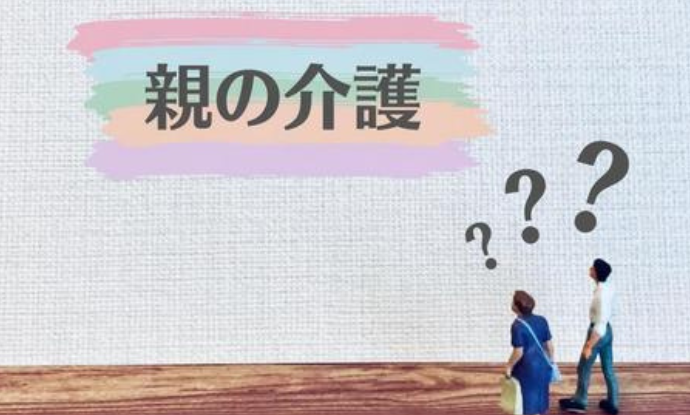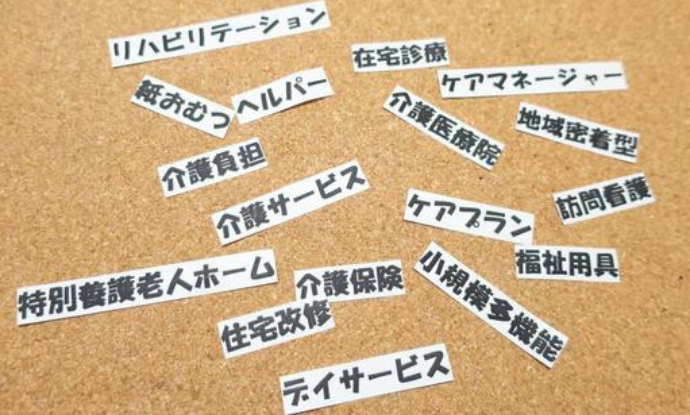1. 在宅介護を調整する人
・医療ソーシャルワーカーの役割
病院に入院している場合、入院中から退院に向けて在宅介護がスムーズに導入できるように動くのは医療ソーシャルワーカーです。介護保険サービスの導入が必要と判断すれば、要介護認定を申請する必要があるため、 手続き方法などを説明します。
入院前から在宅介護サービスを受けていた場合は担当のケアマネジャーと情報共有しながら在宅復帰を調整します。退院日に向けて在宅介護の担当者と、ご本人、ご家族、病院スタッフも含め退院前カンファレンス開催の予定を調整します。
・ケアマネジャーの役割
退院前カンファレンスの情報からどのサービスを利用するかご本人、ご家族に確認・調整し、介護保険のサービス計画書を立案するのがケアマネジャーの役割です。
介護保険サービスを利用しながら在宅介護をするのであればこのサービス計画書が必要になります。
介護が始まったら、きちんと介護サービスを利用できているか、困りごとはないか、思うようなサービスが提供されていないと感じたらケアマネジャーと相談し、事業所を変更することも可能です。
2. 在宅介護でお世話になる人
実際に退院が決まり、具体的に在宅介護について考えていく際には、医療ソーシャルワーカー、ケアマネジャー以外にどんな方々と関わるのでしょうか。これから介護していくうえで長くお付き合いをする方々の紹介をしていきます。
主治医:介護認定を受けるうえで必ず必要となる主治医意見書を書くのは主治医の役割です。主治医のアドバイスをもとに健康管理しながら在宅生活を送り、介護サービスを利用していきます。状態に応じて外来通院か訪問診療なのかは病状などを確認し、主治医と相談して決めます。
看護師:訪問看護が頭に浮かぶと思いますが、看護師は通所サービスやショートスティの施設にも常駐していますので体調不良時などもご安心ください。
介護士:介護士も在宅や通所、ショートスティ先の施設に常駐しています。訪問介護士と通所、施設介護士の違いはサービスを受ける方のご家族の同居状況にもよりますが、自宅で調理、掃除、買い物などをしてくれます。生活に密着しており頼りになる存在です。
理学療法士:リハビリが継続して必要な方は訪問リハビリや通所リハビリのサービスを活用できます。そこに常駐しているのが理学療法士です。リハビリ職は他にも作業療法士、言語聴覚士などもいます。
福祉用具業者:必要時、介護ベッドや車椅子、杖などの準備をします。状態に応じて各担当者と情報共有し、最適な福祉用具を選択してゆきます。
薬剤師:継続して今までお世話になっている薬局でお薬を購入することは可能です。もし病状や介護状況に変化があった場合には訪問して頂くことも可能です。その場合は別途料金が必要になります。
主にお世話になる方達を紹介してきましたが、いずれもケアマネジャーが中心となり各担当者と情報共有し、安心して在宅介護サービスを受けて頂けるように連携しています。
3. ご本人ご家族の準備
介護サービスが始まる前にケアマネジャーはご家族が介護できる時間、介護に必要なお金の事、介護に協力してくれるご家族以外の存在を確認します。介護を受ける方の生活リズムや趣味、大切にされている事なども聞き取り、生活に対するそれぞれの思いを確認します。自宅で安心して過ごす為には、介護を受ける方、ご家族のそれぞれの気持ちが大切です。
以下は介護サービス計画書に必ず記入するご本人とご家族の意向です。
ご本人:入院前の様に一人でお風呂に入れるようになりたい。
ご家族:介護サービスを活用しながら一人暮らしを続けてほしい。
これは一例です。安心して在宅生活をすることがお互いの願いだと思いますが、具体的に生活で困っている事を整理して、これができるようになったら良いなと思う目標をケアマネジャーと考えます。それに沿って介護サービスを決めていきます。
4. 実際の介護サービスが始まるまで
要介護認定を受けている場合は退院前カンファレンス、サービス担当者会議を行い、各担当者の準備、契約を締結し、退院日が決まれば介護サービスはスムーズに始まります。
しかし、要介護認定を受けていない場合は約1か月ほど時間がかかってしまいます。また新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、認定調査が病院の面会許可状況で左右され、認定結果が遅くなる可能性もあります。
・早期退院の社会的背景
入院し退院、そして在宅介護までさまざまな調整やカンファレンスを行い、準備していきますが、早期退院を余儀なくされるケースもあります。
その背景には政府の施策として高齢化社会において入院日数が長引き、病床数が足りなくなることを危惧し、出来るだけ入院日数を短くするような医療政策が打ち出されており、入院日数が長引けば医療報酬も低くなる仕組みがあるためです。国の推奨する入院日数は病気によって相違がありますが、14日間となっています。
もちろん病状が安定しないのに退院させるという事はありません。急性期の対応でなくなれば回復期病棟に転科するか、リハビリテーション病院へ転院となるケースもあります。このような状況から介護認定結果も出ていないままで退院するケースもあります。
こういう流れはとても困りますよね。そんな時、在宅介護はどのように進めていけばよいのでしょうか。
5. 一時的な自費サービスの利用
介護認定結果が出て介護保険サービスが始まるまでは、場合によっては数週間~1か月程度かかることがあります。それまでの間、介護保険適応の専門職からサービスを受けることができません。安全に生活していく為の対策なしに在宅生活を再開しなければならないということになります。
急に退院し、どのように介護を行ったらよいかわからない時、どのような自費の介護サービスを活用したらよいのでしょうか。その場合の選択肢として、看護師の有資格者の自費の訪問サービスというものがあります。
・自費の訪問サービスの役割
医療保険、介護保険で対応できない部分のお手伝いをするのがこのサービスの役割です。自費の訪問サービスは、介護保険適応のサービスとは違い、退院した当日から必要な介護を提案・ 実行し、正式に介護保険適応のサービスを利用するまでの繋ぎとして活用することもできます。
看護師は医療や介護、生活の視点など多方面での情報や分析が可能ですので、介護保険サービスを利用する前にサービス担当者会議に出席し、ケアマネジャーや多職種と相談しながら連携して進めることができます。
他の自費の介護サービスとしては、介護の電話相談や家事代行サービスや旅行付き添い、外出支援、訪問理容などがあります。
6. 終わりに
介護をしていく上でいちばん大切なことは、「介護を受ける人」と「介護をする人」がお互いに満足できるようさまざまなサービスを上手に活用することで、それは介護が終わった時、後悔しない為です。
もっと相談する人がほしかった、ああすればよかった、こんなサービスがあったなんて知らなかったなど、振り返った時に残念な気持ちにならないようにしたいものです。
今回ご紹介した各担当者の役割や自費サービスが利用できることを知っていただければ、介護の選択肢を増やすだけでなく、快適な環境、関係性、時間を作っていただけると思います。