高齢者は加齢とともに筋肉の量が減少して、体が疲れやすくなったり、歩くときにふらついたりなどさまざまな症状が現れやすくなります。この筋力低下のスピードは年に1~2%程度といわれていて、上半身の筋肉より下半身の筋肉が3倍衰えやすいそうです。
このように、低下する筋力をなんとか補うために運動しようと思うと、どうしても専門のスポーツクラブなどに行かなければ出来ないと考えてしまい、なかなか取り組めていない方も多いと思います。しかし、実はスポーツクラブに通わなくても日常のちょっとした工夫で運動の効果を高めることができます。
このコラムでは、自宅の外で簡単に取り組める介護予防に繋がる運動を4つ紹介します。

歩くことについては歩数だけではなく、スピードを意識することも大切になってきます。実は歩行スピードと余命には深い関係があるといわれています。70歳になっても若い人と変わらないスピードで歩くことができる高齢者の方は、健康寿命を維持して長生きができるという研究があります(歩行速度から予想される余命(JAMA. 305(1), 50–58, 2011)(出所=『健康寿命をのばす食べ物の科学』))。
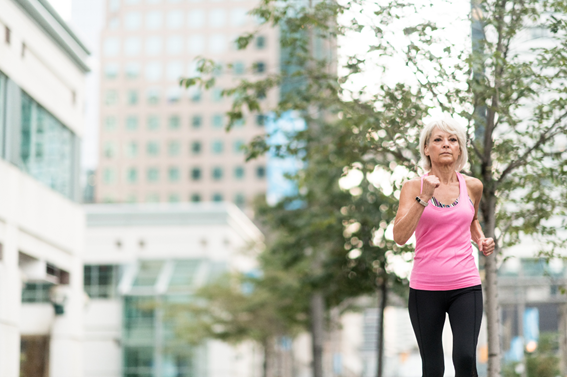
歩行運動と似ていますが、階段の昇り降りも下半身の強化にはとても効果があります。階段の昇り降りができる人とできない人を比較した研究では、階段の昇り降りができる人の方が、長い距離を歩くことができたり、転倒しにくいという結果が出ているそうです。
日常の中で階段の昇り降り運動を始める際におススメの方法をご紹介します。
●スーパーなどでエレベーターやエスカレーターの使用を控えて、階段を使ってみましょう。
●散歩のコースに階段のある公園などを取り入れる。
●昇るときにはやや前傾姿勢、降りるときにはゆっくりと足をつくことを意識してみましょう。
もちろん、こちらもひざなどに痛みがある場合には無理をせず、徐々に頻度を上げていくことを心がけましょう。「普段は1Fから3Fまでエスカレーターを使っているけど、今日は2Fからエスカレーターを使おう」というように、部分的に階段を用いることが大切です。
また、荷物を多く持った状態で行うことは転倒にも繋がりますので、時と場合によってはエレベーターやエスカレーターを積極的に使いましょう。

椅子からの立ち座りは下半身の筋力トレーニングにとってとても効果的です。立ち上がる際は、大殿筋や大腿四頭筋と呼ばれる下半身の大きな筋肉が使われています。外出時には椅子に座ることが多くなるでしょうから、そのときには下記のポイントを考えながら行ってみると良いでしょう。

この記事では、自宅の外で簡単に取り組める介護予防に繋がる運動をご紹介しました。いずれも日々の生活にほんの少し変化を加えるだけですので、慣れてしまえば当たり前になってくることでしょう。取り組めそうなものを1つだけでも取り組んでみてくださいね。

著者:坂元大海(アークメディカルジャパン株式会社 代表取締役)
<プロフィール>
10年間整形外科に勤務後、アメリカ(UNLV)に留学し、ピラティスマスターのライセンスを取得。帰国後にアークメディカルジャパン株式会社を立ち上げ、医療・健康・スポーツ分野において事業を展開。延べ10万人以上の豊富な治療経験や多くのプロ選手、日本代表選手、俳優などへのケアやコンディショニングを行っている。教育、講演、育成においても精力的に活動し、全国での指導実績も豊富にある。
<所有資格>
・理学療法士
・鍼灸師
・柔道整復師
・国際PNF協会 Recognized course修了者
・(財)日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー
・NASM-PES
<講師実績>
久留米大学、九州共立大学、福岡リゾートアンドスポーツ専門学校非常勤講師
<学術活動>
・「血流制限下でのレジスタンストレーニングが筋活動に及ぼす影響」PT学会、理学療法学
・「シンスプリントの発生要因に関する一考察」九州・山口スポーツ医学会など多数