「介護予防教室」とは、高齢者の方ができるだけ自立した生活を続けられるように、心と体の健康を保ち、日常生活の動作をスムーズに行えるようにサポートする場です。以前は心身の機能を回復するための訓練が中心でしたが、今では「活動」や「交流」に重点を置いた、楽しく通える場へとその役割が広がってきています。参加することで心身の衰えを防ぎ、「自分らしく、元気に暮らし続ける力」を育むことができます。
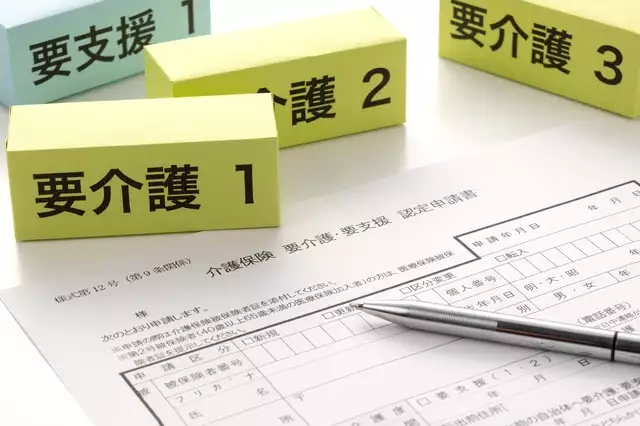
介護予防とは、高齢者が要介護状態になるのを防いだり、すでに要介護となっている方でもその状態を軽くしたり、悪化を防ぐことを目的とした取り組みです。その中心的な場となるのが「介護予防教室」です。
以前は介護予防といえば、体の機能を回復させる訓練(機能回復訓練)が中心でした。しかし、今では「体と心の機能」「日常生活の活動」「地域や家庭での役割参加」の3つをバランスよく支えることが大切だと考えられています。
介護予防教室では、体の機能改善だけを目指すのではなく、日常生活の中での活動を増やし、地域や家庭での参加を促すことを大切にしています。その結果、生きがいや自己実現を支え、生活の質(QOL)が高まります。運動や栄養指導だけでなく、地域での居場所づくりや役割づくりといった支援も含め、幅広い取り組みが進められています。

介護予防教室の主な対象年齢は65歳以上の方です。ただし、要支援・要介護認定を受けていない方や医師から運動制限を受けていない方など、市町村によって詳細な条件が異なります。一部では60歳以上を対象とする教室もあります。国は年齢や心身の状態にかかわらず、地域で気軽に通える「通いの場」を増やし、多くの人が参加できるようすすめています。
特に、体が弱っている方や家に閉じこもりがちな方も対象です。専門のリハビリスタッフ(リハ職)が、その人の体の状態に合わせて安全な動き方をアドバイスするなど、安心して参加できる工夫がされています。実際に、要支援1から要介護2までの高齢者を対象としたモデル事業も行われています。

介護予防教室では、「体と心の機能」「日常生活の活動」「地域や家庭での役割参加」の3つの要素に働きかける、さまざまなプログラムが用意されています。
①心身機能へのアプローチ
座る・立つ・歩くなど、日常生活に必要な基本動作を改善する訓練(機能回復訓練)が行われます。リハ職が、参加者の体の状態に合わせて運動プログラムを作り、介護職員などに助言することで、安全に効果的な運動が実施できます。
②活動へのアプローチ
食事、着替え、入浴などのADL(日常生活動作)や、掃除、洗濯、料理、外出などのIADL(手段的日常生活動作)をスムーズに行えるようサポートします。リハ職が通所や訪問の両方で関わり、自宅や地域での生活環境に合わせた訓練を提供することで、生活の自立度を高めます。
③参加へのアプローチ
地域の中で生きがいや役割を持てる居場所づくりや活動への参加を支援します。高齢者が地域の体操教室で指導役を担うなど、自分の役割を意識することで、生きがいや自信が生まれます。大分県竹田市の「暮らしのサポートセンター」では、さまざまな世代が楽しめるイベントを開催し、住民の交流を促進するとともに、地域への愛着を育んでいます。
介護予防教室のプログラム内容は、市町村によって異なり、実にさまざまです。体操やストレッチなどの運動、口腔機能向上や栄養指導、趣味活動や交流プログラムなど、多彩な取り組みが行われています。
・運動プログラム:いきいき百歳体操、転倒予防体操、ストレッチ、イス体操、筋トレなど
・認知機能対策:脳トレ(計算・音読・パズル)、間違い探し、回想法(昔話や写真を使った会話)
・口腔機能向上:パタカラ体操、嚥下体操、発声練習
・栄養・食生活改善:栄養講話、減塩・バランス食講座、フレイル予防の食事ワークショップ
・交流・社会参加:茶話会、趣味活動(手芸・工作・園芸等)、地域ボランティア参加紹介
・健康・生活講座:健康チェック(血圧測定等)、フレイル予防講話、生活習慣病予防教室

介護予防教室は、市町村が地域の実情に合わせて進めています。多くの地域では、住民自身が運営する体操や集まりなどの「通いの場」がつくられています。内容や料金は地域やプログラムによってさまざまです。住民が主体となって活動する「通いの場」の一部をご紹介します。
・大阪府大東市:自治会・町内会が中心となり、「大東元気でまっせ体操」を市内全域で展開しています。
・愛知県武豊町:町・大学・社会福祉協議会が協力し、住民ボランティアを支援。徒歩15分圏内(500m圏内)に「憩いのサロン」を設置しています。
・茨城県利根町:60歳以上の住民ボランティア「シルバーリハビリ体操指導士」が公民館などで体操教室を立ち上げ、自主活動として運営しています。
・高知県高知市:運動機能向上の「いきいき百歳体操」、口腔機能向上の「かみかみ百歳体操」といった取り組みやすい体操が考案され、普及しています。
※上記はいずれも2025年9月現在の情報です

介護予防教室に参加することで、身体機能の維持だけでなく、より活動的で充実した生活を送ることができます。以下は、各地で開かれた介護予防教室に参加した方のコメントです。
・奈良県生駒市:腰痛と物忘れで要支援・要介護状態だった夫婦が教室に参加。夫は畑仕事を再開し、要介護認定を更新せず、妻も役割を得て笑顔が増えました。
・大分県竹田市:股関節の手術後に要支援状態となった女性が、水中運動やウォーキング、地域の役割づくりに参加し、畑仕事も再開、要介護認定を更新しませんでした。
・岡山県岡山市:膝関節手術後に外出に自信がなかった女性が、リハ職の支援と介護予防教室への参加を通じ、介護予防教室のボランティアとして活動するまでになりました。
・東京都世田谷区:脊柱管狭窄症の手術後に外出に自信をなくした女性に、リハ職が自宅の動線を確認しながら歩行の練習を行った結果、デパートへの外出や趣味の活動を再開することができました。
介護予防活動や社会参加が盛んな地域ほど、転倒、認知症、うつのリスクが低いことがわかっています。住民が運営する体操教室や通いの場の活動が広がることで、人と人とのつながりが増え、活動が長続きしやすくなります。
お住まいの地域の市町村のウェブサイトや、地域包括支援センターなどで介護予防教室に関する情報を確認することができます。ぜひこの機会に、介護予防教室や通いの場を調べて、参加してみてはいかがでしょうか。
・出典:厚生労働省「これからの介護予防」
構成:研友企画出版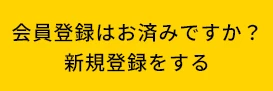

著者:MySCUE編集部
MySCUE (マイスキュー)は、家族や親しい方のシニアケアや介護をするケアラーに役立つ情報を提供しています。シニアケアをスマートに。誰もが笑顔で歳を重ね長生きを喜べる国となることを願っています。