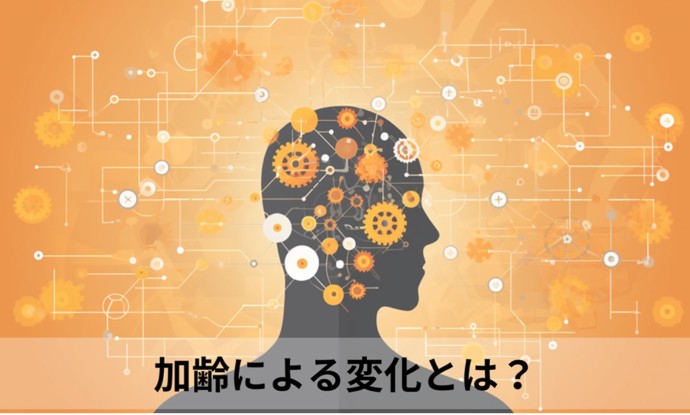1. 脳神経細胞と加齢の関連
1.認知機能低下のメカニズム
脳の重さは加齢とともに減ります。それは、脳の萎縮によるものです。60歳から比べると90歳では5〜7%ほど軽くなると言われています。脳の萎縮は脳神経細胞の減少によるものです。脳神経細胞は何種類もある神経伝達物質を細胞から細胞へと伝えており、感情・記憶を左右します。感情とは、嬉しい、悲しい、幸せなどと感じるものですね。感情に関係する神経伝達物質はセロトニン、ドーパミンなどです。記憶に関係するのはアセチルコリンになります。通常は脳神経細胞により神経伝達物質がネットワークのように繋がり、感情や記憶をコントロールされています。しかし加齢により神経伝達物質が少なくなると、ネットワーク機能もまた低下し、物忘れや認知症状を起こします。
認知症の原因は主に4つに分かれ、その7割を占めるのがアルツハイマー病になります。加齢によるアセチルコリン分泌の低下や特殊なタンパク質(アミロイドβ)の蓄積がアルツハイマー病の原因と言われています。ちなみに残りの原因は血管性認知症(約20%)、レビー小体型認知症(10%)、その他(1%程度)となっています。
2.すぐには起こらない認知症
これまでは、神経細胞は成長段階で分裂した神経細胞は増えない、というのが定説でしたが、一部の研究では海馬(記憶を司る部分)に神経細胞を新生する働きのある細胞が存在し、高齢者の脳でも神経細胞が新たに生まれている、という研究報告もされています。
脳では毎日10万個もの神経細胞の脱落が起こっていると言われています。しかし、脳全体では140億個もの神経細胞があるため、すぐに機能低下が起こるわけではありません。しかも、残った神経細胞は代償作用で新たな神経細胞の伝達回路を作り出すため、脳の機能は保たれています。加齢にまつわる変化の全てが認知症状の低下に繋がるとは言い切れないようです。
2. コミュニケーションの必要性
1.自己認識とコミュニケーション
誰しもが認知症の症状を抑えたい、進行を遅らせたいと思われるでしょう。上記に述べたように加齢の全てが認知症を促進させる理由にはならないということがわかってきています。
その鍵を握るのがコミュニケーションです。大前提として、人は1人で生きていくことはできません。誰か他人がいて初めて自分というものを認識することができます。世の中にたった1人、あなたしかいないと仮定してみてください。自分のことが認識できるでしょうか? 生きていけるでしょうか? このように考えると、人は第三者とコミュニケーションをとらなければ生きてはいけないことがわかります。
2.コミュニケーションの重要性
ある心療内科の患者さんでこのような方がおられました。退職された男性で、役職も務めていた方です。退職後、趣味がなく、食事をしている時はもちろん、四六時中、寝る直前までスマートフォンでインターネットをされていたそうです。数か月後、電子レンジの操作方法を忘れる、オートロックの鍵が開けられなくなど日常生活に影響が出始めました。そこで病院を受診し検査を行うと、前頭葉の機能低下が起こっていることが判明したのです。前頭葉は前回の記事「認知機能とは」で書いたように、理性や記憶を司る部分で大脳の30%を占めています。
国立長寿医療研究センターが65歳以上の13,984名を対象に約10年間の追跡調査を行いました(2017年に発表)。その結果では、「配偶者がいる」「同居家族と支援のやりとりがある」「友人との交流がある」「地域のグループ活動に参加している」「何らかの就労をしている」の5つのつながりのある人では、認知症発症リスクが低下することがわかっています。
さらにこれらの5つのつながりのある人は、1つもないか1つだけの人と比べて認知症発症リスクが46%低下することがわかっています。特定のつながりだけを持つよりも、さまざまなタイプのつながりがある方の方が認知症発症リスクを低下させる可能性があるといえます。
3.日本の社会的背景
戦後、高度経済成長の発展により人口が大都市に集中し、単独世帯が増加してきています。平成27年度の単独世帯は1841万7922世帯、令和2年度の単独世代は2115万人1世帯と、14.8%増加しており、世帯全体の38%およそ4割を占めています。このように年々単独世帯は増加傾向にあります。地域のつながりも気薄となってきており、孤独感を抱える高齢者が増えています。しかし、別居している家族とコミュニケーションをとったり、他者との交流をはかることで、認知症状の進行が緩やかになることは、上記研究から想像できます。
最近は会話するロボットや操作が簡単なスマートフォンも普及してきていますが、ご高齢の場合新しい事を覚えることが困難であり、機器の取り扱いに難渋している場面を多々見かけます。私自身も介護保険外の訪問看護を行なっていますが、時々スマートフォンの操作方法を聞かれることがあります。何週間も前の留守番電話が残っている、別居のお子様からの着信履歴に気づかれていない、などの方がおられるのが現状です。直接コミュニケーションをはかる機会が必要と感じる場面が多々あります。

3. 非言語的コミュニケーションの重要性
一番重要となるのは、何を話すかというような言葉でのやり取りより、話し方や声のかけ方、口調、接し方です。接するご本人様が何を受け取るかというと、話している言葉自体はほんの数%に過ぎないのです。
メラビアンの法則をご存知でしょうか? 人に与える印象に影響するのは、話し言葉自体が7%、視覚情報は55%、聴覚情報は38%といわれています。例えば会議などで、はきはきとしっかりとした口調で話をされている人と、おどおどと自信なく小さな声で話をしている人では、同じ内容の説明をしていても、受け取られ方が違うことはお分かりでしょうか?
1.聴覚情報の特徴を活かした接し方
・ご本人様が聞こえる声の大きさで
・聞こえる方の耳へ話しかける
・やや低めの声で(聞こえやすいと言われている)
・難聴があればできるだけ補聴器を装着してもらう
・多くの内容を一度に伝えず、1つずつ伝える
・間違っていることを訂正しない
2.視覚情報の特徴を活かした接し方
・穏やかな表情で話す
・できるだけご本人様が長年愛用しているものを使う(引越しや施設入所時など)
・背後から話しかけず、ご本人様の視野に入って話しかけるようにする
・できるだけ一緒の時間を共有する
・ご本人様がされていること(食事やお着替えなど)を急かさない
・相手に動きを合わせる(一緒に歩いている場合、歩調や呼吸を合わせる)
私たちは言語的コミュニケーションにスポットをあてて考えてしまいがちですが、実は非言語的コミュニケーションから受け取る印象が大部分を占めています。同じように「おはよう」と言うだけで印象が違うのは、非言語的コミュニケーションの部分で印象を受け取っているからです。
加齢と脳神経細胞の関連、そこからのコミュニケーションの重要性をお伝えしました。次回はコミュニケーション以外の対処方法をお伝えします。