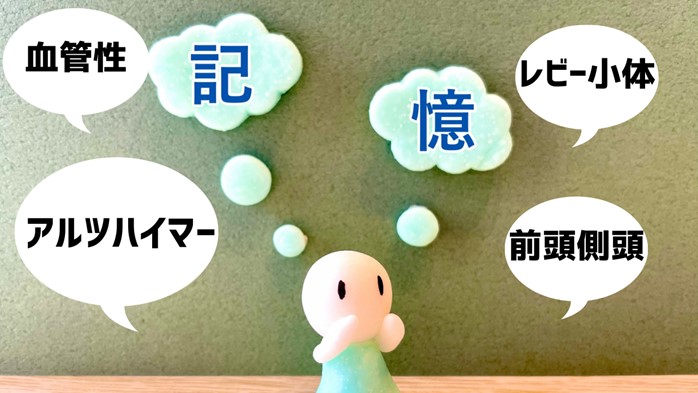1. 原因疾患によるもの
認知症は発症した原因により大きく4つに分けられます。アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、血管性認知症、前頭側頭型認知症の4つになります。以下詳細と対処方法について整理して説明します。
1.アルツハイマー型認知症
「認知症とコミュニケーション」でも書きましたが、加齢によるアセチルコリン分泌の低下、また特殊なタンパク質(アミロイドβ)の蓄積がアルツハイマー病の原因と言われています。記憶を司る海馬から広い範囲に、脳神経細胞の障害が見られ、認知症の約7割を占めています。比較的女性に多くみられます。初期症状としては物忘れが、症状が進行すると以下のような症状が見られます。
・失語:ものの名前がすぐにでてこない「あれ」「どれ」などで表現されることが多くなる
・失認:目で見えているがなにかがわからない(ペットボトルを見ているが何か理解できない)
・失行:ものの扱い方がわからない(ペットボトルのふたが開けられない)
・遂行機能障害:一連の行動が計画通りにできない(自動販売機でお茶を買おうとお金を入れ、ボタンを押していないのに、商品を取ろうとするなど)
これらの症状は必ず全ての例で見られるわけではなく、人によってさまざまです。また症状はゆっくりと進行していくのが特徴です。しかしアルツハイマー型認知症は食事、睡眠、運動など生活を整えること、またご家族様や他者とコミュニケーションをとることで、進行が緩やかになると言われています。
2. レビー小体型認知症
レビー小体というタンパク質が脳に溜まり引き起こされる認知症で、認知症のうち約1割を占めます。またアルツハイマー型認知症と合併することもあります。男性がやや多い傾向があります。また初期症状には睡眠障害や便秘が見られることがあります。症状が進行すると、パーキンソン症状と呼ばれる、幻想・妄想・うつ状態、起立性低血圧などが見られます。
対処方法としては、幻視予防として、室内の明るさを一定に保つ方法があります。またアルツハイマーと異なり転倒リスクが高いため、室内の段差をなくす、床にものを置かないなど環境整備が必要になります。運動療法も重要です。体内の血流改善で脳の活性化を促します。ご本人様の好きな音楽をかける、絵を描くなどのことも脳への刺激につながります。
3.血管性認知症
アルツハイマーの次に多く、全体の約20%を占めます。脳梗塞・脳出血などで脳血流が悪くなり、脳細胞が障害されて起こります。男性に多くみられます。高血圧・肥満・糖尿病・喫煙など生活習慣が一因となっていることもわかっています。症状は障害される脳の領域によりさまざまです。歩行障害や嚥下障害、排尿障害など身体的な症状などに加え、うつ状態や感情の起伏が激しくなる(急に笑い出す、泣くなど)などの症状が見られます。脳の障害部位によってこれらの症状が起こらない場合もあります。
生活習慣が原因だとわかっているので、生活習慣を改善することが望まれます。規則正しい食生活や運動、禁煙などです。感情的になられている時は、穏やかにゆっくりと傾聴することなどが必要でしょう。
4.前頭側頭型認知症
名前の通り、脳の前頭葉と側頭葉が障害され発症します。他のアルツハイマー型やレビー小体型には見られない症状が見られます。前頭葉は思考・理性などを司っています。人が人らしく生きられる部分です。側頭葉は知識・記憶・感情などを司っています。性格の変化や同じことを繰り返すなどの症状が見られます。社会性を失う傾向にあるので、万引きをする、赤信号を無視するなどの行動が見られます。逆に物忘れはあまり見られません。
病気が進行すると、意欲や活動性が低くなり、上記のような行動は徐々に見られなくなり、同じ行動を繰り返すことぐらいが残ります。少しずつ感情がなくなり、発語も聞かれなくなります。やがてご自身から動作することが少なくなり、ベッド上での生活が長くなります。
対処方法としては、同じ行動を繰り返すという特徴をふまえ、他の方法に置き換える療法があります。ご本人様が以前お好きだったもの、編み物やパズル、踊りなどに置き換える方法です。このご病気の方は道具を上手に使える方が多いというのが特徴です。そして集中しているか、楽しそうにされているか、無理なく続けられることかが大切です。
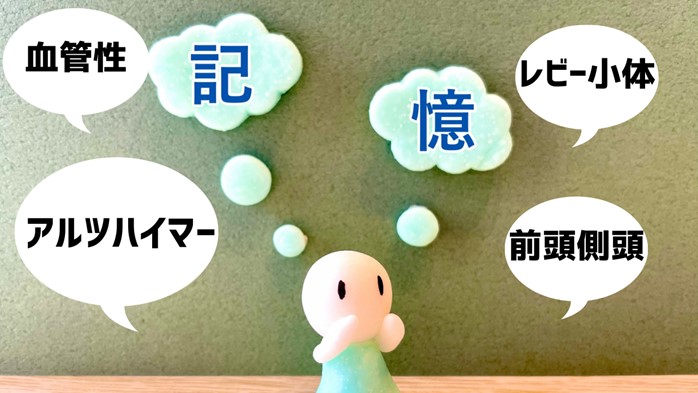
2. 認知症の2大症状
1.中核症状
中核症状とは脳の神経細胞の減少で起こる症状のことです。以下にまとめて説明します。
・記憶障害:何度も同じ話を繰り返す、約束を忘れる、薬の飲み忘れなど。
・注意障害:注意力低下で同時に複数のことができなくなる。会話についていけなくなる。
・言語障害:適切な言葉がでてこない。相手の話の内容が理解できなくなる。
・見当識障害:日にち、時間、場所がわからなくなる。友人や家族がわからなくなる。
・実行機能障害:家事や仕事の段取りができなくなる。今までできていたリモコンなどの操作がわからなくなる。
対処方法としては、まずご本人様に今何ができるかを確認、見極めていきます。そしてできることを行なってもらい、役割をもってもらいます。ご本人様が楽しめることを行なってもらうといいでしょう。地域の交流会などがあれば参加する、デイサービスを利用するなどして、他者と交流することも脳の刺激に有効です。
2. 周辺症状(BPSD)
周辺症状は1の中核症状に合わせて、上記の原因やご本人様の性格、周囲の環境などで変わってきます。つまり症状には個人差があります。
・暴言・暴力:怒りや感情を抑えられず、大きな声を出される。
・うつ:できないことが増えていき、うつ状態になる。
・妄想:お金を盗られたなどの妄想が生じる。
・徘徊:今いる場所がわからなくなる。自宅にいるのに「家に帰る」と言い出し、徘徊が見られる。
・幻覚:見えないものが見えたり、聞こえたりする。
対処方法としては、ご本人様は今まで出来ていたことができなくなってきた、新しいことが覚えられないなどの不安や恐れがあります。介護者としても焦りを感じるでしょう。否定したり相手を責めたりするのではなく、なるべく受け入れ、今できることを行なってもらうことが大切です。ゆっくりと相手のペースに合わせ、もしお財布をとられたなどの発言が聞かれたら、責めるのではなく一緒に探して、見つけてあげる。話をじっくり聞くなどの接し方が重要です。
3. まとめ
認知症の対処方法は1人ひとり異なるため、難渋すると思います。その方に合った接し方を模索しながら関係性を構築していく必要があるでしょう。特に周辺症状は暴言を吐く、徘徊するなど、介護者の心理的・身体的負担は大きくなります。先に症状を知っておくことで、ご病気によって出ている症状であると理解できるため、本記事でお伝えしました。一般的な症状についての対処法方でしたが、次の記事では、ご両親が認知症になった時の接し方をお伝えします。