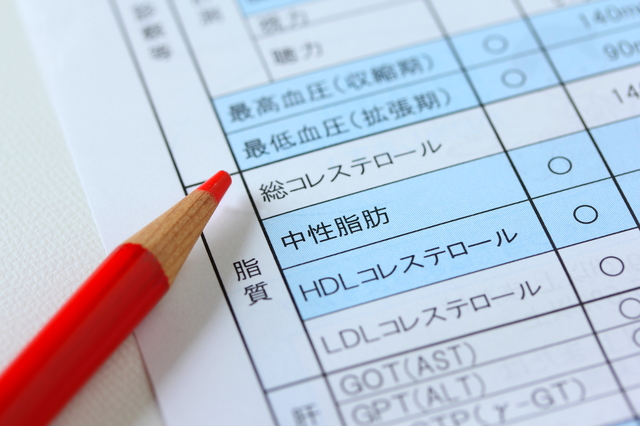1. 変形性ひざ関節症になりやすいのはこんな人
中高年になるとひざの痛みを感じる人が増えてきます。そして、その多くが変形性ひざ関節症といわれる病気です。変形性ひざ関節症は、ひざへの衝撃を吸収する軟骨や半月板がすり減り、クッションの働きが低下することで発症します。時間をかけて進行し、少しずつ症状が重くなっていきます。
変形性ひざ関節症の代表的な原因とされているのは、長年のひざへの負担や加齢による軟骨、半月板の摩耗ですが、実はそれだけではありません。ひざ検査方法や治療方法の話をする前に、まずは「変形性ひざ関節症になりやすい人」の特徴を把握しておきましょう。
下のチェックリストが、ご自身やご家族にあてはまらないかを確認してみてください。
<変形性ひざ関節症になりやすい人>
□高齢(加齢で軟骨がすり減ってしまう)
□肥満傾向(体重で関節に過重な負担がかかるほか、脂肪組織からの分泌物によって関節に炎症をおこしやすくなる)
□女性(関節を支える筋肉量が少ない。また、閉経後は筋肉量が減りやすくなる)
□もともとがO脚
□運動不足
□やせ形で筋肉が少ない
□スポーツや仕事でひざを酷使してきた
□ひざの治療が不完全
高齢者が変形性ひざ関節症になると、歩きづらさから外出を避けるようになり、家に閉じこもりがちになるケースも見られます。体を動かさず、人と話す機会も減ると、抑うつ症状を招く原因になりかねないので、十分に注意しましょう。
2. 痛みを感じたら、検査で原因を突き止めて!
変形性ひざ関節症の治療は、「運動の習慣をつけること」が基本ですが、痛みが強くて運動ができない場合は、薬や装具による治療を行う場合もあります。それでも痛みが改善しない場合や、痛みで日常生活に支障を来している場合は、手術が検討されることになるでしょう。
ここでは、治療や手術に進む前段階として、ひざの痛みを感じたときの検査方法を紹介します。
●検査
ひざの痛みで受診すると、「いつから、どのようなときに痛むのか」や「痛みの程度はどのくらいか」などを尋ねられます。さらに、医師がひざを触ったり動かしたりしながら、外見上の変化や曲げ伸ばしできる範囲、関節の腫れや熱感、痛みの出方などを確認します。関節液がたまっていると判断されれば、注射器で抜いて詳しく調べることになります。
変形性ひざ関節症の場合、こうした問診・触診に加えて、X線検査を行ったうえで診断するのが一般的です。必要に応じて、MRI(磁気共鳴撮影)検査を行う場合もあります。なお、症状がどれくらい進んでいるかは、X線検査で軟骨のすり減り具合や関節の変形具合、骨の状態などを調べて判断されます。
「正常な関節のX線検査画像を見ると、骨と骨の間に黒く写る隙間があるはずです。そこには軟骨などがあるのですが、変形性ひざ関節症が進行すると隙間が狭く写るようになり、ついにはなくなってしまいます。そうすると骨同士がぶつかって、強く痛むようになるのです」(中川匠先生)
関節の隙間が狭くなる状態を「関節裂隙(れつげき)の狭小化」と呼びます。また、症状が悪化すると、関節のまわりにとげ状の骨である「骨棘(こっきょく)」が見られるようになり、さらに変型が進んでいきます。
3. 痛みが強いときは、薬や装具で運動療法をカバー
前述したように、変形性ひざ関節症の治療の基本は運動療法です。痛みの程度や病気の進み具合によって、すすめられる運動は異なりますが、すべての患者が運動に取り組むことになります。ただし、痛みで運動ができない場合は、薬による治療や装具を使った治療、さらには外科的な手術を行うことになるでしょう。
●薬物療法
変形性ひざ関節症の薬物療法には、「内服薬」「外用薬」「関節内注射」があります。
・内服薬
痛みや炎症を抑える非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAIDs)やCOX-2選択的阻害薬、デュロキセチンなどが使われます。
・外用薬
こちらも、非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAIDs)の塗り薬や貼り薬が使われます。
・関節内注射
ひざが腫れたり関節液がたまったりして、炎症が強いと判断されると、注射器で関節液を抜いたうえでヒアルロン酸やステロイドを注射する場合があります。ヒアルロン酸注射は副作用がほとんどなく、関節が滑らかに動くようになり、痛みが軽減されます。しかしながら、変形性ひざ関節症が進行して骨と骨がぶつかり合っているような段階では効果がない場合があります。
●装具療法
サポーターや足底板などの装具を使って、ひざにかかる負担を軽減したり関節を安定化させたりする装具療法も、変形性ひざ関節症の治療の1つです。足底板というのは足の外側を高くした靴の中敷きで、これによって重心がひざの内側から中央に移動するため、O脚のバランス矯正に役立ちます。
●手術
ここまで紹介してきた治療法を行っても、痛みが取れない、改善しないといった場合は、手術を検討することになります。主な手術方法として挙げられるのは、骨に切り込みを入れて関節の角度を調整し、ひざを真っすぐにする「高位脛骨骨切り術」や、傷んだ関節表面の骨や軟骨を人工関節に置き換える「人工関節全置換術」などです。
なお、適切な手術方法は、本人の年齢や状態、生活環境などによって変わってきます。医師の説明を聞き、きちんと理解してから治療法を選ぶようにしてください。
4. 関節の水(関節液)を抜くとクセになるって本当?
関節内注射の項で触れましたが、関節内にたまった関節液を注射器で取り除くことを、俗に「水を抜く」といいます。
ひざの水については、「抜くとクセになる(水がたまりやすくなる)」という人もいるようですが、本当でしょうか。この点について、中川先生は「関節液を抜くことで、さらに関節液がたまりやすくなることはありません」と否定しています。
「関節液はひざ関節に炎症が起きたときの防御反応としてつくられるもの。炎症が治まっていないと、関節液を抜いてもすぐにたまることになります。これがクセになるといわれる理由です」(中川先生)
ちなみに、関節液を抜いたあとは、運動療法や薬物療法などで炎症を抑える治療をあわせて行ったほうが効果は高いそうです。
5. まとめ
朝、ベッドから起き上がるときにひざの痛みを感じたけれど、気がついたら痛みはなくなっていた——。そんな場合、多くの人が医師の診察を受けることもなく、そのままにしてしまうのではないでしょうか。しかし、立ち上がりや歩き出しで痛みを感じるのは、変形性ひざ関節症の初期症状の可能性があります。また、一時的に痛みが消えたとしても、関節軟骨のすり減りは少しずつ進行するので注意が必要です。
変形性ひざ関節症は進行すると、日常生活に支障を来すようになったり、ロコモティブシンドローム(運動器症候群)の原因になったりするため、早い段階で医療機関の検査を受けるようにしましょう。当記事の「変形性ひざ関節症になりやすい人」の項目にあてはまる場合は、とくに気をつけてくださいね。
監修:中川 匠先生
中川 匠(なかがわ・たくみ ※写真下)
帝京大学医学部整形外科講座 教授。1966年生まれ、東京大学医学部卒業。専門は整形外科、とくにひざ関節疾患、スポーツ整形外科。整形外科学会専門医。著書に『NHKきょうの健康 痛み解消!ひざ体操 あなたの症状に合わせてできる』(NHK出版)などがある。