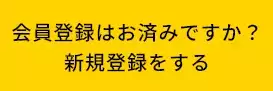1. ふだんの掃除で「見て見ぬふり」をしている場所はありませんか?
窓や網戸、家具の隙間——。いつかは掃除しなければと思いつつ、「見て見ぬふり」をしてしまう場所ってありますよね。照明器具や天井といった高い場所の掃除も、わざわざ脚立を使わなくてはいけなかったりして、とても面倒です。しかし、だからといってずっと放置するわけにはいきません。年に一度の大掃除だからこそ、ふだんは掃除しない場所まですっきりキレイにしちゃいましょう!
そこで本記事では、掃除研究家兼お掃除ライターのおそうじペコさんに教えてもらった、「ふだんの掃除でなかなか手が回らない場所」を掃除する際のアイデア&テクニックを紹介します。
掃除に使用するグッズは、100円ショップで購入できるものばかり。やり方がわかれば手軽に、そしてスムーズに進めることができるので、しっかり読んで実践してみてください。すみずみまでキレイになると、家の雰囲気が今まで以上に明るくなるかもしれませんよ。
2. 窓まわり&ベランダの掃除では、使い古したスポンジが大活躍
窓まわりやベランダは、掃除を後回しにしがちな場所の代表格です。本当なら、雨や風にさらされて汚れやすいからこそ、こまめに掃除したいところですが……。「家の中とは勝手が違う分、やり方がよくわからない」と、ほったらかしにしている人も多いのではないでしょうか。
確かに、ベランダは落ち葉や砂ぼこりなどが入り込み、家の中とは違った汚れ方になります。しかし、屋外にあるからといって、思いっ切り水をまいてブラシでゴシゴシこするというわけにもいきません(マンションならなおさらです)。面倒に感じるのも当然ですよね。
「その気持ちはわかります。でも、ポイントを押さえて取り組めば、効率よくキレイにすることができるんですよ。例えば、ベランダの床は、湿らせた新聞紙を利用すればラクにほこりを集められます」と教えてくれたのは、おそうじペコさんです。
おそうじペコさんがいうには、湿らせた新聞紙をちぎって丸め、ベランダ全体にまいてからほうきではくと、砂ぼこりや土ぼこりが新聞紙に吸着し、ほこりが立ちにくくなってラクに掃き集めることができるのだとか。なるほど、理にかなった道具とやり方を覚えれば、そう難しくはなさそうです。さっそく、他の場所の掃除術も伝授してもらいましょう。
窓まわり&ベランダの掃除で用意するグッズは、以下のとおりです。
・スクイージー(水切りワイパー)
・炭酸水
・マイクロファイバークロス
・スポンジ
・ペンキ用のはけ(3cm幅)
・ピンセット
・氷用トング
1.窓
スプレーボトルに入れた炭酸水を窓全体に吹きかけ、水でぬらして絞ったスポンジで炭酸水を全体に塗り広げましょう。炭酸水に含まれる二酸化炭素には汚れを浮かせる作用があるため、スクイージーで水気を拭き取れば、汚れがすっきり落とせます。
スクイージーをかけたあと、乾いたマイクロファイバークロスで仕上げ拭きすると、さらにきれいになりますよ。
2.網戸
網戸の掃除は外側からスタートします。バケツに水を張り、スポンジにたっぷりと水をふくませたら、網戸の目を意識しながら上下左右に拭きましょう。内側はスポンジの水気をよく絞ってから拭いてください。仕上げに水でぬらして固く絞ったマイクロファイバークロス(窓ガラス・鏡用)を使い、水気を拭き取ります。
「使い古したキッチンスポンジや風呂掃除用スポンジは、捨てずにとっておいて網戸掃除に活用しましょう。水をよく含むうえに、網戸にひっかかることもないので上手に掃除できます」(おそうじペコさん)
3.ベランダの溝
溝や排水口にたまった落ち葉や砂ぼこりは、ほうきでは取り除けません。大きなゴミは氷用トングで取り除き、細かい砂ぼこりはペンキ用のはけで掃き集めた後、厚紙などで回収しましょう。
4.サッシのレール
バケツに水を張り、ペンキ用のはけをぬらしながらサッシのレール部分のほこりをからめとると隅の方の汚れまで簡単に落ちます。仕上げに、固く絞った雑巾をピンセットでつまみ、細かい部分を拭き上げます。
なお、ゴミやほこりが舞い散らないように、ベランダ掃除はできるだけ風の弱い日を選びましょう。

3. 高い場所&足元の掃除は、「上から下」が基本です
一見、きれいに見える部屋であっても、視点を変えてじっくり見てみると、思いのほかほこりや汚れがたまっているものです。特に気をつけたいのは、目線より高い場所と床に近い足元。これらの場所は目につきにくいため、つい放置してしまい、知らず知らずのうちにほこりや汚れが蓄積してしまいます。
高い場所を掃除する場合は、「上から下へ」の順番で行うのが基本です。家具の上や照明器具などのほこりをはらい落としてから、腰の位置ぐらいのテーブルや棚の上を掃除し、最後に床のゴミやほこりを集めましょう。そうすることで、二度手間を防ぐことができますよ。
高い場所&足元の掃除では、以下のグッズを用意してください。
・アルカリ電解水配合使い捨てシート
・ハンディーワイパー(ヘッドが薄いタイプ)
・お掃除手袋(手袋型のモップ雑巾)
・住宅用中性洗剤
・歯ブラシ
1.照明器具
お掃除手袋をはめ、シェード全体をなでるようにしてほこりや汚れを拭き取りましょう。「マイクロファイバー素材のお掃除手袋は、直接触れて小回りも利くため、高い場所や複雑な形状のものを掃除するときに便利です。カーテンレールの上や電気コードなどの掃除にも活躍しますよ」とはおそうじペコさんの言葉です。
ただし、照明器具を掃除する際は、スイッチを切り、十分に温度が冷めてから行うようにしてください。
2.冷蔵庫の上
冷蔵庫の上のベトつきは、油を含んだほこりが原因。油汚れは酸性なので、アルカリ性の洗剤で中和させるのがポイントです。アルカリ電解水配合のシートを使って、汚れを拭き取りましょう。一度で汚れが取り切れない場合は、数回繰り返してください。
3.壁の巾木(はばき)
巾木というのは、壁と床の境目に取り付けてある部材のことです。なくてもよさそうに見えますが、この部材には壁と床の隙間をふさいだり、掃除機やモップがぶつかる衝撃から壁を守ったりする役目があるんですよ。
巾木を掃除する際は、まずドライシートやモップでほこりを除去します。ほこりがあると汚れを塗り広げてしまうためです。次に水を入れたバケツを用意しましょう。その後、住宅用中性洗剤を含ませた歯ブラシで汚れをこすり、歯ブラシが汚れたらバケツの水で洗ってください。これを何度か繰り返し、最後にぬれた雑巾で仕上げ拭きをすれば完了です。
「こするときは、あまり力を入れすぎないようにしてください」(おそうじペコさん)
4.家具の下の隙間
ベッドやキャビネットなどの下は、ドライシートを取りつけたハンディーワイパーでほこりを拭き取りましょう。ほこりが舞い上がらないように、ワイパーは床をすべらせるように動かしてください。
ウェットタイプのシートで水拭きすると、ほこりやほこりについた細菌などが床に広がってしまうので、ドライシートを使うのがおすすめです。

4. 浴室の天井やドアもしっかり掃除して、清潔さを保ちましょう
浴室の掃除方法については、別記事「大掃除の効率をアップするラク家事講座 浴室・洗面所」でも解説しましたが、ここでは「ふだんあまり掃除をしない部分」に絞って、掃除術を紹介していきます。
活用するグッズは、以下のとおりです。
・フローリングモップ
・消毒用エタノール
・クエン酸(粉末タイプ)
・歯ブラシ
・ラップ
1.天井
浴室の天井は、柄の長いフローリングモップを使うことで楽に掃除できます。
浴室はカビが発生しやすい場所です。カビの胞子は天井につきやすいため、消毒用エタノールを含ませた雑巾をフローリングモップに取りつけ、天井全体を拭きましょう。
2.鏡
スプレーボトルに200mLのぬるま湯(40℃ほど)とクエン酸(粉末タイプ)小さじ2を入れ、よく混ぜてから鏡にスプレーします。その後、鏡に密着するようにラップを貼りつけ、15分ほど放置してください。ラップをはがしたら、そのラップを丸めて円を描くように鏡全体をこすり、最後に水で洗い流しましょう。
「クエン酸の成分が残ったままだと素材を傷める原因になるため、パック後はしっかりと水で洗い流してください。ちなみに、クエン酸も100円ショップで手に入ります」(おそうじペコさん)
3.ドアの内側
ドア内側のガラス面(あるいはアクリル板)に付いた汚れは、ほとんどがシャワーで飛び散った石けん類のカスや水垢です。汚れはアルカリ性のため、掃除には酸性のクエン酸水を使いましょう。
まずは、鏡の掃除と同じ要領でクエン酸水を作り、ドアのガラス面やアクリル板に吹きかけます。5分ほど放置して成分をなじませたらスポンジで軽くこすり、水で洗い流してください。
5. まとめ
「ふだんの掃除では手が回らない場所」を取り上げて、掃除のポイントをお伝えしてきましたが、参考になりましたか? 記事内容とダブる項目もありますが、掃除の際は次の点を意識するようにしてください。
●上から下に掃除する
キレイにした所にゴミが落ちたり、汚れがついたりすると二度手間になってしまいます。「上から下へ」をきちんと守りましょう。
●取れにくい汚れがあれば、あらかじめ洗剤をなじませる
「酸性の汚れにはアルカリ性、アルカリ性の汚れには酸性」を基本に、洗剤をなじませておけば、掃除がはかどります。掃除がはかどれば、「面倒」「大変」と感じることもなくなるはずです。
●不要なものはできるだけ処分する
あまり掃除をしない場所には、余計なものが置いてあったりしがちです。効率よく掃除を進めるためにも、不要なものは処分しておきましょう。
また、何も準備せずに始めてしまうと、「時間が足りなくて、掃除したい場所が掃除できなかった!」ということにもなりかねないのでご注意を。それぞれの項で紹介したグッズを準備したうえで、計画的に大掃除を進めてください。
監修:おそうじペコ さん
おそうじペコ
掃除研究家・掃除ライター。ハウスキーピングコーディネーター2級、掃除能力検定士5級。2007年、掃除好きが高じ、自身のブログを「おそうじペコ」として公開。毎日の掃除を丁寧に、しかし無理せず楽しむ姿勢や、汚れを落とすための緻密な研究が評判となり、またたくまに人気ブログとなる。2008年、地球洗い隊「大そうじ大賞2007」グランプリを受賞。