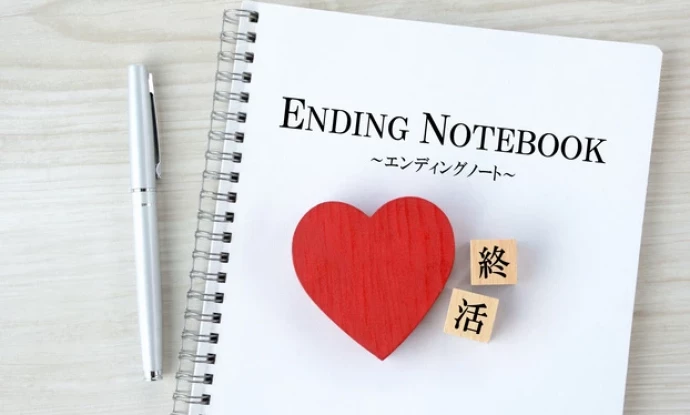1. ひとり娘はいるが、老後に過度な負担は掛けたくない
10年前に離婚をして、東京都郊外の賃貸マンションで、大学生の一人娘・美咲さん(22歳)と二人で暮らしている北村真由美さん(56歳)。真由美さんは、神戸市内の一戸建ての実家で一人暮らしをしている母親の北村好子さん(83歳)が転倒して入院したことをきっかけに、好子さんとともに、親子で「終活」に取り組むようになりました。
母親の好子さんの終活については、今のうちに好子さんの希望をしっかりと聞いておくことで、介護などで外部の力も借りながら、娘である自分が離れた場所から見てあげようと決心しました。
しかし、自分自身の身にもいつか必ず訪れる老後とその先については、いったいどうしたら良いのか、無条件に娘の美咲さんに頼んでよいのか、と考え込むようになりました。
真由美さんは、周囲からは「気が早すぎない?」と言われますが、60歳代の芸能人が急に亡くなる最近のニュースなどを見ていると、決して早すぎることはないと考え、自分自身のエンディングについての準備を開始しました。
ひとつの選択肢は、やはり唯一の直系の親族となる一人娘・美咲さんを軸として備える方法です。
とはいえ、今まだ22歳の美咲さんが、これから先、どんな家族構成でどんな人生を送っていくのかは、まったくわかりません。大学卒業後は得意の英語を活かして海外で働く計画を立てているようです。
したがって、真由美さんが一番重視したいのは、「美咲に過度な迷惑をかけたくはない」ということ。どのような備えをしたら良いでしょうか。
2. 老後への備えは、人生の棚卸しをすることから
まずやらなければならないことは、真由美さんの人生の棚卸しです。
母親の好子さんの終活を手伝っているとき、真由美さんは、あまりにも自分が母親のことを知らないということに愕然としました。
真由美さんは、自分自身の老後とその先のことを、一人娘の美咲さんを軸にして、どんどん外部委託をすることを想定しています。
そうであれば、美咲さんはもちろん、美咲さんから委託されて将来、真由美さんの世話をすることになる人たちに、これまでの真由美さんのことを、ある程度知っておいてもらった方が良いと思いました。
真由美さんは、要介護3以上で自宅での生活が難しくなった高齢者が主に入居している特別養護老人ホームに勤務する友人から、こんな話を聞きました。
特別養護老人ホームでは、入居する時点で既に正常な会話が困難になってしまっているケースが多く、入居者の人柄や性格、好きなことや嫌いなこと、どんな成育環境や学習歴、職歴を持っているかなどについて、入居者本人から聞き出すことが出来ない。すると、本人に寄り添った介護を行うことが難しく、本人にも介護する側にとってもストレスが溜まりやすいのだそうです。
お子さんがないご夫婦で、頼りにしていた夫に先立たれてしまった女性(86歳)は、既に認知症が進んでいる状況で、15年ぶりに会った姪っ子が苦労してこの特別養護老人ホームに入居させたのですが、彼女も本人のことについてはまったく知らない状況でした。
突然夫に先立たれたショックもあり、鬱々として落ち込んだ精神状態が続いており、特別養護老人ホームのスタッフが、合唱・書道教室・買い物イベントなど何か楽しいことに誘い出そうとしてもまったく反応がなかったそうです。このままでは老人性鬱に移行してしまうと懸念していたところ、たまたま食堂のテレビでプロ野球のナイター中継をやっていた映像に釘付けになっているのに職員が気付き、この女性がプロ野球の読売ジャイアンツの大ファンだったということが分かったそうです。
それ以来、姪っ子に自宅マンションからジャイアンツのファングッズや応援グッズなどを持参してもらうなどし、職員もプロ野球の話題を取り上げるようにしたところ、この女性の警戒感は薄れ、笑顔が出るようになり、やがて特別養護老人ホームでの生活に溶け込むようになったそうです。
3. 老後に世話をしてくれる人に、人生の積み重ねを知らせる準備を
これはほんの一例ですが、生まれて間もない乳幼児の世話と違って、それぞれ違った人生を歩んできたお年寄りですから、寄り添い方にもそれぞれ違いがあって当然です。そして、その違いを老後に世話をしてくれる人に見つけてもらうには、その方のこれまでの人生を熟知している人に聞くか、これまでの人生を知らせることのできるツールを用意しておくべきでしょう。
したがって、「人生の棚卸し」として当然記録しておくべき年金収入や資産残高などの情報とともに、本人の尊厳に関わる情報も非常に重要になる場面があることを、真由美さんはしっかり認識し、準備しておくことにしました。
4. 老後に求められる重要な意思決定についての回答を用意しておく
次は、これからの人生における自己決定です。住まい、医療、介護、そして亡くなった後の葬儀・納骨など、老齢期からその先には、重要な意思決定を求められる場面が数多く訪れます。
しかし、その重要な意思決定は、それが必要とされる時期には、自分自身で完結できないことがほとんどです。少なくとも亡くなった後については、自分自身で完結させることは絶対にできません。
そこで、各場面で求められる可能性のある意思決定について、場面ごとに分けて元気なうちに答えを用意しておくのです。
「自宅で一人暮らしを続けたいけれど、こういう状況になったら老人ホームへの入居を考えたい」
「口から食べ物が食べられなくなり、もう回復の見込みがないと医師が判断したら、無理に胃ろうや経管で栄養摂取をさせないでほしい」
「死亡後、遺影や位牌など、引き継がなければならないものは、一切用意しないでほしい」
こうした自己決定をしっかりと残しておくことにより、実際に必要な場面において、意思決定を求められる美咲さんが決断に困ることがなくなるでしょう。
5. 「エンディングノート」は、見つけてもらってこそ意味がある
こうしたことを書き記したものが、いわゆる「エンディングノート」です。エンディングノートはどの自治体でも無料で配布していますし、100円ショップでも売っているほど、高齢者の間では普及しています。
しかし、実際にエンディングノートを書き終えて活用している人は、ほとんどいないといわれています。
年齢に関わらず、人生はいつ何が起こるか分かりません。エンディングノートはすべてを書き終えて完成させるのではなく、書き終わったパートから、老後とその先を託す予定の人、真由美さんの場合には美咲さんに渡していかなければなりません。完成前に渡してすべてを見られることに抵抗があるのなら、少なくともどこにしまってあるかを伝えておくべきです。
そうでなければ、せっかく書き記したエンディングノートは誰にも見つけてもらえず、真由美さんの自己決定が絵に描いた餅に終わってしまいます。
真由美さんはエンディングノートの最後に、こんなメッセージも残しておきました。
「美咲には、ママの世話に大切な時間や労力を使ってほしくありません。いざというときの大切な決断は美咲にお願いをしておきますが、それ以外のことは、どうか『娘だからやらなければならない』と思わずに、お仕事としてプロに依頼してください。そのためのお金は、これからしっかり準備しておきます。美咲の時間や労力をママの世話に使わせないということが、ママの将来の尊厳を守ることだと認識してください」