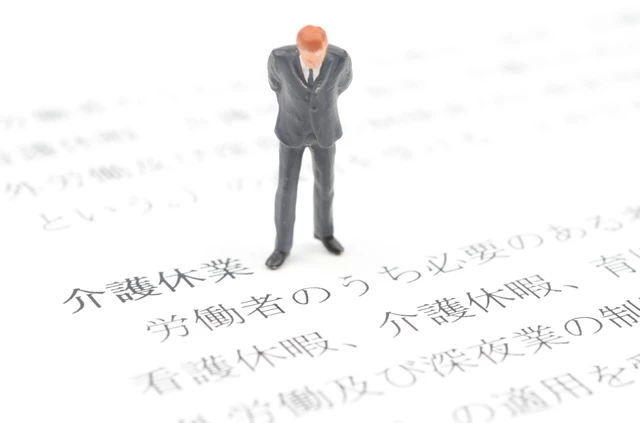1. 女性に負担がかかる傾向が強い介護の現状
厚生労働省が公表している「令和5年版高齢社会白書」によると、65歳以上の要介護者数は増加傾向にあり、特に75歳以上の割合が高くなっています。具体的には、65歳から74歳の人口に占める要介護者の割合は3%であるのに対し、75歳以上になると、23.4%が要介護の認定を受けているのが実情です。
そして、要介護者を介護する人については同居している人が約54.4%を占め、別居している家族も約13.6%となっています。ここで注目したいのは介護者の性別で、男性が35%、女性が65%と、圧倒的に女性に負担がかかっていることです。
また、要介護度が高くなるにつれて終日介護が必要な割合が増えており、要介護5となるとそのうち約57%が終日介護を必要としています。そのため、介護と仕事の両立が難しく、実際介護を理由に離職する女性の割合は、離職者全体の75.8%を占めているのです。
そこで政府は、せっかくのキャリアやスキルを介護が理由で手放すことのないよう事業者に対し、社内における介護休暇制度、そして介護休業の体制づくりを推進しています。
2. 仕事と介護の両立をサポートしてくれる「介護休暇制度」とは?
介護休暇制度とは、家族の介護や通院の付き添いのほか、介護サービスの手続きやケアマネジャーとの打ち合わせのために、年間5日まで1日単位もしくは時間単位で休暇を取得できる制度です。仮に介護対象家族が2人以上いる場合は、年間で取得できる休暇数が10日まで延長されます。
●要介護状態とは?
介護休暇制度でいう要介護の状態とは、以下の状態を指します。
・ケガや病気もしくは身体や精神の障害によって、2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態
●対象となる労働者、ならない労働者
原則として、介護の対象となる家族を介護する労働者が対象ですが、以下に該当する場合は対象外となりますので、注意が必要です。
・日々雇用される人
・下記の条件に該当する場合、介護休暇を取得することができないという労使協定を締結している人(ただし、③については1日単位で介護休暇を取得することができる)
①入社6カ月未満である
②一週間の所定労働日数が2日以下である
③時間単位で介護休暇を取得することが困難だと認められる業務に従事している
●対象となる家族の範囲
介護休暇制度を取るための対象となる家族の範囲は広く、配偶者をはじめ、本人の父母や祖父母、子ども、孫、兄弟姉妹のほか、配偶者の父母も含まれます。子どもについては、法律上の親子関係にある必要があり、養子も対象です。
●介護休暇制度を取るための手続き
特に所定の様式が定まっているわけではありません。会社の規定で様式や手続きが決まっているかを確認し、それに沿った手続きを行いましょう。また、口頭で申し出ることも可能です。会社で特に規定がないなら、まずは上司に相談することをおすすめします。
3. 介護休暇より長期で休暇がとれる「介護休業」とは?
介護休業とは、家族の介護のために一定期間会社を休む制度で、介護が必要な家族1人につき3回まで、通算して93日まで休むことができます。一度に93日休んでもいいですし、3回に分けて休暇を取得しても構いません。
介護休業は、介護に関する自治体への手続きや、地域包括支援センターもしくはケアマネジャーとの相談や、介護サービスの手続きなどの目的で利用できます。長期での休暇が取れるため、休業中に家族で今後の介護方針を話し合ったり、介護のために活用できる事業者や地域サービスを探すこともできます。
介護休業を取得するための家族の要介護状態は、介護休暇制度と同じです。さらに、対象となる家族の範囲も介護休暇制度と同じですので覚えておきましょう。
●対象となる労働者、ならない労働者
原則として、介護の対象となる家族を介護する労働者が対象です。ただし、以下に該当する人は除きます。
・日々雇用される人
・下記の条件に該当する場合、介護休暇を取得することができないという労使協定を締結している人
①入社1年未満である
②介護休業を申し出る日から93日以内に雇用期間が終了する
③1週間の所定労働日数が2日以下である
また、パートやアルバイトなど、期間を定めて雇用されている場合は、介護休業を申し出る時点で、介護休業を取得する予定日から起算して93日を経過する日から6カ月後までに、現在の雇用契約が満了し、かつ更新されないことが明らかでない(引き続き雇用されることが見込まれる)という条件を満たさなければなりません
●介護休業を取るための手続き
介護休業を取得するには、休業開始予定日の2週間前までに書面で会社に提出し、手続きを行わなければなりません。
提出の際には休業終了予定日を記載する必要がありますが、介護状態によっては休業期間を延長しなければならないケースもあり得ます。その際には、休業終了予定日よりも2週間前までに会社に申し出ることで、休業終了予定日を延長できます。ただし、延長できるのは1回の申し出につき一度だけですので、注意しておきましょう。
4. 時短、所定外労働の制限など併せて利用したい制度
政府は介護休暇制度や介護休業のほかにも、以下のような措置をとることを事業主に対して推進しています。実際に利用できるかは勤務先の規定によって異なりますが、規定の内容を確認し、積極的に利用しましょう。
①短時間勤務などの措置
企業は、介護休暇制度や介護休業を利用した日から3年以内の期間で、2回以上可能な「短時間勤務制度」「フレックスタイム制度」「時差出勤」「介護費用の助成」などの措置を講じなければならないとされています。
なお、この措置については期間を定めて雇用される者も対象となりますが、以下の条件に当てはまる労働者は対象外となります。
・日々雇用される人
・下記の条件に該当する場合、短時間勤務措置の適用除外としている労使協定を締結している人
① その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
③所定外労働および時間外労働などの制限
介護が必要な状態が終了するまでの間、残業時間を制限してもらえます。また、時間外労働についても介護が終了するまで、1カ月につき24時間、年間150時間までに制限されます。さらに、午後10時から朝5時までの深夜業も制限の対象です。
なお、「所定外労働の制限」の利用については、以下の条件に当てはまる労働者は対象外となります。
・日々雇用される人
・下記の条件に該当する場合、短時間勤務措置の適用除外としている労使協定を締結している人
① 入社して1年以内の労働者
②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
「時間外労働の制限」の利用については、以下の条件に当てはまる労働者が対象外となります。
・日々雇用される人
・入社して1年以内の労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
※なお、「所定時間外労働」とは、就業規則などで定められている勤務時間を超える労働、いわゆる残業のことを指し、「時間外労働」とは、法定労働時間(原則1日8時間、1週間で40時間)を超える労働のことを指します。
5. 介護休業給付金も活用しよう!
介護休業は雇用保険の対象のため、要件を満たせばハローワークに申請することで「介護休業給付金」を受け取れます。申請は介護休業が終了した日の翌日から2カ月後の月末日で、直接ハローワークに申請するのはなく、会社を通して申請しなければならない点に注意しましょう。
申請することで日額賃金の67%を休業した日数分受け取れます。ただし、受け取れるのは同じ介護対象家族について93日を上限に3回までであることや、介護休業中の賃金が休業前の80%未満であることなど、さまざまな要件を満たす必要がありますので、申請の際には事前に会社の担当者に相談するようにしましょう。
6. まとめ
仕事をしながら介護を行うための介護休暇制度、介護休業について、また活用したい給付金制度について解説しました。介護のためにキャリアやスキルを手放すことのないように、仕事と介護が両立できる制度をうまく利用しましょう。
7. 監修者プロフィール
新井智美(あらい・ともみ)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
福岡大学法学部法律学科卒業。 2006年11月、世界共通水準のFP資格であるCFP®認定を受けると同時に、国家資格である1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。 2017年10月に独立し、コンサルタントとしての個人向け相談や、資産運用などにまつわるセミナー講師のほか、大手金融メディアへの執筆および監修に携わる。