本、そして読書という行為を通して自分を問い直す──そんな企画が始まります。単なる本紹介や書評ではなく、いくつになっても自分をアップデートしていける手段としての「読書」を掘り下げ、より良い自分を追求していきたい、と考えたからです。案内人は、東京・荻窪の個人書店店主で著述家としても活躍している辻山良雄さんです。
街なかで本屋をやっていると、その時代の空気に触れたと思う時がある。
売れる本の傾向、それを手にする人の表情、その人が店内にいる時の様子……。それは必ずしも明文化されているわけではないが、そうした一切に、この時代を包みこんでいる空気が貼りついている。
そして今店内にいて強く感じるのは、みなとても不安そうにしているということだ。
それは無理もないだろう。いま目にするニュースと言えば、相次ぐ自然災害や気候変動、終わらない戦争。そして近くを見れば物価高で生活は困窮、SNSには、感情をそのまま吐き出したようなざらついた言葉ばかりが流れてくる。そうした言葉に触れているだけで、少しずつ自分が失われていくということはあるのではないか。
その一方で、何か不安だ、しんどいと思った時、〈本〉はただひと時そこに自分を没入させるだけで、自らを回復させてくれる避難所(シェルター)になり得る。どこにもつながっていないそのしんとした空間にいるのは、基本的には読者一人だけ。本は自分が主体的にならないと進まず、そこにある言葉の多くはすぐには役に立たないものかもしれないけど、だからこそ人を損得の関係から解放し、本来の〈わたし〉に帰らせてくれる力がある。
人はいくつになっても、その人が読んできたものや、触れてきたものからできている。この場所でわたしは、そうした〈わたし〉をつくる本を紹介したい。それはできるだけ早く、たくさん知識を詰め込みたいという読書とは違うかもしれないけど、この小さな店から見ている限り、「求められているのはこちらでは?」と、根拠のない開き直りが心のうちに湧いてくる。今回は初回ということもあるので、「読む」という行為そのものについて考えさせる本から、いくつか紹介したい。
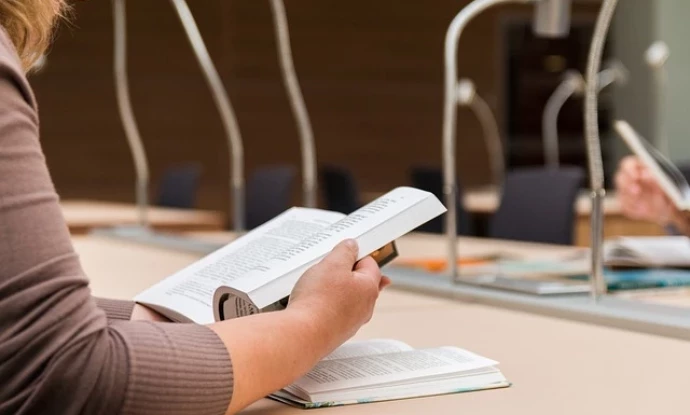
「読む」ことについてくり返し語っていたのは、詩人の長田弘だ。『読書からはじまる』(ちくま文庫)という、いくつかの講演草稿をもとに書き下ろされたエッセイには、長田の本を読むことに対する考えが力強く、グッと静かに押し込んでくるような言葉で書かれている。タイトルから想像されるような、読書のすすめといった内容ではなくて、あくまでも「読む」ことと人との関わりについて触れられた本。そのまっすぐに差し出された言葉には、よき師を思わせるような響きがあって、読み進めるうちにクセになっていく。
長田は、人間の根本には「初めに言があった」という。
「人間は言葉のなかに生まれて、言葉のなかに育つのであり、そうして、言葉のゆたかさを手に入れた人だけが幸いな人であるだろうという事情は、何一つ変わっていない」。(P.84より)
言葉は、それが差す意味がすべてなのではなく、それをどのように使うか――みなが同じマフラーを持っていたとしても、それを自分はどう結ぶのか――が重要なのだ。そして彼は、「これがわたしだ」という言葉、自分の本質的なありようを確かにする言葉を貯めていく行為が読書なのだと説く。
そうした言葉の在り処、図書館こそが〈本〉なのだ。それはいつでも閲覧できるものだから、たくさん読まなくたって構わないし、むしろ積極的に忘れるべきである(だから人は再読するし、そうした何度も手を伸ばしてしまう本がその人のための本となる)。そう言ってもらえると、なんでもすぐに忘れてしまうわたしなどは安心してしまうが、そうした闊達さがこの本にはあって、例えば彼は、読書にまず必要なのは〈本〉ではなく〈椅子〉なのだと明言する。
まずは、読むための椅子を手に入れること――いまは、本を読むことに特化した店もつくられている時代だから、そうしたハードウェアの重要性に早くから気がついていたのはこの人の先見性だろう。それは読むことを含めた自分の生活をどのように捉えるかということで、自分の避難所は、自分でつくらなければならないということだ。
写真下:『読書からはじまる』 長田弘著 筑摩文庫
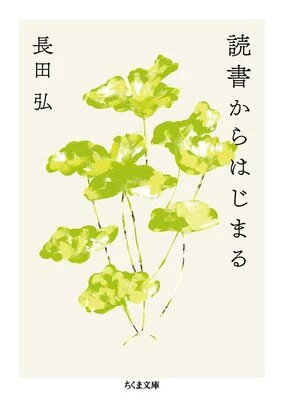
そうした〈本〉とともにある人生を、自分が実際に手にしてきた本を一冊ずつ広げるようにして書いたのが、翻訳家である斎藤真理子のエッセイ『本の栞にぶら下がる』(岩波書店)だ。本はゆっくりゆっくりその人に浸透していくもので、あとからその因果関係を具体的に指し示せるものではないが、そうした染み込んでいくという体験の持つゆたかさが、本書を読めば随所に感じられる。
現在と過去。
このエッセイでは、そうした二つの時間を何度も行き来することになる。過去という時間には、斎藤さんがその本を読んだ時間、そして読んだ本で語られている時間が含まれるが、いまという時の薄皮を静かにめくり、そっと覗き込んでみれば、そこにはいま・ここに注ぎ込んでいるさまざまな人生、熱い血が、まだそれが生きていた時の生々しさをもって、脈々と流れているのだ。
川崎の、多摩川沿いの町工場の在日コリアンを書いた永山則夫の「土堤(どて)」。同時期に同じ雑誌で活躍した、仲村渠(なかむら・かれ)とチョン・ジヨンという沖縄と朝鮮の詩人をめぐる話など、ともすれば時代という波の向こうに消え去ってしまいそうな弱きもの、小さきものの姿が、本書では忘れてはならぬものとして彫り深く描かれている。そして彼らは、このように文章としてふたたび書かれることで、いまこの時代に起こっている出来事と軌を一にして、切実なものとしてこの世界に立ち返ってくる。
「どんなに古い本にも、今につながる栞がはさまっている」(P.201より)
斎藤さんは「自分が思いつくのは古い本のことばかり」だと書いているが、それは自分のほんとうに身についた本しか語ることができないという誠実さの現れだと思う。そして一個人に深く染みついた本であったからこそ、その本は同時代性を持つことにもなったのだろうが、そのようにして「読む」ことは、それを読む個人すらも乗り越えていくものなのかもしれない。
写真下:『本の栞にぶら下がる』斎藤真理子著 岩波書店
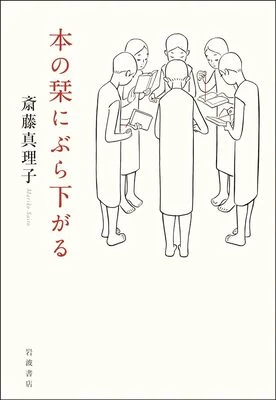
わたしたちはいったい何を読んでいるのか? 「読む」ことにかけられた長い時間を体現したように見える本が、石川美子『山と言葉のあいだ』(ベルリブロ)だ。石川さんはフランス文学を専門に、哲学者ロラン・バルトの著作の翻訳なども手掛けてこられた方で、この随筆集もそうした専門分野を下敷きとしているが、同時に自身が人生の折々で出合った〈山〉の姿が重ね合わせるようにして描かれていて、余韻を残す。
わたしも若いころは山に登っていたが、特に串田孫一や深田久弥という名前を持ち出すまでもなく、山と文学というものはふしぎと相性がいい。わたしが知っている単独行が好きな先輩は、夜テントの中で本を読むのが楽しみで、わざわざ一人で山に行っていると話してくれた。
「ひとつの山をいくどとなく眺めてきたひとは、いま目に見えている山のすがたの中に、かつて見たいくつもの景色と過ぎ去った自分の時間とが重層的に内包されているのを感じとるのである」(P.198より)
本書で石川さんはそのように書いているが、ここで山を見ている人は、同時に自らの内にあることばをも読み取っているのだと思う。
かつての記憶や、果たせなかった思い、それでもいまこうしてこの場にいるという納得……。そうしたはっきりとした形をとらないことばが、そこにある山が契機となって次々と導き出されてくる。そうしたことばこそが〈わたし〉なのであり、先ほどの長田弘の言葉を借りれば、「自分の本質的なありようを確かにする言葉」でもあるのだろう。そして、人生や思いを託すことのできることばをたどれば、そこには何十年、何百年にわたり、大勢の人がそこに立ち返ってきた〈本〉というものがあるのだ。
本書ではスタンダールやアレクサンドル・デュマ、バルザックといった文学者の人生の断片が次々に描かれるが、それは彼らの文学に親しんできた石川さんにとっては必然の、〈わたし〉をつくった言葉なのだと思う。
写真下:『山と言葉のあいだ』石川美子著 ベルリブロ
※次回は6月に掲載の予定です。
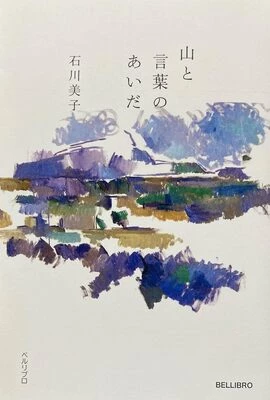

著者:辻山良雄
辻山良雄(つじやま・よしお) 1972年兵庫県生まれ。大手書店チェーン〈リブロ〉を退社後、2016年、東京・荻窪に本屋とカフェとギャラリーの店Titleを開業。書評やNHK「ラジオ深夜便」で本の紹介、ブックセレクションもおこなう。著書に『本屋、はじめました』『365日のほん』『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』、画家のnakabanとの共著に『ことばの生まれる景色』がある。最新刊は『熱風』誌の連載をまとめた『しぶとい十人の本屋』(朝日出版社)。撮影:キッチンミノル