「ショートステイ」というサービスは知っていても、「こんな個人的な理由で利用していいの?」と一歩を踏み出せない人は多いかもしれません。そこで今回は、よく知られているショートステイの利用シーンを紹介。ショートステイを少しでも身近に感じもらい、利用のハードルが下がるような情報をお届けします。
まずは、ショートステイの概要を見てみましょう。ショートステイは在宅介護中、一時的に施設に宿泊し、施設の職員が介護のピンチヒッターを担うサービスです。最短一日から利用でき、生活介助やリハビリを受けられます。特別養護老人ホームや介護老人保健施設など介護保険が使える施設の場合は、要支援1~2、要介護1~5の要介護認定を受けた65歳以上の高齢者が利用できます。また40歳~64歳で特定疾病により要介護と判断された人も利用可能です。一方、有料老人ホームなどが提供するショートステイは、介護認定がない自立した人でも利用できますが、費用はすべて自己負担になります。
次に利用シーンですが、「ピンチのときしか使えないのでは?」と誤解していませんか。利用する理由にルールはなく、介護する側、される側が「必要と思ったとき」に使えるのがショートステイの魅力です。ここでは利用シーンの一例を紹介します。
●家族がリフレッシュしたいとき
介護では、家族が一時的に休みを取り、介護から離れてリフレッシュする「レスパイト(休養)」がとても重要です。ショートステイを利用する間は趣味や外出を楽しむのもよし、頑張っている自分を労わる時間に使ってください。
●冠婚葬祭で自宅を留守にするとき
冠婚葬祭に関しては、お祝いごとは事前に日程がわかりますが、予想できないのがお悔やみごとです。「明日、急に知人の葬儀に行くことになった!」という場合も施設に空床があればショートステイを利用できます。
●仕事が忙しく介護との両立が難しいとき
急に仕事のシフトが変更になったときや、繁忙期にも利用できます。地方では農家が収穫を迎える農繁期に、スキー場関係者がハイシーズンの冬場にショートステイの利用が増えると言います。
●本格的な施設入所の予行練習に
将来の施設入所を見据えて、施設での生活に慣れておくために1泊2日、2泊3日ぐらいの短期で利用するケースもあります。施設での集団生活を経験しておくと、いざというときスムーズに生活の場を移行できそうです。
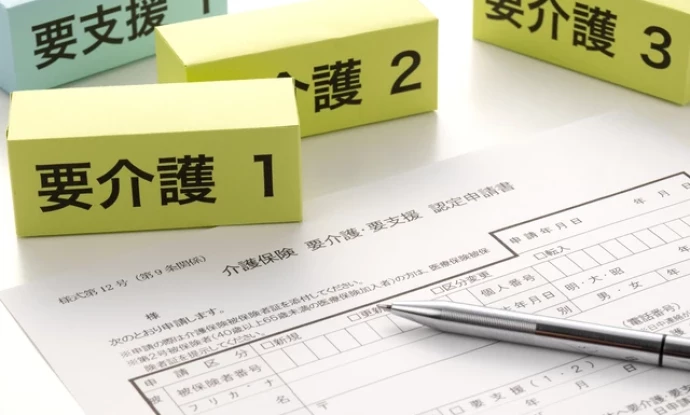
たとえば、引越しが決まり、新居が片付くまで預かってほしい。そんな理由でショートステイを利用しても問題ありません。
その際に大切なのは、介護者が被介護者にショートステイを利用する理由を正直に伝えることです。嘘をついたり、理由を曖昧にしたりすると、何かのきっかけで話がかみ合わなくなったとき家族との信頼関係が崩れ、その後の介護に悪影響を及ぼすことがあります。どうしても納得してもらえないときは別の理由を考えるようにして、認知機能が低下していても、まずは現在の家族の状況を正直に伝えてみましょう。
また、ショートステイは短期間の預かりサービスなので、ずっと施設暮らしが続くのではなく「一週間したらちゃんと家に帰れるよ」と期限をしっかり伝え、先が見通せると不安がやわらぎ利用を受け入れやすくなることがあります。

通所サービスの利用を拒否し、家に引きこもってしまう高齢者は少なくありません。通所サービスでさえ嫌がるのに、ショートステイの利用を促すのはなおさら「高いハードル」と言えます。
そんなときは、経験豊富なケアマネジャーのサポートを借りて背中を押してもらいましょう。上手に説得してショートステイに結びつき、自宅以外の場所で様々な刺激を受けると、通所サービスの利用に結びつきやすくなる可能性も期待できます。
家族が促しても外に出たがらないと、ついイライラして利用者に強く当たってしまうことがあります。家族は悪くありませんが、提案を拒否するのは何か理由があるかもしれません。
たとえば、現役時代にバリバリ仕事をしていた人、役職について人の上に立っていた人ほど、年を取り弱った自分をふがいなく思い、人に会いたくなくなる傾向があります。もともと出不精で自宅が一番、と思っている人もいますし、家族に強い信頼感を寄せている人も外に出ることを嫌います。稀に「妻が作った食事しか食べない!」という人もいるので、強い意思表示の背景に目を向けると、少し冷静になれることがあります。
家や家族に対する思いが強い場合、無理に外に連れ出すと逆効果になるので本人の意思を尊重した対応を心がけましょう。

介護は短距離走ではなく、予めゴールが設定されていない長距離マラソンのようなものです。頑張りすぎると息切れするので、一定の速度を保ちながらゆっくりと進んでいく必要があります。そのためには介護者、被介護者どちらもリフレッシュできる時間を作り、ストレスを溜めないようにするのがとても大切です。
特に心配なのは、介護する側の家族のストレスです。被介護者への愛情や責任感が強いと休むことに罪悪感を抱え、介護疲労に陥ってしまうこともあります。
しかし、よく考えてみると、介護者が倒れたら一番困るのは被介護者です。それで在宅介護をすることが難しくなれば、被介護者の意思に関わらず、施設入居を検討せざるを得なくなるかもしれません。
共倒れしないためには、全力疾走のスピードを緩めて一度立ち止まってみましょう。完璧主義を手放して遠慮なくショートステイを介護プランに組み込み、リフレッシュを習慣にしましょう。


著者:中村雅彦
中村雅彦(なかむら・まさひこ)
JA長野厚生連北アルプス医療センターあづみ病院居宅介護支援事業所主任介護支援専門員。特別養護老人ホームの生活相談員を経て、ケアマネジャーに。前一般社団法人長野県介護支援専門員協会会長、前一般社団法人日本介護専門員協会長野支部長、長野県主任介護支援専門員研修・長野県介護支援専門員専門研修(専門研修課程Ⅰ・Ⅱ)講師、介護予防ケアマネジメント指導者など、介護支援専門員に関する研修指導や、訪問介護・通所介護などの研修活動にも従事。