昨今、日本には毎年のように台風が上陸しており、気象庁が台風の統計を取り始めた1951年以降で、台風が上陸しなかった年は5回のみという事実があります。また、近年は台風や大雨による災害が激甚化しており、被害を防ぐための対策が強く求められるようになりました。一方、台風や大雨は地震と異なり、接近を予測し、事前に避難が可能な災害です。つまり、普段から備えをしておくことで、被害を確実に減らせるわけです。そこで今回は、台風や大雨の対策として普段から備えておくことや取るべき行動、注意点などを詳しくまとめました。いざというときに落ち着いて行動するためにも、高齢者も含めて家族全員で確認しておきましょう。
大雨・台風関連の防災対策でまず行いたいのは、ハザードマップで自宅周辺の浸水や土砂災害の危険度、避難所(公民館や体育館など)をチェックし、適切に避難するための準備をすることです。ハザードマップは自治体で入手できるほか、国土地理院の「ハザードマップポータルサイト」でも調べられます。
「ハザードマップポータルサイト」
その際、同じ浸水想定区域であっても、鉄筋コンクリート造の3階以上に住んでいる場合は「そのまま在宅での避難が可能」で、低い土地で木造建築の1階に住んでいる場合は「早めに自宅を出て避難することが必要」になるケースもあります。自分が住んでいる建物や立地を考慮しながら、適切な準備を進めてください。
「ハザードマップなどを参考にして、自宅を中心に浸水危険度の高い地域や避難先などを書き込んだ、【わが家の防災マップ】を作成するのもおすすめです」と危機管理教育研究所代表・危機管理アドバイザーの国崎信江先生は話します。
「作成にあたっては、避難先までこのマップを携帯して歩き、危険度の高い場所などを書き込んでいきましょう。雨水がどこからどこへ流れ、どこでたまりやすいかなどをしっかり見ておくことで、避難行動がよりスムーズになります」(国崎先生)
避難先は自治体が設置する避難所だけでなく、親せきや知人宅、ホテル、旅館なども想定しておくのがポイントです。それぞれの危険度をチェックした上で、事前に連絡を取って利用の可否や方法、費用(ホテル・旅館)などを確認しておきましょう。徒歩で行くことを想定した避難先なら、普通の雨の日にそこまで歩いて、避難ルートを確認しておくことも大事です。
以下に、避難ルートにおけるチェックポイントも紹介しておくので、【わが家の防災マップ】作りに役立ててください。
〈避難ルートでのチェックポイント(避けるべき危険箇所)〉
●氾濫の危険性のある土手・堤防
●フタのない側溝/用水路
●崩れそうな斜面
●マンホール(フタが外れると落とし穴になる可能性があるため)
●強風で倒れたり、飛ばされたりしそうな建物・設備(煙突、電柱、フェンスなど)
●アンダーパス (道路や線路などの下部にある通路部分)
●高潮の危険性のある岸壁/堤防/海岸沿いの道路

避難先を確認したら、避難する際の非常持ち出し袋や防災備蓄について家族で話し合い、必要なものを揃えておきましょう。家族会議では、避難行動に移るタイミングについて話し合うことも大事です。自治体からの「避難指示」が出たときはもちろん、高齢者がいる場合は、とくに家族の健康状態、過去の災害状況を考慮し、全員が安全に避難できるタイミングを決めておいてください。
「加えて、家族が離れていた場合の緊急連絡の取り方や、停電、断水、電波障害・回線不通などにどう対処するかなども話し合っておく必要があります。家族で決めたことは、メモにまとめて家族全員が常に携帯するようにしましょう。その際、【マイ・タイムライン】を活用するのも1つの方法です」(国崎先生)
マイ・タイムラインとは、大雨や台風に備えて、家族の「誰が」「何をするのか」を時系列で(警戒レベルごとに)まとめ、家族全員で共有する「自分の避難計画」です。たとえば、「私と妻で避難所を確認する」「私が父の薬をもらいに行く」「妻と父で避難開始」などと書き込み、避難行動を明確にしておくわけです。マイ・タイムラインを作成する際、台風接近予想日の3日前、2日前と区切って計画しておくと、より有効活用することができます。裏面に家族の緊急連絡先や非常持ち出し品リスト、避難先の場所や行き方などを記入しておくのもよいでしょう。
国土交通省「マイ・タイムライン」
事前に家族全員で検討することで「想定外」を減らし、いざというときに行動に移しやすくしてください。

適切な防災行動を取るには、大雨・台風に関する正しい情報や最新の情報が欠かせません。気象庁、市区町村から出される、「気象」や「避難」に関する情報の意味を理解した上で、取るべき行動を知っておきましょう。
台風や集中豪雨をもたらすような強い雨雲が近づいてくると、気象庁は予測される雨量や風速などをもとに、防災行動につなげてもらうためのさまざまな注意報や警報などを発表します。
〈主な注意報・警報の種類と内容〉
●大雨注意報:大雨による土砂災害や浸水害が発生する恐れがあると予想したとき
●強風注意報:強風により災害が発生する恐れがあると予想したとき
●洪水注意報:河川の上流域での大雨や融雪によって下流で増水が生じ、洪水災害が発生する恐れがあると予想したとき
●大雨警報:大雨による重大な土砂災害や浸水害が発生する恐れがあると予想したとき
●暴風警報:暴風により重大な災害がおこる恐れがあると予想したとき●洪水警報:河川の上流域での大雨や融雪によって下流で増水や氾濫が生じ、重大な洪水災害が発生する恐れがあると予想したとき
●大雨特別警報:台風や集中豪雨により数十年に一度 の降雨量となる大雨が予想されるとき
各市町村長は、こうした防災気象情報などを確認し、住民に危険がおよぶ恐れがあると判断した場合は、避難情報を発令することになります。なお、市町村が住民に避難を促すために発令する避難情報は、「高齢者等避難」「避難指示」「緊急安全確保」の3種類です。

ここでは、避難情報が発令された際に取るべき行動と、相当する警戒レベルを紹介します。警戒レベルは、災害発生の危険度が高くなるほど数字が大きくなるので、ぜひ覚えておいてください。
〈警戒レベルと住民が取るべき行動〉
●警戒レベル1:災害発生の危険性はまだ低い段階ですが、気象庁から警戒レベル1「早期注意情報」が発表された場合は、最新の防災気象情報に注意 するなど、災害への心構えを高めてください。
●警戒レベル2:気象庁から警戒レベル2「大雨注意報」や「洪水注意報」などが発表され、災害発生に対する注意が高まる段階です。避難に備えて、ハザードマップなどで自分あるいは家族の避難行動を確認しておきましょう。
●警戒レベル3:市町村から警戒レベル3「高齢者等避難」が発令された段階です。避難に時間がかかる高齢の方や障がいのある方、避難を支援する方などは、危険な場所から安全な場所に避難しましょう。土砂災害の危険性がある区域や、急激な水位上昇の恐れがある河川沿いに住んでいる方も、この段階での避難が望まれます。
●警戒レベル4:市町村から警戒レベル4「避難指示」が発令された段階です。対象地域の方は全員すみやかに危険な場所から避難してください。
●警戒レベル5:市町村から警戒レベル5「緊急安全確保」が発令された段階です。すでに災害が発生しているか災害が発生する直前の状況にあるため、ただちに安全な場所で命を守る行動を取ってください。
防災気象情報や避難情報が出されても、情報を受け取れなかったり、受け取るのが遅れたりしては、適切な防災行動につなげることができません。このため、台風や危険な雨雲が近づいている時点から、気象情報や自治体の動きをこまめにチェックする必要があります。
国崎先生は「大雨や台風に関する情報は届くのを待っているのではなく、自分から取りに行くことが大切」として、スマートフォンやパソコンなどで、最新の情報が得られる態勢をととのえておくことをすすめています。
大雨や台風が近づいてきたら、避難の方法を確認する、自宅内外の防災の準備をするなど、限られた時間の中でやるべきことがいろいろあります。大雨・台風が近づく数日前から当日にかけて、家族全員の安全のために「しておきたいこと」「してはいけないこと」を事前に整理しておきましょう。
●大雨・台風の2~3日前
大雨や台風が近づいてきたら、避難先までの経路や行き方、家族の緊急連絡先、非常持ち出し品など、家族会議で話し合ってまとめたことを中心に確認します。備蓄品の点検・補充も重要です。持病の薬の受け取りといった先延ばしにできない用事も、前倒しで済ませておきましょう。
加えて、自宅まわりの対策も忘れてはいけません。強風で飛ばされそうなプランターやゴミ箱などは固定するか、室内に入れておきます。雨戸がきちんと閉まることを確認し、必要があれば窓ガラスの補強も行ってください。道路に排水があふれる原因になる側溝のゴミも、しっかり取り除いておくとよいでしょう。
「浸水想定区域なら、土のうを用意・設置しておきましょう。土のうがない場合は、大きめのゴミ袋に水を入れて水のうを作るのがおすすめです。浴槽・浴室の排水口、便器の中などに水のうを置けば、排水管からの逆流浸水を防げますよ」(国崎先生)
水のうの作り方は次の通りです。
1. 40 ~ 45Lのゴミ袋を二重にして水(約20L)を入れる
2. できるだけ空気を抜いてしっかり縛る
●大雨・台風の前日~当日
「明日にも危険な大雨や台風が最接近しそう」という状況になったら、不要不急の外出は控えてください。浸水の危険があれば、濡れてはいけない備蓄品や電化製品などを2階に運びます。また、断水に備えて浴槽やバケツ、ウォータータンクなどに水をためておきましょう。
いつでも避難行動に移れるように避難準備もととのえ、危険を感じたら「避難指示」が出る前であっても自主的に避難を開始してください。避難先に明るいうちに着けるように、早めに決断することが大切です。避難先に移動するときは長靴ではなく、脱げにくく動きやすい運動靴、マリンシューズなどを履きましょう。傘はささずにレインウェアを着用します。傘が飛ばされたらその傘で誰かがケガをするかもしれません。大雨や台風の真っただ中では、テレビやラジオはつけっぱなしにして最新情報を収集することも大事です。
なお、道路が冠水した場合、歩けるのはせいぜいひざまでの水深です。それ以上になったら在宅避難に切り替えましょう。
「浸水想定区域であっても、道路が冠水するなどして危険だと判断した場合は、迷わず自宅の2階などに避難しましょう。近くに斜面(崖)があれば、できるだけ離れた部屋へ退避するなどして、とにかく命を守る行動を取ってください」(国崎先生)

夏から秋にかけて発生する大雨や台風などの自然災害は、日本各地に大きな被害をもたらしています。また、ここ数年は大雨・台風の影響がほとんどなかった地域が被害を受けるケースも増えており、住んでいる地域がいつ警戒区域になるかわからない状況です。いざというときに落ち着いた行動ができるよう、日頃から対策をしておきましょう。
高齢者は特に災害時に身動きが取りにくく、行動範囲が制限されがちです。在宅介護を行っている場合は、担当の医師やケアマネジャーに緊急時の対応方法や、避難方法についてきちんと確認しておきましょう。万が一に備えて、近隣住民に協力を依頼しておくことも大事です。周囲の人たちと協力し合える環境を作り、より確実な災害対策を行ってください。
監修:国崎 信江さん
国崎 信江(くにざき・のぶえ ※写真下)
危機管理アドバイザー
株式会社危機管理教育研究所 代表
20年以上にわたり第一線で防災・防犯・事故防止対策を提唱している。行政、企業、マンションなどのリスクマネジメントコンサルを行い、省庁の検討・審査委員や自治体の防災アドバイザーなどを務めている。NHKラジオでは10年以上『マイあさ』の「暮らしの危機管理」 のコーナーで情報提供するほか、多くのメディアで被災地の支援活動時の経験や防災防犯普及啓発を発信している。著書に『大切な家族と自分を災害から守る はじめての防災ブック』(ナツメ社)など多数。
https://www.kunizakinobue.com/
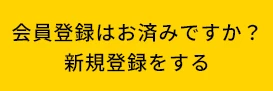

著者:MySCUE編集部
MySCUE (マイスキュー)は、家族や親しい方のシニアケアや介護をするケアラーに役立つ情報を提供しています。シニアケアをスマートに。誰もが笑顔で歳を重ね長生きを喜べる国となることを願っています。