高齢者に対する犯罪の手口は年々巧妙化しており、いつ誰が巻き込まれてもおかしくありません。家族を危険から守るためには、各種犯罪の手口を知ったうえで、日頃から防衛策やルールを決めておく必要があり、高齢者の家族にはとくに注意深く伝えるようにしましょう。今回は、一般社団法人日本防犯学校副学長であり、防犯アナリストでもある桜井礼子さんに、ひったくりなどの街頭犯罪、住宅侵入窃盗、訪問盗の犯罪について、手口や被害事例、対策方法を教えていただきました。
主な街頭犯罪には、ひったくり、自転車盗、オートバイ盗、自動車盗、車上ねらい、自動販売機荒らし、路上強盗などがありますが、ここでは私たちのまわりで頻繁に発生している「ひったくり」についてお話しします。
ひったくりは、みなさんが考えている以上に注意しなければならない犯罪です。単純にバッグ(かばん)を盗られるだけでは済まない、二次被害が発生する可能性があるからです。バッグの中には多くの場合、財布、スマートフォンや携帯電話、家の鍵などが入っています。財布の中に保険証や免許証を入れている人も多く、そこから家の住所を特定されれば、住宅侵入窃盗(泥棒)の被害にあう可能性が高まります。
また、ひったくり被害にあった女性が、スマホの情報からストーカー被害や住宅に侵入され、性的被害にあった事件も発生しています。これらは、ひったくりからほかの犯罪へ発展した、代表的な事例といえるでしょう。
一方、バッグを盗られまいと必死に抵抗して、大けがを負った人もいます。では、こうしたひったくりにはどう対処すればよいのでしょう? 実はひったくりの対策は、決して難しくありません。バッグは建物側に持つか、盗られないように前で抱える。ショルダーバッグはたすきがけにする。夜間は極力明るい道を選ぶ。速足で歩き、ときどき後ろを振り返って「自分は注意しているぞ!」とアピールする。たったこれだけです。逆に避けたほうがよい行為は、歩いているときにスマホの画面を見る、イヤホンなどで音楽を聴きながら歩くなどです。まわりの状況がわからず、危険度が増すので絶対にやめてください。
最近は、ひったくりが「路上強盗」へと凶悪化するケースが多発しており、凶器を使って背後から襲いかかり、バッグを奪うという事件もおきています。徒歩だけでなく自転車に乗っているときに襲われた事例もあり、男女に関係なく被害にあっています。ひったくり・路上強盗は20時以降から深夜にかけて多発しているので、帰宅が遅くなった場合は、最寄り駅からタクシーを利用するようにしましょう。路上犯罪を“自分ごと”と捉えて防犯意識を高め、あなた自身をしっかりと守ってください。
〈POINT〉
● 荷物は前に抱えるか、たすきがけにして、極力明るい道を速足で歩く
● 歩行時はスマホを見たり音楽を聴いたりせず、絶えず周囲に注意を払う

住宅侵入窃盗とは、家に侵入し気付かれずに金品を盗む「泥棒」のことです。そうした泥棒は、留守中に入ってくる「空き巣」、家人が就寝中に入ってくる「忍び込み」、家人が生活中に入ってくる「居空き(いあき)」の3つの手口に分けられます。
その中でいちばん厄介なのは、忍び込みと居空きです。在宅中の家人が、犯人と鉢合わせする可能性があるからです。実際、忍び込み犯と鉢合わせした家人が大きな精神的ショックを受けた結果、長期の入院を余儀なくされたという事例もあります。
また近年は、泥棒が暴力や脅しなどで無理やり盗む、「強盗」へと変化してきています。留守中に侵入し、わざわざ家人の帰宅を待つ「待ち受け強盗」(「入り待ち強盗」ともいう)や、空き巣・忍び込み・居空きで侵入し、家人と鉢合わせになったとき居直る「居直り強盗」などがその一例で、盗みから凶悪犯罪へと発展するケースも少なくありません。
侵入窃盗の被害にあわないためには、「自分が泥棒なら、どこから侵入するだろう」という目線で自宅をチェックすることが大事です。泥棒は入る前に必ず下見をするといわれており、いくつもの防犯対策を行っている家は、泥棒から狙われにくくなります。以下に【泥棒に狙われないための防犯対策】を紹介しておくので、ぜひ活用してください。
【泥棒に狙われないための防犯対策】
●ごみ出しなど短時間の外出でも必ず施錠する
●新聞受け、植木鉢の下などに鍵を置かない
●玄関のドアには鍵を2つ付ける
●窓ガラスには補助錠を付け、CPマークのついた防犯フィルムをガラス全面に貼る
※CPとは「Crime Prevention=防犯」の頭文字で、「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」が制定した共通標章。 防犯性能が高いと認められた建物部品には「CPマーク」の使用が認められる。
●センサーライトや防犯カメラを設置する
●歩くと大きな音がする防犯砂利を活用する
なお、警察庁の統計によると、侵入窃盗被害にあった住宅の約半数が「無施錠」でした。防犯のためには、トイレや浴室などの小窓も必ず施錠することを習慣付けしましょう。自宅の防犯対策について定期的に家族で話し合い、日頃から防犯意識を高めておくのもおすすめです。
〈POINT〉
● 防犯対策をいろいろ行っている家は、泥棒から狙われにくい
● 確実な施錠や窓ガラスの強化で、泥棒に侵入されにくくする

「訪問盗」というのは、文字どおり住宅を訪問し、家人の隙を見て金品を盗む犯罪のことです。聞き慣れない言葉かもしれませんが、実はかなり前からある手口で、近年はこの訪問盗が増加傾向にあります。おそらく、新型コロナウイルス感染症が流行して以降、在宅勤務の人が増え、犯罪者にとって活動しやすい環境がととのっているからでしょう。以下では、実際に起こった訪問盗の事例を紹介します。
都内に住む80代女性の家に、電気工事の業者を名乗る2人組が訪ねてきました。2人は「近くで漏電がありました。ブレーカーを見せてください」といって家に上がり込むと、1人は1階、もう1人は2階を点検し始めます。そして、女性が2階の点検に立ち会っている間に、1階にいる犯人は金品を盗み、何食わぬ顔で帰っていきました。こんなふうに堂々と家に上がり込んでくる相手だと、ついだまされそうですよね。
実はこの訪問盗も、最近は「訪問強盗」へと姿を変えて凶悪化しています。みなさんの中にも「ガスの点検を装った強盗が発生している」というニュースを聞いたことがある人がいるのではないでしょうか? そうした訪問強盗の手口は、「ガスの点検です」と家に上がり込み、家の中に入った途端に暴行を加え、手足を粘着テープで縛り、金品を盗るというもの。被害者は50~90代の人が中心だといわれています。
訪問盗・訪問強盗の犯人たちは、事前にその家の情報を調べ、準備を整えたうえでやってきます。そうした中で、どうすれば被害を避けられるでしょうか? まずは、家にいるときの行動をチェックしてみましょう。人が訪ねてきたときや宅配便の人がきたとき、いきなり玄関を全開にしていませんか? その行為はとても危険です。在宅中でも必ず施錠し、ドアガードやドアチェーンをかけてください。そして、いかなる来訪者が来ても、ドアガードやドアチェーンをかけたままで対応しましょう。玄関まで行かずに、インターホンだけで対応するのもよいですね。
また、「点検です」といわれた場合は、家に入れる前にその地区の電気(ガス)会社へ電話で確認をしてください。電気やガスの点検だけでなく、時には役所や警察を名乗ってくる場合もあるので、すぐに電話ができるように電気やガス会社、警察署、役所などの電話番号を電話の近くに貼っておくとよいでしょう。
犯罪は決して他人ごとではありません。次はあなたの家にやってくるかもしれないので、くれぐれも油断しないでくださいね。
〈POINT〉
●来訪者には、ドアガードやドアチェーンをかけたまま対応をする(できればインターホンだけで済ませる)
●家に入れる前に、その人が名乗った会社などに電話して確認する
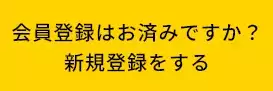

著者:桜井 礼子(さくらい・れいこ)
一般社団法人日本防犯学校副学長、防犯アナリスト。
日本初の女性防犯アナリスト。事件現場の検証と取材に携わり、子育て経験や高齢者がいた経験を活かして、女性・母親・高齢者の親を持つ立場で皆様と同じ目線に立ち、自分自身で出来る防犯対策を始め、子供と高齢者・女性を守る防犯対策を分かりやすく解説。弱者を犯罪被害から守る予知防犯を提唱する活動を展開している。