たいした財産はないと思っていても、意外なものが財産になることがあります。「財産に値するものとは?」「お金の整理はどうすればいい?」「認知症になったら預金はどうなる?」など、相続の際に困らないように疑問をすっきり解決します。決して人ごとではないお金の終活について考えてみましょう。
わが家は多額の財産がないから、お金の終活は無縁だという思い込みはありませんか? 実は銀行口座にあるお金以外にも、財産に該当するものはいくつかあります。例えば、生命保険や共済保険といった加入済みの保険、株式、投資信託、債券などの有価証券。ほかにも家、土地、車、貴金属、骨董品、ゴルフ会員権などが財産に該当します。住宅やクレジットカードのローンと借金などの債務もマイナスの財産になり、手続きをしなければ相続人にそのまま引き継がれるので、子どもに迷惑をかけないように整理を始めておきましょう。

複数の銀行に口座がある場合、家族は相続の際にすべての銀行窓口に出向いて手続きをする必要があり、手間がかかります。その手間を最小限にするには、使っていない口座は解約し、最終的に残す口座を2、3口にまとめることをおすすめします。
口座名義人の判断力が低下して銀行側が認知症と認識した場合、金銭トラブルを防ぐために口座が凍結されて取引が制限されます。口座を1口に絞るとその口座が凍結されたらATMでの入出金などができなくなり、生活に支障が出ます。そのため銀行口座は2、3口までに整理しましょう。その際に、同じ銀行で支店が違う口座を複数持つのではなく、銀行を変えて口座を持っておくことが重要です。
残した口座に関しては、代理人カードを作成しておきましょう。代理人カードとは、口座名義人の家族に預貯金の引き出しを代行してもらうためのカードです。口座名義人が入院や寝たきりになり、振り込みや入出金ができなくなったときに便利です。ただし、本人が認知症になると代理人カードは使えなくなります。作成する際は、口座名義人が銀行窓口で手続きを行います。ほとんどの場合、家族の同行なしで手続きできます。また、定期預金の解約手続きは、本人しか行えないため、タイミングを見て解約手続きを行い、普通預金に移行しておきましょう。

終活は、複数加入している保険を整理する良い機会です。つきあいで加入した保険や保障が重複している保険、特約の内容を見直してみましょう。
整理の手順は、まず契約している保険と保障内容を一覧にして加入状況を把握し、何のための保険なのか「目的」を明確にします。そして今後の生活に必要な保険だけを残し、その他は解約します。例えば、契約者の死亡や病気に備える生命保険は、子どもが独立していて万が一の事態を補えるだけの十分な貯蓄がある場合は、あまり必要ありません。一方、子どもに残せるお金が少ない状況ならば、解約せずに残しておくのもいいでしょう。解約は避けたいが保険料が生活費を圧迫している場合、受取金額を下げれば保険料も下がります。加えて必要のない特約を解除するのも有効です。
また、配偶者が死亡しているのに、受取人を配偶者のままにしているケースも多くあります。保険を見直す際は、受取人を変更するなどのメンテナンスも忘れずに行いましょう。契約者一人の判断で保険を整理するのが難しいときは、子どもと一緒に検討したり、契約している保険会社の担当者に相談すると安心です。
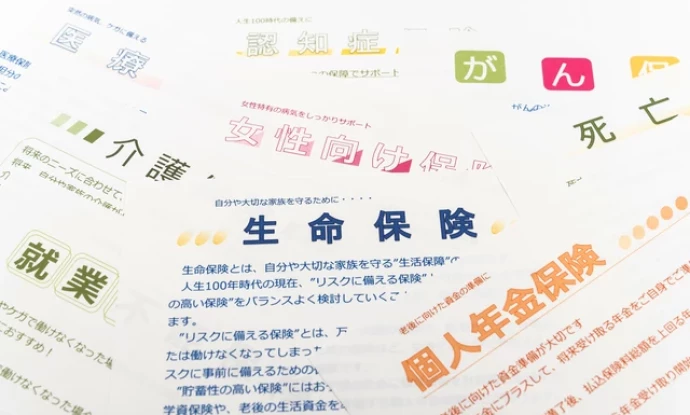
株や国債などの有価証券を持っている場合、親が亡くなったあとに、相続財産として相続人に引き継がれます。その際、相続する人が同じ証券会社に口座がない場合は口座を開設する必要があり、複数の証券会社と取引がある場合、口座開設にも時間と手間がかかります。なお、保有銘柄や評価額を知りたい場合は、残高証明書を取得します。
〈相続手続きに必要な情報〉
・株・投資信託
証券会社名、支店名、口座番号、銘柄、株数・口数
・債券
証券会社名、支店名、口座番号、債券名
※証券会社から送られてくる「取引残高報告書」があれば、これらの情報の代わりになる。
また、遺言書がなければ相続人全員で遺産分割協議をして有価証券の分け方を話し合う必要があり、全員の意見が合わない限り相続が進まず、揉め事になりかねません。有価証券を売却するタイミングは難しいものですが、折を見て現金に換えておくことは相続をスムーズに進めるための有効な方法でもあります。せめて、相続人のことを考えて、使っていない口座は解約しておきましょう。

シニア世代でクレジットカードを複数持っているケースは少ないと思われますが、もしそのような場合は、使っていないカードは解約することをおすすめします。カードを多数所有していると、残された家族は一つずつカード会社に連絡して、解約手続きに追われることになります。よく使うカードを2、3枚だけ残し、エンディングノートには残すカードの会社名、連絡先、引き落とし口座を明記しておきましょう。
ただし、解約するとポイントや付帯する保険も一緒になくなります。カード契約者が死亡後に家族が解約する場合、ポイントは相続の対象外ですが、家族が使いたい場合は保有ポイントを確認してから解約できるようにしておくといいでしょう。また旅行中のけがや病気で亡くなった場合、付帯する傷害保険の補償を受けられることがあるので、付帯する保険の内容をチェックしてから解約しましょう。
近年増えているクレジットカードの不正利用や、認知機能の低下による浪費を防ぐには、限度額を下げることをおすすめします。紙の明細からWEB明細に切り替えるカード会社は増えていますが、WEBで頻繁にチェックできるなら問題ありません。デジタルが苦手なら手数料を払って紙の明細を発行してもらい、心当たりのない引き落としがないか定期的にチェックすると安心です。

お金の終活は、銀行口座にある預金だけでなく、保険、有価証券、クレジットカードなどのチェックも含まれます。「うちはお金持ちじゃないから」と安心しないで、家族が解約手続きに追われないように今のうちに必要なものと不要なものを精査し、残すものの情報(残高は不要)をエンディングノートに記載しておきましょう。
参考:『1000人の「そこが知りたい!」を集めました 人に迷惑をかけない終活』明石久美監修(オレンジページ)

著者:明石久美(あかし・ひさみ)
明石行政書士事務所代表。相続・終活コンサルタント、行政書士、ファイナンシャル・プランナー(1級・CFP)、葬祭アドバイザー、消費生活アドバイザーほか。遺言書作成、おひとりさま準備、相続手続きなどの相続業務を17年行っており、講師歴は19年。葬儀、墓などにも詳しいため、終活も含めたセミナーを全国で行うほか、メディア出演、執筆・取材等を通じた情報発信も行っている。著書に『読んで使えるあなたのエンディングノート』(水王舎)ほか多数ある。