スマートフォンやパソコンが生活に欠かせなくなった今、大事な情報はすべてデジタル機器の中にあるという人は多いはず。そこで必要になるのが「デジタル終活」です。
デジタル終活をしておかないと起こる得る困り事をこの記事で知っていただき、しかるべきタイミングで情報の整理を始めてみましょう。効率的にデジタル終活を進める方法もご紹介します。
「デジタル終活」とは、スマートフォンやパソコンに保存している不要な写真、ファイル、メール、使っていないサービスやアプリを生前に整理しておくことです。SNSアカウント、利用サービスのURL、そしてID、パスワードのヒントをエンディングノートなどにリスト化することも含まれます。
デジタル機器を使用していた本人が亡くなると、家族は葬儀の連絡や遺影写真を探すためにスマートフォンのロックを解除する必要があります。また有料のサブスクリプションサービスや電子マネーなど金銭に関わるサービスの解約手続きも必要になるので、デジタル終活を行っておけば、このような手続きを家族がスムーズに行えます。現在90歳前後のシニアはデジタル機器を利用する機会が少ないと思いますが、公私にわたりスマートフォンやパソコンを使っているであろう50~60代の方は、終活の際にデジタル情報の整理を忘れずにやっておきましょう。

インターネットに接続して利用するサービスを、オンラインサービスといいます。たとえば、SNS、電子メール、ネットショッピング、インターネットバンキング、電子マネーなどが該当します。現代人はオンラインサービスなしでは生活できないといえるほど、日常的に依存度が高くなっています。
自分が亡くなったあと、家族がオンラインサービスの扱いに困らないようにするには、利用しているデジタル情報をリスト化してエンディングノートに記載するか、パソコンのデスクトップなどに利用情報をまとめたファイルを作り、その場所を伝えておくと安心です。加えて、そのデータをどうしてほしいかを明記しておくと家族が迷わず対処できます。
例えば、SNSやブログなど家族に見られたくない内容であれば、生前に削除するのが得策ですが、思い出を振り返るツールでもあるので、残しておくか、削除するかを家族と話し合って決めておくといいでしょう。亡くったあとにアカウントを放置しておくと、悪用や乗っ取りに遭うケースがあるので、死後もアカウントを残したい場合は「追悼アカウント」への移行をおすすめします。
Facebookの場合、亡くなったら生前に指定しておいたFacebook内のアカウント管理人によって追悼アカウントに移行することができます。Instagramは、アカウント保有者が亡くなったことを申請できるフォームがあり、家族が必要情報を入力して死亡を証明する書類を添付すると移行が完了します。Xの場合、追悼アカウント機能はありません。

デジタル終活をしないまま亡くなると、家族はどんな困り事に直面すると思いますか? まずスマートフォンやパソコンのID・パスワードがわからないと、ロック解除ができず、使うことさえできません。Androidのスマートフォンは専門業者に頼めばロック解除できる場合がありますが、iPhoneのスマートフォンは専門業者でも解除が困難なので、解除方法は家族に必ず伝えておきましょう。
次にサブスクリプションサービス、電子マネー決済、WEB明細、クレジットカード決済などを把握していないと無駄な出費や悪用が心配です。例えば、サブスクリプションサービスは解除しない限り、契約は自動更新されて、利用料が引き落とされ続けます。クレジットカードを止めたあと、請求書や督促状が郵送されて初めて利用状況を知るという事態になりかねません。また携帯電話会社が提供している電気サービスを利用している場合、契約書や検針票もすべてオンラインで確認するため、利用している電気会社を把握できず、解約に手間がかかる場合があります。
ネット銀行やネット証券は、キャッシュカードや取引明細書があれば利用状況がわかりますが、通帳レス口座だと実態がつかめないことがあります。これらの財産は相続の対象になるので、金融機関名や支店名をリストに加えておきましょう。

スマートフォンやパソコンの利用歴が長くなると、保存しているデータや利用サービスが増えて、デジタル終活がおっくうになりがちです。先延ばしにすると情報は増えるばかりなので手順を踏んで行い、一度終活をして完了ではなく、時々見直して情報を整理する習慣をつけましょう。
●ステップ1:引継ぎが必要な情報を書き出す
・利用中のサービスとURL
・SNSのアカウント、ID、パスワード
・電子メールアドレス
・写真、動画、ファイル
・インターネットバンキングの取引記録
・ネットショッピングの購入履歴
・インターネット回線とプロバイダーの契約先
・返却が必要なインターネット機器と返却先 など
●ステップ2:残すもの、残さないものを分ける
一気に整理しようとして、家族の思い出となる写真や動画まで削除しないようにしましょう。残すもの、残さないものは家族と相談しながら決めると後悔なく進められます。
●ステップ3:残す情報をリスト化する
家族に引き継ぐ情報はエンディングノートや、エクセルなどで作った一覧表に記載しておきましょう。パスワードは悪用を防ぐため、桁数がわかるように虫食いの状態で記載し、正式なパスワードの保管場所を別に設けて信頼できる相手にのみ知らせましょう。
パスワードの記載例:a※※1※※
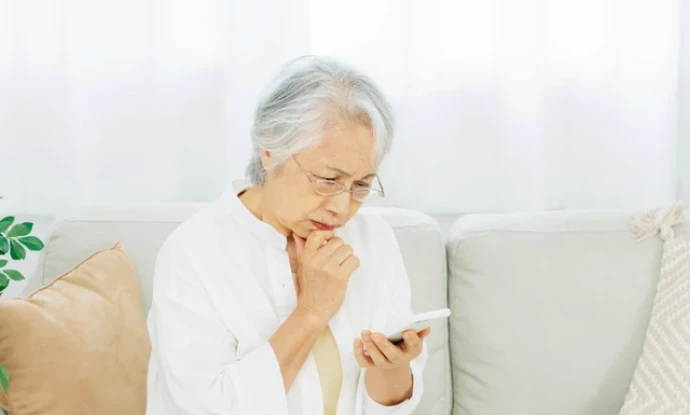
デジタル終活をおろそかにすると、故人のスマートフォンやパソコンを開くことさえできなくなります。さらに自動更新されるサブスクリプションサービスなどは、クレジットカードを止めるまで利用料が引き落とされてしまいます。不要な出費やサービスの悪用を防ぐためにも、生前にデジタル終活を行うことをおすすめします。
しかし、スマホとパソコンは連携しているものがあるため(PCのWEBでログインすると携帯に送られた番号を入力するなど)、すぐにスマホや、インターネット回線・プロバイダーの解約はしないほうがよいことも頭に入れておくとよいでしょう。

著者:明石久美(あかし・ひさみ)
明石行政書士事務所代表。相続・終活コンサルタント、行政書士、ファイナンシャル・プランナー(1級・CFP)、葬祭アドバイザー、消費生活アドバイザーほか。遺言書作成、おひとりさま準備、相続手続きなどの相続業務を17年行っており、講師歴は19年。葬儀、墓などにも詳しいため、終活も含めたセミナーを全国で行うほか、メディア出演、執筆・取材等を通じた情報発信も行っている。著書に『読んで使えるあなたのエンディングノート』(水王舎)ほか多数ある。