子育てが一段落したくらいの年齢になると、今度は高齢の親に心配ごとが出てきます。持病の悪化や目や耳、足腰の衰えなどに加え、物忘れや勘違いなど認知面での違和感。そんな問題にどう対処してゆくかが人生の新しい課題になってきます。今回スタートするストーリーの主人公、50代の女性、山内聖子もそんな課題に向き合っているケアラーの一人。父の死後、一人暮らしを続けてきた実母の変化に気づき、さまざまな経緯を経て1年ほど前に母の住む東京都品川区の一軒家に夫や娘と越し、同居を始めました。聖子のケアラーとしての視点から、日々の出来事や思ったことなどを綴っていきます。
8月下旬、あまりの暑さで5時前に目が覚めてしまった。しばらくぼーっとしていたのだけれど、なにやら台所あたりから物音が。台所に入ってみると、母がキョロキョロと探し物をしていた。部屋は締め切られていて、ムッとするような暑さ。大急ぎでエアコンのスイッチを入れた。
「聖子、あの、ホーローのお鍋、どうしたかしら?」と、母はしきりにシンク周りの引き出しを覗いている。上の戸棚を見やって、そちらにも手を掛けようとしているので、「ちょっと待ってね」となだめる。以前なら、「やめて! お母さんはいいの!」と強めに遮ってしまうところだけれど、ここ1年あまりの同居とその間に得た知識などから、お母さんへの対応はなるべくやさしく、おだやかにするように心がけている。なかなか難しく、今でも完全に慣れたわけではないけれど、以前のように母を、子どもをたしなめるように叱るようなことは母の気分を害し、認知の状態を悪化させるかもしれないのだそう。
「あの赤い両手鍋。煮物はあれでやるって決めてるから……」と、まだ諦めていない母をダイニングの椅子に座らせ、冷たい麦茶を入れたグラスを渡す。
「あとで一緒に探そう。これから朝の支度があるから、お母さんも手伝ってくれる?」と声を掛けてみたが、それも何となく気分を害したようで、「朝刊来てるかしら……」と台所から出て行ってしまった。
「手伝う」という言い方が悪かったのかな? この家の台所を守ってきた母にとって、台所の主はあくまでも自分なのだ、という意識なのかもしれない。
私たち母の娘家族がこの家に越してきたのは、母が起こしたボヤ騒ぎがきっかけだった。父の死後、この家で一人暮らしをしてきた母が、なんとか人の手を借りずに家事をこなしていたが、ある日の昼間、煮物をしていた鍋を焦がしてしまい、煙が充満、火災報知器が鳴り響く事態となってしまった。たまたま昼間で、荷物の配達のために玄関口に来ていた配送業者の方が異変を母に伝えてくれたおかげで大事には至らなかった。さらにその日、月に何度か様子を見に来ていた私が来る日だったことも、奇跡的なタイミングだった。その日に焦がして台無しにしてしまった鍋が、母が探していた「赤いホーローの鍋」だ。仕方なく処分して、それ以降違う鍋を使ってきたのだけれど、母はまだあの鍋があると思っている。

ボヤ騒ぎから一人暮らしの母の家事すべてに危険さを感じるようになってしまい、まず、ガスコンロを交換した。火をつけているのに不注意からそのことを忘れてしまう事態にも対応し、自動で火が消えてくれるタイプのものがあると、ネットで調べて知ったから。「なんで交換するの?」と不思議そうな母を尻目に、少し強引に交換してしまった。それでも不安が消えるわけでもなく、逆に他のことに不安を感じるようになり、いくつかのプロセスを経て今日の同居に至っている。
もともと教師として働いており、子育てとの両立の難しさから退職して専業主婦となった母。専業主婦となったからには、専業主婦として完璧を目指そうとしていたのか、何事にもこだわりが強い。毎日料理をする主婦なら大概の人がそうなるのかもしれないとは思うけれど、特に台所やそこで使う道具などには、そのこだわりが表れていたように思う。
まず、台所のシンクや排水溝、その周りの引き出し、棚にいたるまでを年中きれいに掃除していたし、料理の種類によって鍋や道具を細かく区分けし、その管理も神経質に行っていた。ただ、60代後半から70代に入った頃から体力的な問題からが難しくなったのか、段々と片付けや掃除もおざなりになり、台所周りの汚れも目立つようになっていた。そんな様子に気付き、私は月に何度か実家を訪れ、掃除や整理を手伝うようになったのだが、その時にも母にはかなり気を遣った。私が母のスペースを荒らす、というような意識が母にあった様なのだ。その時は私も母の状態を理解しておらず、感情的に対処してしまっていたように思う。それまで家事はしっかりやり、私や他のきょうだいに対しても若干威圧的だった母の「衰え」を否応なく感じ、それに対してショックなような、その反面自分を優位に思うような感情がわいてきて、なんとも複雑な心境になった。
その状態から現在に至るまで、介護の窓口への相談や嫌がる母を長い期間かけて説得して要介護認定の申請をし、ケアマネジャーさんやお世話になることになったデイサービスの方などの外部の方と関わるようになったことで、さまざまな気づきがあった。母と対しているのが主に自分だけだった時にはわからなかったことがクリアになっていき、自分の素直な感情を整理し、その上で「なるべく」適切な対応をしようと思えるようになったのだ。
同居についても、本来、ヘルパーさんなどの介護サービスなどを駆使すればしなくてもよい段階なのだと思う。ただ、今の母が受け入れられること、受け入れられないことの境界線がわかってきたことで、私と私の家族に、たまたま母との同居が可能な条件が揃っていたということだ。親御さんが遠くにいる人ならば、なかなかこんな選択はできないだろうし、人とその状況によって選択はさまざまで、どれが正解でどれが間違っているというわけでもないのだと思う。
同居してから、台所は主に私が使うことになっているが、母には常に気を遣っている。主は母で、私は母ができない部分を手伝っていると思うことにすると、私自身、割り切って考えられるみたい。心理的な負担感がないのだ。ただ、今はそう思ってしまおうとしているだけで、私の本心はどうなのかわからない。
ただ、母には今の生活をなるべく楽しんでもらいたい。母がこだわって手入れをしてきた台所を少しでも使いやすくしたり、ちょっとでも華やかになる道具や食器などを少しずつ追加することで、母の気持ちが明るくなってくれたらと思う。実際、そういう部分での工夫を私も、今はまだ楽しめていると思う。
9月は母の誕生日と敬老の日が重なる月。どんなプレゼントにするかが目下の悩みの種だ。
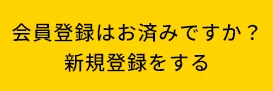

著者:MySCUE編集部
MySCUE (マイスキュー)は、家族や親しい方のシニアケアや介護をするケアラーに役立つ情報を提供しています。シニアケアをスマートに。誰もが笑顔で歳を重ね長生きを喜べる国となることを願っています。