テレビやネット、書籍など、さまざまなメディアで栄養に関する情報が発信されています。その中には、分子栄養学理論に基づいたものも少なくありません。分子栄養学とは、栄養によって全身の細胞一つひとつを元気にし、心身のパフォーマンスを最大限に引き出すことを目的とした理論です。本記事では、シニア世代に必要な分子栄養学に基づいた食事のコツをご紹介します。

1960年代にアメリカで「オーソモレキュラー」という概念が誕生し、アメリカのノーベル化学賞受賞化学者ライナス・ポーリング博士や、カナダの精神科医エイブラム・ホッファー博士らによって築き上げられたのが分子栄養学です。
その後、進化を続け、日本でも2000年代から分子栄養学の理論を取り入れた専門クリニックが登場しました。医師をはじめ、看護師、栄養士、鍼灸師などさまざまなジャンルのプロフェッショナル、さらには意識の高い人々の間で広まりました。
現在では、内科、心療内科、産婦人科、小児科、歯科、美容皮膚科など、多岐にわたる医療機関でこの理論に基づいた治療が行われています。疲れやだるさ、不眠、肌荒れといった不調のケアにも用いられています。
基本的な考え方はシンプルです。栄養によって全身の細胞を元気にする、というものです。私たちの体にある約37兆個の細胞は、摂取した食べ物に含まれる栄養からできています。しかし、不規則な食事、栄養バランスの乱れ、消化機能の低下、腸内環境の乱れ、ストレスなどさまざまな理由から、細胞に必要な栄養素をスムーズに供給することが難しくなり、不調や病気の原因になると考えます。この栄養バランスの乱れを細胞レベルでチェックし、必要な栄養素で整えていくのが基本的な考え方です。
細胞自体や細胞が活動するために欠かせない材料を適切に摂取することで、全身の機能が向上します。病態の改善、QOL(生活の質)の向上、さらにはアスリートのパフォーマンスの向上やアンチエイジングなど、メリットは多方面にわたります。
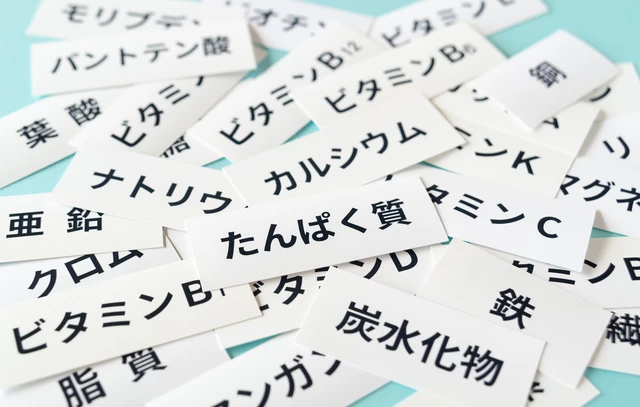
一般的な栄養学との違いの一つに、目的があります。一般的な栄養学では、病気のリスクを回避するということに重点が置かれるのに対し、分子栄養学では、一つひとつの細胞が必要とする栄養素の最適な量とバランスを調整し、細胞ひいては心身が最高のパフォーマンスを発揮できる状態を目指します。
また、分子栄養学は個人差も重視します。私たち一人ひとりの食の好み、食事の時間や量、日々の活動、抱える悩みなどは異なります。そのため、摂取される栄養素や利用される栄養素も状況により変化します。よって細胞のパフォーマンスを最適化するのに必要な栄養素やその量は、個人ごとに異なる、という考え方に基づいています。

シニア世代において、まず問題視されるのが「低栄養」です。低栄養とは、食事量が減り、エネルギーやタンパク質など必要な栄養素が十分に摂取できていない状態を指します。
厚生労働省が発表した「令和5年 国民健康・栄養調査結果の概要」によると、65歳以上の低栄養傾向の者(BMI≦20kg/m2)は男性12.2%、女性22.4%、85歳以上ではその割合が最も高く、男性22.8%、女性24.8%と、低栄養が進んでいることがわかります。
タンパク質は、筋肉や骨、臓器、ホルモンなど、体のあらゆるものの材料となるため、不足すると多岐にわたり影響を及ぼします。体重が減少して足腰が弱くなるほか、感染症にかかりやすくなったり、傷の治りが遅くなったりするなど、さまざまな健康上の問題を引き起こす原因となります。
また、全体のカロリー摂取量が減少すると、体は生命維持に必要なエネルギーを確保するために、筋肉を分解してエネルギーに変換します。このため、筋肉量が減少するリスクも高まるのです。
また、加齢に伴って食欲や食事量が低下する傾向があり、1日の食事回数が減ることもよくみられます。特に一人暮らしの方は、自ら食事を調達するため、体調により食事の質や量が大きく左右されがちです。年齢とともに味覚が鈍くなったり、嚥下機能が低下したり、筋肉量が減るなどの変化が起こりやすく、低栄養状態が加わると、これらの問題はさらに進行します。
その結果、外出がおっくうになって活動量が低下する、食欲もさらに落ち込む、といった悪循環に陥りやすくなります。

現場で実感するのは、シニア世代の食事の傾向が二極化しているということです。
食事に気を遣い、健康管理をしっかり行っている方は、年齢を重ねてもいつも笑顔で、一本筋の通った生き方をする方が多い一方、そうでない方は、痛みなどの不調を訴えやすく、できることが減り、足腰が弱くなり、QOLが低下していく……。そんな傾向が見受けられます。
みなさんも、ご家族の食が細くなったりすると心配になることもあるかと思います。「これを食べて」と言う前に、この先をどう過ごしたいのか、どう生きたいのか、ご家族に聞いてみましょう。
「いつまでも自由に旅がしたい」「孫の結婚式が見たい」など、さまざまな声が出てくるはずです。これを起点に、「では、足腰を強くするためにタンパク質が必要だね」といった具合に一人ひとりに合った食事スタイルが生まれていきます。
中には「年なんだから好きなものを食べたい」という声もあるでしょう。しかし、そんな方もよくよく話を聞くと、心の奥底では健康への不安を抱えていることを頻繁に経験しています。その部分もくみ取り、できることから食事を改善していくことが大切です。

今すぐ取り組める、食事改善の3つのコツを紹介します。
①タンパク質をしっかりとる
タンパク質は、肉、魚、卵、大豆製品に多く含まれます。これらを毎食とることを意識しましょう。シニア世代では、パンや麺類など炭水化物中心の食事でおなかを満たしてしまいがちですが、定食スタイルの食事がおすすめです。
調理が面倒なときは、コンビニでもOK。コンビニでは焼き魚やハンバーグなどの主菜が手に入ります。あとはおにぎりやカップみそ汁をプラスすれば、タンパク質を取り入れた食事が実現します。
また、食べるときは、順番も大切です。シニア世代は食が細く、すぐにおなかいっぱいになってしまうことも多いため、まずはタンパク質から箸をつけるようにしましょう。
「肉は苦手」という方は、豆腐など大豆製品を積極的に取り入れるとよいでしょう。ただし、植物性タンパク質は動物性タンパク質に比べ、体内での利用効率が低い傾向にあるため、動物性タンパク質と組み合わせるのがポイントです。例えば、豆腐にはたっぷりのかつお節、納豆には生卵を加えると効果的です。
②カロリーの確保
現場でシニアの方にお話を伺うと、「1日2食です」という方が多くいらっしゃいます。食事の回数が減ると、カロリー摂取のチャンスも減り、栄養不足に陥りやすくなります。そのため、できる限り3食とることを心がけましょう。
どうしても朝食がとれない方には、「飲む朝食」がおすすめです。最初は豆乳などの液体をとり、徐々にごはんなど固形物を取り入れて、3食に慣れていくとよいでしょう。
③糖質の量を見直す
糖質(詳しくは「我慢したくない! でも病気はイヤ! シニアの甘いものとの付き合い方」をご覧ください)はとり過ぎると、糖尿病のリスクを高めるだけでなく、血管や骨にも悪影響を及ぼすことが知られています。
高齢者で多いのが、食事はほとんどとらないのに、おやつを大量に食べているというパターンです。おやつに含まれる糖質はエネルギー源にはなるものの、体の構成材料にはならないため注意が必要です。
3食でしっかりとタンパク質をとり、カロリーを確保することで、甘いものを欲する頻度は下がりやすくなります。
できることから一つずつ、トライしてみましょう。

著者:吉川圭美(よしかわ・たまみ)
特定非営利活動法人 オーソモレキュラー分子栄養医学協会 栄養カウンセラー(ONP)、管理栄養士、ライター。
取材で出会ったオーソモレキュラー栄養医学(分子栄養学)に魅了され資格取得。内科、心療内科、婦人科、不妊外来のクリニックにおいて延べ5,000件のカウンセリングを担当。シニア世代への訪問指導も行う。多くの人々に栄養の力を伝えるため「plus NUEtrition」を立ち上げ、定期的にセミナーを開催。このほかセミナー講師、栄養学に関する記事執筆、レシピ提案なども。『てんきち母ちゃんのゆる糖質オフのやせる献立』(扶桑社)では栄養監修を担当。