身近な人の体力や生活能力の衰えに直面し、いずれは最期のときに向き合うのが介護の現実です。さまざまな喪失を経験する介護には、「グリーフケア」が必要だと考えられます。介護者が一人で悲しみを背負わないために、グリーフケアを通して知ってほしいことをご紹介します。
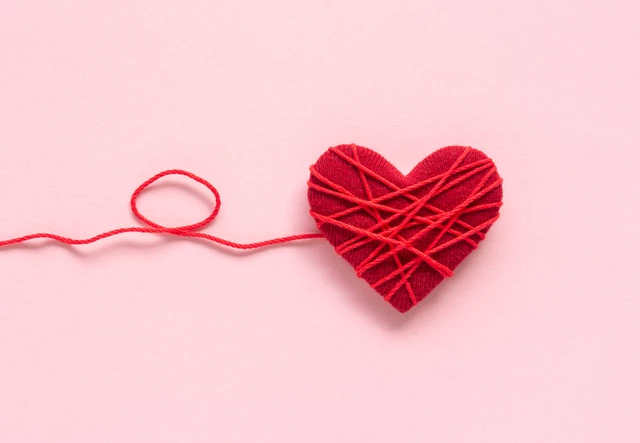
「グリーフケア」という言葉を初めて知る人もいると思います。グリーフ(grief)は英語で「悲しみ」を意味し、大切な人やものを失った際に体験する身体的、心理的、社会的な痛みを指します。そして、その悲しみに寄り添い、癒やすことをグリーフケアと呼びます。
喪失体験の種類はさまざまで、大切な人との別れをはじめ、介護の末にパートナーを失えば妻や夫という役割を喪失します。認知症になれば記憶の一部が失われますし、介護中に心ない言葉に傷つき、自尊心を失うことも喪失体験に値します。
喪失体験に伴う痛みの反応も多岐にわたり、涙が止まらない人もいれば、まったく涙が出ない人もいますが、どちらがいい悪いということではありません。涙が出たら、泣いてしまいごめんなさいと謝るのではなく、「やっとゆるめられた」と自分をいたわってあげたいものです。また、涙が出ないのは「しっかりしなければ」と自分を鼓舞していることの表れかもしれず、そのときその人に必要な反応が起こっていると考えられます。
また、悲しむという反応にはネガティブなイメージがつきまといますが、グリーフケアでは悲しむことを「失われた対象を抱き直す営み」と捉えます。そのように亡くなった方の存在の大切さを再確認し、思い出すことで、その方は心の中で生き続け、絆は継続します。その絆が残された人の支えになる場合があるため、悲しむことは決して悪いことではありません。
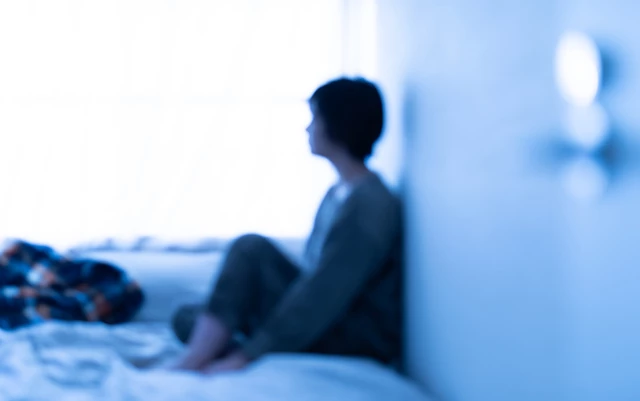
次に、看取りのような大きな喪失を経験した際にたどる、悲嘆のプロセスをご紹介します。あくまでも一般論であり、前に進むペースはそれぞれで、自分なりの道のりを大切にしましょう。再び歩き始める力は誰の中にも宿っていますので、作動するタイミングを焦らず待ってください。寄せては返す波のように、静まった悲しみが再び押し寄せることも自然な反応です。
●悲嘆のプロセス
第一期:
喪失直後は体の一部がもがれたような、強い喪失感に駆られます。感情と思考が働かず、八つ当たりやヒステリックな反応を抑えられない場合もあります。
〈アドバイス〉
これらの反応は、強い悲しみがもたらすものです。本来の自分とは違う状態なので、自分を責めず、「一大事なのだから仕方ない」と悲しみに身をまかせましょう。
第二期:
大切な存在の喪失を現実として受け入れると同時に、「もう二度と会えない」という実感がわいてきます。これまでの日々を振り返り、自責の念、後悔、孤独感がわくのもこの時期です。また記念日反応といって、亡くなった方と関係がある物事に触れると、訳もなく涙があふれることがあります。例えば、入院していた病院の前を通ったとき、クローゼットに残る故人の香りをかいだときなど、引き金はさまざまです。
〈アドバイス〉
一人で悲しみに耐える必要はなく、共感してくれる相手に胸の内を話すと心が軽くなり、グリーフケアにつながります。葬儀や法要を行い、節目をつくることも気持ちの区切りになります。
第三期:
激しい感情に振り回される時間は減りますが、時折悲しみがぶり返し、戸惑うことがあります。また喪失感が薄れると、故人を忘れていく罪悪感にさいなまれて、自分を責めてしまう人もいます。
〈アドバイス〉
もう大丈夫と思ってもふとした瞬間に寂しさがこみ上げるのは、弱いからではなく、人として自然な反応です。グリーフケアが目指す回復とは、悲しみをなかったことにするのではなく、悲しみと共存しながら新たな生活や役割を構築していくことです。薄れる悲しみに自責の念を感じたら、日常を取り戻して、喜びや楽しさを感じることを自分に許し、意欲の芽を大切にしましょう。

グリーフを癒やすには、悲しみの荷下ろしが必要で、そのために有効な手段の一つが「傾聴」です。傾聴とは真摯に相手の話に耳を傾けることで、それができる相手に思いを聴いてもらうと次のような変化が期待できます。
●「悲しんでいいんだ」という肯定感が生まれ、悲しみとしっかり向き合える。
●共感者がいることで「一人じゃない」と思え、孤独感が軽減する。
●気持ちを言葉に出すと心の中が整理され、新しい視点や考える力が生まれる。
●新たな日常に適応する自分の内なる力に気づき、前に進める。
傾聴の基本は「言いっぱなし、聴きっぱなし」といわれています。語る側はありのままの気持ちを吐き出し、聴く側は否定や批判をせず、ただ受け止める。そうした経験は自己回復力の向上を助けます。

介護中や看取り後に、周りからの言葉に傷ついた経験はありませんか? 悲しみと向き合うことをグリーフワークといいますが、周りからの一言によって傷つき、グリーフワークが滞って心の回復が遅れるケースがあります。次のような言葉をかけられたときは、自分を守るための受け止め方と受け流し方を意識してみましょう。
【グリーフワークを妨げる言葉】
●「きっと時間が解決する」
悲しみの深みにいるときは先が見えないもの。失った相手が大切な人であるほど、時間が解決すると思えないのは当然です。
●「いつまでも泣いていないで早く前を向いて」
泣くことは悲しみを受け止め、前に進むために必要なグリーフワークです。先を急がず、自分のペースで悲しみを受容するタイミングを待ちましょう。
●「大往生でよかった」
故人が高齢であっても別れはつらいものです。この言葉に違和感を覚えるのは、「もっと一緒にいたかった」という故人への深い愛情の証しといえます。
●「あなたがしっかりしないと」
長男、長女という理由で涙を流せない人もいます。大切な人との別れは、立場や役割を脱ぎ捨て、心のままに振る舞っていい貴重な時間と心得て。
●「あの人はもっと大変」
悲しみの大小をジャッジする権利は、誰も持ち合わせていません。悲しみ比べに意味はないとスルーし、自分らしく悲しんで。
●「元気そうでよかった」
表情は笑顔でも心が元気とは限りませんが、内と外のギャップは理解されにくいものです。人前で笑顔を見せられる自分を褒め、同時に等身大でいられる時間をつくるのも大切。
●「私も経験者だから気持ちがわかります」
「気持ちがわかる」と言われると、「簡単にわかるはずがない」と反論したくなります。介護の経験者であっても、他者の気持ちを100%理解するのは不可能です。反発が生まれるのは自然な反応と受け止めて。

著者:北林あい
医療・健康・介護分野のフリーライター、臨床傾聴士(上智大学グリーフケア研究所認定)。30代で乳がんになり、治療は順調に進み寛解を迎えたものの、穏やかな日常が突然奪われる怖さ、将来への漠然とした不安が消えない日々を過ごす。その経験から喪失悲嘆や心のケアの領域に興味を持ち、大学の研究・教育機関でグリーフケアを学び、臨床傾聴士の資格を取得。現在、乳がん患者や自殺念慮を抱える人を対象に、傾聴を通じたグリーフケアを行っている。