家族の介護では、サポートしてくれる医療・介護専門職との連携が不可欠です。しかし、いくら丁寧に説明しても状況がうまく伝わらず、もどかしさや不信感を抱いてしまうことも少なくありません。

関東在住のBさんは、脳梗塞で寝たきりになった80代の母親(要介護5)を在宅介護しています。夫は仕事で忙しいものの、Bさんを気にかけ、週末には積極的にケアをしてくれています。その一方で、Bさんは訪問介護や訪問看護のスタッフとのやりとりにはうまく噛み合わない部分があり、不満を募らせています。
Bさんは、母親の状態や介護内容を毎日ノートに記録しています。顔色や痰の量といった体調の変化だけでなく、衣服のシワの伸ばし方や体位交換の工夫など、母親ができるだけ過ごしやすくなるように工夫し、丁寧に書き留めています。方法はその日の様子に合わせて微調整し「今日は痰が多いので横向きの姿勢を長くとってください」といった依頼をノートに記してきました。
悩んでいるのは、その内容がスタッフに十分に伝わっていないことです。「訪問時にはノートを見てください」とお願いしているものの、なかなかケアに反映されません。記録の書き方が不十分なのではないかと考えたBさんは、より詳細に記すようにしましたが、対応は変わりませんでした。
Bさんは次第に「プロ意識に欠けている! こんな人たちに母を任せられない!」と、スタッフに対する信頼感が揺らぐようになりました。
「しっかり伝えたい」「わかってほしい」という思いから、詳細な状況を書きたくなるのは自然なことです。しかし、伝える情報量=伝わる量ではありません。
Bさんに見せていただいた介護記録ノートは、少ない日でも1ページ、多い日は2ページ以上にわたって、日記のように長文でびっしりと書き込まれていました。日々、母親の変化を細やかに観察し、気にかけてこられたのでしょう。しかし、文章が長くなると読む側の負担が大きくなり、要点をつかむのに時間がかかってしまいます。
Bさんには、特に伝えたい点について、文章ではなく箇条書きで整理する方法を提案しました。相手と情報を共有したいときは、文章よりも箇条書きにすることで、要点がつかみやすくなり、理解もスムーズになるからです。Bさんは「なぜ、私がそこまでやらなきゃいけないんですか? プロなら理解に努めるのが当然でしょう?」と、抵抗を感じておられたようでしたが、試しに箇条書きにし、具体的なケア方法の部分に蛍光ペンでアンダーラインを引いてみました。すると、スタッフから「今日はお腹がゆるいんですね」「横向きの角度はこれでいいですか?」との確認があったそうです。Bさんは「箇条書きにするだけで、相手の反応や行動がこんなにも変わるんですね」と、驚いておられました。
続いて、Bさんはノートではなくメモを手渡すことにしました。メモは、事業所内での情報共有に活用されるようになり、Bさんは訪問スタッフが変わるたびに同じ説明を繰り返す必要がなくなりました。
Bさんは、のちに「その日のケアで特に気にかけてほしいことは1つか2つほどだったにもかかわらず、母の状況を一つ残らず伝えなければ、というプレッシャーがあって、どんどん長文になっていたことに気づきました」と話してくれました。

介護記録だけでなく、介護で相談したいことや困っていることがあるときは、口頭よりもメモ書きを用いると便利です。とはいえ、いきなり箇条書きにして書き出すのは難しいものです。文章を書くことには慣れていたBさんも、箇条書きで簡潔にまとめるのに最初は時間がかかったそうです。
箇条書きにするまでのステップは以下のとおりです。
1 今、気になっていることを思いつくままに書き出す
2 1で書き出したものを眺め、特に伝えたい内容に丸をつける
3 2の内容を具体的な行動に書き換える
4 箇条書きに書き直す
私自身も、最初は箇条書きにまとめることが難しく、戸惑いました。しかし、何度も繰り返しながら、だんだんコツをつかむことができました。要介護・要支援の認定調査や担当者会議など、普段の様子が伝わりにくい場面で箇条書きのメモを共有することで、ずいぶん助けられました。現在は、家族の介護に限らず、仕事や友人とのコミュニケーションを取るときにも、この箇条書きメモを活用しています。
介護トラブルの最中は、記録を取ったりメモを作ったりする余裕がなかなか持てません。少し余裕のあるときから、最近の変化や気になる点を書き出し、箇条書きに慣れておくと、いざという時に役立つことがあります。
もし、相談内容や要望がうまく伝わらない、わかってもらえないと感じた時は、ぜひ一度試してみてください。思いが届くことで、心の重荷が少し軽くなるかもしれません。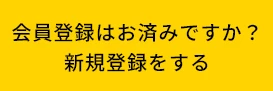

著者:橋中 今日子
介護者メンタルケア協会代表・理学療法士・公認心理師。認知症の祖母、重度身体障がいの母、知的障害の弟の3人を、働きながら21年間介護。2000件以上の介護相談に対応するほか、医療介護従事者のメンタルケアにも取り組む。