能楽師として40年以上舞台に立ちながら、実用書から豊富な古典知識を活かした教養書やエッセイまで、多ジャンルで活躍する著述家として知られる安田登さんのエッセイをシリーズでお届けします。初回のテーマは、安田さんがレビー小体型認知症を患ったお母さまの認知症と向き合う中で見出した「幽霊と共に生きる」という世界。それは、図らずも安田さんが能の舞台で務めてきた“彼岸と此岸”をつなぐ「ワキ」の役割と重なるものでした。古典芸能、脳の使い方、脳内AR──ジャンルを超えて思索する能楽師が語る、認知症のある暮らしの深く豊かな風景とは。
はじめまして。
最初に簡単に自己紹介をいたします。
能楽師をしています。古典芸能である「能」の役者です。年齢は69歳。世間的に見れば若くはありません。人によっては、もう十分に年だという人も多いでしょう。
しかし、能の世界にいると、自分が年を取っている感じがまったくしません。
皆さんも何となくご存知だと思うのですが、能楽師は年を取っても元気で、69歳で現役なんてたくさんいる。90歳以上で現役という方もいらっしゃいます。
先日も、楽屋にいるメンバーで私が一番年下だなんてことがありました。
撮影:石田裕
しかし、能楽師がみな高齢というわけではありません。早い人は3歳くらいから稽古を始めます。多くの人が就学前に初舞台を迎えます。ですから、楽屋には子どももいれば青年もいる、壮年もいれば高齢者もいるのです。
能楽師が長生きだということはありませんが、多くの人が長く現役を続けています。それは身体と脳の使い方に理由があるのではないかと思っています。能楽師の身体の使い方に関しては、何冊か本を書きました。いまは能楽師の脳の使い方に興味があり、いろいろと考えています。
そういうことも書いていこうと思っています。
また、私はいろいろな分野の本を書いています。共著を入れれば今までに50冊以上の本を書きました。
最初に書いた本は漢和辞典(熟語担当)です。20代の時です。
能や古典の本も書きましたが、さきほども書いたように、能から学ぶ身体の使い方の本も書きました。また、3DCGの本も書きましたし、ゲームの攻略本も書きました。その流れでCGの会社の設立にも関与しました。その会社は今でもあります。
その他、風水の本も書きましたし、エイズの本も書きました。
要は何でも興味のあることに手を出して、それを本にできるくらいは学びます。
また、NHKのEテレの『100分de名著』という番組で3つの古典の講師と朗読をつとめました。『平家物語』、『太平記』、そして『ウェイリー版源氏物語』です。
簡単にと書きましたが、だいぶたくさん自己紹介をしてしまいました。まだまだいろいろあるのですが、そろそろやめて本題に入りたいと思います。
今回は、母の認知症の話をします。
86歳で亡くなった母は、最後の2年間は認知症になっていました。
出身は千葉県の銚子市で4人兄弟。私を含めて男3人は東京や埼玉にいて、千葉にいるのは妹だけ。父が亡くなってから、母は妹夫婦と二世帯住宅に住んでいました。
「お母さんが認知症らしい」
ある日、妹から電話がかかってきました。
私の家からは片道三時間ほどかかるということもあり、忙しさを言い訳に妹夫婦に任せっぱなしになっていたのですが、それからはなるべく顔を出すようにしました。
脳の活性化につながるかと、母のもとに行くと能の謡を教えました。
実は母は私の出演する能をたった一回しか観たことはありません。
それからも何度か誘いましたが「あんな辛気臭いもの、観ていられない。どうせなら歌舞伎がいい。玉三郎がいい。銀座のホテルで夕食はステーキ。ついでに伯母さん(母の姉)も一緒に招待しなさい」といつも言われました。
しかし、もともと声を出すことも、からだを動かすことも好きな母。謡の稽古は楽しかったようです。
八十歳で認知症になっても謡の詞章を覚えようとする母は、「このごろなかなか覚えられなくて」と言います。「覚えようとしなくてもいいから」と言っても、覚えようとしました。
母の認知症はレビー小体型認知症というもので、よく「幽霊がいる」と言っていました。
身内がこの認知症になると大変だという人も多いようですが、母の場合はいい方に作用しました。物盗られ妄想がすべて幽霊のせいになるのです。ですから同居する妹も、面倒をみてくれるヘルパーの方も、その被害を免れることができました。
「幽霊がいる」という人に対しては否定しないことが大切だといいます。能楽師はそれが得意です。なぜなら能という芸能は、幽霊と出会う芸能だからです。
能の主人公を「シテ」といいます。能のシテは幽霊や神様、動植物の精霊などの、普通の人には見えない存在であることが多い。対するのは「ワキ」。私はワキをする役者です。
ワキといっても脇役という意味ではありません。
ワキという言葉は「分き(分く)」からできた言葉です。「脇の下」といいますが、着物の横の線を「脇」といいます。あの線を境にして、着物は前の部分(前身頃)と後ろの部分(後身頃)に分かれます。着物の「脇」とは、前身頃と後身頃の中間の部分をいいます。
能のワキも同じです。あちらとこちらの中間=境界にいる存在、それが「ワキ」です。
能でいえば、幽霊の住む「彼岸」と、我々人間の彼ら住む「此岸」、その境界にいて、幽霊と人間との橋渡しをする、それがワキです。
ふだんからそんな世界にいるので、母が「幽霊がいる」といっても驚かない。母は認知症になることにより、能のワキのような存在になったのです。
アマゾンの奥地に住むピダハンと呼ばれる人は、みな精霊が見えるといいます(『ピダハン(みすず書房)』)。
彼らのもとにキリスト教の布教に行った宣教師(ダニエル・L・エヴェレット)は、ある日、100メートルと離れていない川辺に「イガガイーという精霊がいる」とピダハンたちに言われます。しかし、彼には何も見えません。宣教師はピダハンたちに「何もいない」と言いますが、彼らは「あそこにいる」と言うのです。
宣教師は書きます。
「あそこに何もいないのはわたしにとって間違いないのと同じくらい確かに、ピダハンたちは何かがいることを確信していた」
そして「わたしには、川岸には誰もいないとピダハンを説得することはできなかった。一方彼らも、精霊はもちろん何かがいたとわたしに信じさせることはできなかった」
ピダハンの人たちが精霊を見えるということを、西洋人である宣教師が理解することは難しいし、同じように宣教師が精霊が見えないということを彼らがわかることも難しいのです。
母と私たちも同じです。
ワキである母には幽霊が見えるが、私たちには見えない、それだけなのです。妹夫婦もそれを理解してくれたおかげで大きな問題にはなりませんでした。
問題があるとすれば、夜中でも「いま、女の子の幽霊が現れたのよ」などと電話をかけてくることくらいでした。
幽霊は母の稽古中にも現れるようになりました。
母が「いまそこにいる」というので「えっ」と隣を見ると「お前が見るからいなくなった」と言われました。
こういうことが何回か続いたあとで、ふたりで合図を決めました。たとえば中年の女性の幽霊がいるときは母は人差し指で机を叩く。女児の幽霊のときは小指などと。
その合図を決めてからは、母と会話をしながらも隣にいる幽霊にも聞かせるように話をします。
幽霊が成仏する能の謡を稽古しているときは、隣にいる幽霊にも向かいながら「あなたも早く成仏できればいいのにね」などと言っている。小さい子の幽霊には慰めの言葉をかけている。
これはなかなか楽しい。
それでも「幽霊がいるなんて変だ」という人もいるでしょう。
「本当にいるなら見せてみろ」という人もいます。襖絵の虎を「外に出してくれたなら退治しましょう」という一休さんと同じです。
自分が見ているものを他の人に見せられるかどうかが、本当に見えているか、あるいは本当に存在しているかの証明になります。
が、考えてみればこれは変です。自分が見ていたものを人に見せられないこともあります。
たとえば夢です。
「夢を見たことがない」という友人が二人います。
最初にそれを聞いたときには「覚えていないだけだろう」と思いました。しかし、精神科医の友人に聞いたり、いろいろ調べたりすると、彼らは本当に夢を見ていない人なんだと思うようになりました。
全身麻酔をしたときにはその間の記憶がない。夢も見ない。
彼らは、おそらくはそのような睡眠をしているのでしょう。
そして、彼らに私が夢を見ているということを証明することはできない。私が「昨日、こんな夢を見た」といって、「それを見せてみろ」と言われても見せることはできない。ピダハンと同じです。
遠い未来、彼らのような人が主流になったら「むかしは夢というものを見ていたらしいよ」、「うそだ」なんて会話がされるかもしれない。
母が見ているものを私が見えていないからといって、それを否定することはできません。それどころか見えていない私たちが問題なのかもしれない、なんて思ったりします。
昔から日本人は「見えないもの」を見ることが得意でした。
能もそうですし、古典の中にはそのような話がたくさん出てきます。物語だけではなく、日記の中にも出てきます。
古典だけではありません。算盤を習った子どもは、空中に出現させた算盤で暗算をします。障子の桟があるとよりよくできると言います。
まるでAR(拡張現実)です。私はこれを「脳内AR」と呼んでいます。
駒込(東京都文京区)にある六義園(りくぎえん)という庭は、武士が脳内ARを訓練する庭でした(これについてはいつか書きます)。

写真:写真AC
仏壇に手を合わせると母の声が聞こえてきます。お墓参りでご先祖さまと会話をするという人も多いでしょう。
日本人がふつうに持っていた脳内ARを、私たち現代人は忘れてしまっているのです。
認知症とは忘れていた脳内ARを再発動させ、能の世界を生きることなのかも知れません。
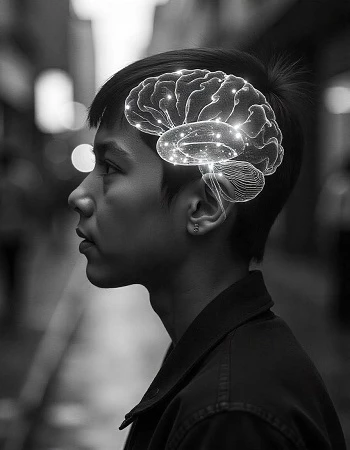
写真:Freepik
今回の記事と関連する安田さんの著書と安田さんの公式ウェブサイトをご案内します。
●『100分de名著 平家物語』(2019年5月) 安田登著 (NHK出版)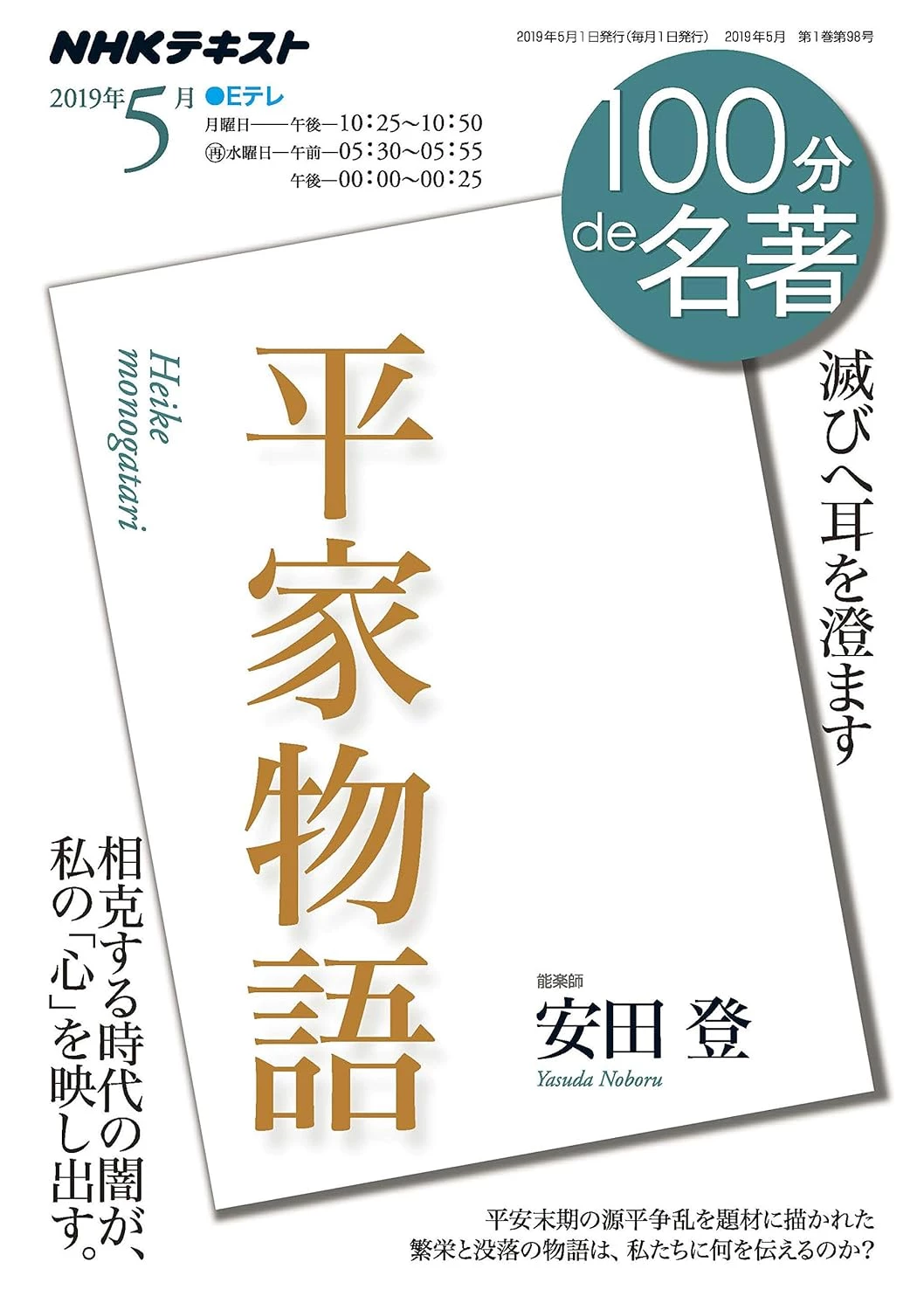
●『つらくなったら古典を読もう』安田登著 (大和書房)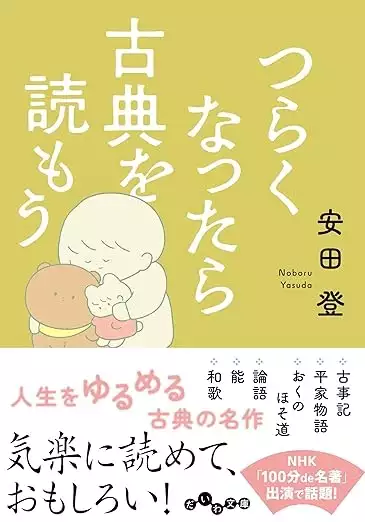
・公式HP 和と輪
写真(トップ):Freepik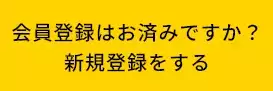

著者:安田登(やすだ・のぼる)
1956年千葉県銚子市生まれ。下掛宝生流能楽師。高校時代、麻雀とポーカーをきっかけに甲骨文字と中国古代哲学への関心に目覚める。能楽師のワキ方として活躍するかたわら、『論語』などを学ぶ寺子屋「遊学塾」の開催やNHK Eテレ『100分de名著』の講師としても知られている。著書に『あわいの力「心の時代」の次を生きる』、『イナンナの冥界下り』(ともにミシマ社)、 『能 650年続いた仕掛けとは』(新潮新書)、『あわいの時代の『論語』: ヒューマン2.0』(春秋社)など多数。近著は『つらくなったら古典を読もう』(だいわ文庫)、『話はたまにとびますが 「うた」で読む日本のすごい古典』(講談社)。