大切な家族のケアをされている皆さんにとって、将来の相続や財産の承継は気になるテーマの一つではないでしょうか。特に、自宅や実家といった「不動産」を、親が生きているうちに贈与してもらうべきか、それとも亡くなった後に相続として引き継ぐべきか、どちらがお金(税金や費用)の面で有利なのかは判断に迷うところでしょう。今回は、税理士の視点から、不動産に焦点を当てて生前贈与と相続のメリット・デメリットを比較し、どちらが税制上有利になる可能性が高いのかを解説します。
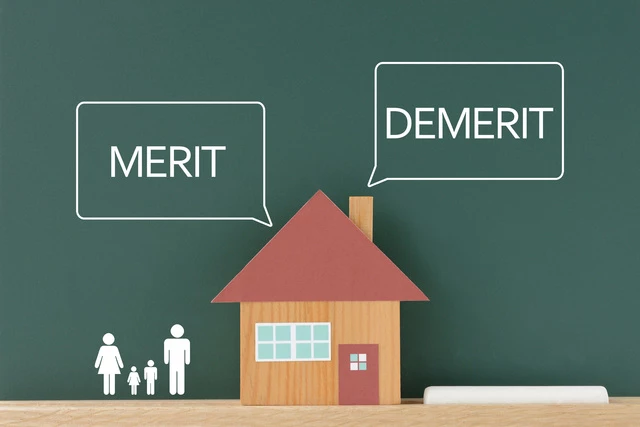
生前贈与とは、親が生きているうちに財産を子どもなどに渡すこと、相続とは、親が亡くなった後に財産を引き継ぐことをいいます。どちらも財産を次の世代に引き継ぐ方法ですが、適用される税金の種類や特例制度、かかる費用などが大きく異なります。一般的には、相続税がかかるような状況では、生前贈与の税率のほうが相続税の税率よりも低くなる可能性が高いので、「生前贈与を積極的に行ったほうがよい」といわれます。
しかし、家や土地などの不動産に関しては事情が異なります。税制上の観点からみると、不動産は生前贈与よりも、相続で引き継ぐほうが有利になる可能性が高いとされています。ただし、アパートや賃貸マンション、駐車場などの収益を生む不動産については、生前贈与も選択肢となる場合があります。

不動産を相続で引き継ぐほうが税制上有利になる主な理由は、大きく分けて2つあります。
①相続の時しか使えない、お得な特例制度がある。
②不動産を生前贈与すると、手続きにかかるお金(コスト)が高い。
こうした理由から、もし不動産と預貯金などの現金を両方持っているなら、まずは現金や他の財産から優先的に贈与していくのがおすすめです。

相続の時だけ利用できる特別な制度の一つに、「小規模宅地等の評価減の特例」があります。これは、亡くなった人が自宅として使っていた土地を、配偶者や同居していた親族が相続する場合に、その土地の評価額が最大80%も減るという特例です。
例えば、1億円の価値がある土地でも、この特例を使えば2,000万円の評価額で相続税を計算できるので、税金の負担を大幅に減らせます。土地の広さには330㎡(約100坪)までという制限がありますが、100坪を超えても100坪分までは特例が適用されます。この特例は、生きている間に贈与してしまうと使えません。
自宅の土地だけでなく、アパートや駐車場などの事業用の土地についても、一定の条件を満たせば200㎡まで、評価額が50%減る別の小規模宅地等の特例がありますが、これも生前贈与では使えません。相続まで待つことで、これらの特例をしっかり活用できるチャンスが生まれます。

2020年4月から始まった新しい制度に「配偶者居住権」があります。これは、自宅の権利を「住む権利(配偶者居住権)」と「それ以外の権利」の2つに分けて、それぞれを別々に相続できるようにするものです。
例えば、4,000万円の自宅を2,000万円ずつの権利に分け、残された配偶者が「住む権利」だけを相続することができます。配偶者には「配偶者の税額軽減」という制度があり、最低でも1億6,000万円までは相続税がかからないため、この配偶者居住権の相続には税金がかからない場合が多いです。
配偶者居住権は、配偶者が亡くなった際に自動的に消滅し、その時点で新たに相続税が課税されることはありません。つまり、二次相続(配偶者死亡時)で配偶者居住権部分については相続税の課税対象とならず、二次相続対策として活用されるケースが増えています。配偶者居住権の設定・活用は、相続税の節税や二次相続対策として有効な場合が多い一方で、ケースによっては不利益となることもあるため、必ず税理士や弁護士などの専門家に個別の状況を確認することが重要です。

不動産を生前贈与する際に、なぜ高コストになるのでしょうか。主な理由は、以下の2つの税金が大きく影響するからです。
不動産取得税:不動産を手に入れる際にかかる税金で、固定資産税評価額の3%(土地は実質1.5%、テナントは4%)が課税されます。これは生前贈与ではかかりますが、相続ではかかりません。
登録免許税:法務局で名義変更を行う際に支払う税金です。相続の場合には固定資産税評価額の0.4%ですが、贈与の場合には2%となり、なんと5倍も高くなります。
具体的な例で比べてみましょう。評価額2,000万円の不動産を贈与した場合、不動産取得税が約60万円、登録免許税が約40万円かかり、合計で約100万円ものコストがかかる可能性があります。一方、同じ不動産を相続で引き継いだ場合、不動産取得税はゼロで、登録免許税は約8万円で済みます。このように、贈与と相続ではかかるコストに大きな差があることがよく分かりますね。

不動産を毎年少しずつ贈与していく場合、その都度、司法書士に名義変更を依頼することになり、毎年、司法書士費用が発生します。これは、一度に贈与する場合や相続の場合と比べて、結果的にコストが高くなる原因になります。
さらに、生前贈与には「3年(7年)以内加算」という重要なルールがあります。これは、生前贈与をしてから3年(7年)以内に贈与した贈与人が亡くなってしまった場合、その贈与はなかったことになり、相続財産に加算されて相続税が計算されるというものです。この場合、贈与のために支払った不動産取得税や登録免許税、司法書士費用などは一切戻ってきません。つまり、せっかく税金対策としてしたのに、効果が得られないばかりか、かけたお金が無駄になってしまうリスクがあるため、十分な注意が必要です。

例外として、アパートや賃貸マンション、駐車場のように家賃収入など収益を生む不動産については、生前贈与が有利になる可能性があります。これは、不動産収入によって親の財産がどんどん増えてしまい、将来の相続税の負担が膨らんでしまうのを防ぐためです。
先に子どもに贈与しておくことで、親の財産増加を抑え、将来の相続税が増えるのを防ぐ効果が期待できます。この場合、土地ではなく、建物(上物)だけを贈与するという方法も有効だとされています。ただし、賃貸不動産の贈与には特に注意すべき点が多いため、検討する際は必ず専門家(税理士など)に相談するようにしましょう。

著者:橘 慶太(たちばな けいた)
税理士、円満相続税理士法人代表
前職の税理士法人山田&パートナーズでは相続専門の部署で6年間、相続税に専念。これまで手がけた相続税申告は、上場企業の創業家や芸能人を含め、通算500件以上。相続税の相談実績は5,000人を超える。また、全国の銀行や証券会社を中心に通算500回以上の相続税セミナーの講師を務める。2017年1月に独立開業。現在、東京・大阪・名古屋・大宮の4拠点で相続専門税理士が多数在籍する円満相続税理士法人の代表を務める。「最高の相続税対策は、円満な家族関係を構築すること」をモットーに、依頼者に徹底的に寄り添い、円満相続実現のために日々尽力する。2019年から始めたYouTubeは2025年現在、チャンネル登録者17万人を突破。2020年に出版した『ぶっちゃけ相続』(ダイヤモンド社)はシリーズ累計21万部を超えAmazonベストセラー1位を獲得する。https://osd-souzoku.jp/