お盆などで家族が集まる機会に、親の財産や今後のことについて、いつか話さなければ……と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。特に近年、相続や贈与に関する国の制度が大きく変わってきています。今回は、2024年から改正された「生前贈与」のルールに焦点を当てて、税理士が分かりやすく解説します。ケアラーの皆さんが、親御さんとの大切な話し合いを始めるきっかけになれば幸いです。

2024年1月1日から、贈与税に関するルールが大きく変わりました。特に「暦年課税」という、これまで多くの人が利用してきた制度に変更があり、今後、効果的な贈与を行うためには新しい知識をしっかりと押さえておくことが大切です。
この改正には、国がこれまであまり利用されてこなかった別の制度(相続時精算課税制度)の利用を促し、人気のあった暦年課税を使いにくくするという意図があるようです。今回の改正で、どのような場合に、誰に、どのくらい贈与するのが効果的なのかが変わってきています。知らずに以前と同じような対策をしていると、かえって損をしてしまう可能性もゼロではありません。正しい知識を身につけることが、将来の相続への備えにつながります。

贈与税の計算方法には、大きく分けて2つの制度があります。
①暦年課税制度(れきねんかぜいせいど):年間110万円まで贈与税がかからない、最も一般的な制度です。1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に贈与された財産の合計に対して課税されます。
②相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど):父母または祖父母から、子または孫に対する贈与のうち、合計2,500万円までの贈与税を非課税とする制度です。
これまで日本では、ほとんどの人が暦年課税制度を利用していました。しかし、2024年の改正により、この暦年課税制度の使い勝手が「改悪」されたと言われています。その一方で、相続時精算課税制度は「改良」され、今後は相続時精算課税制度を利用する人が増える傾向になると考えられています。
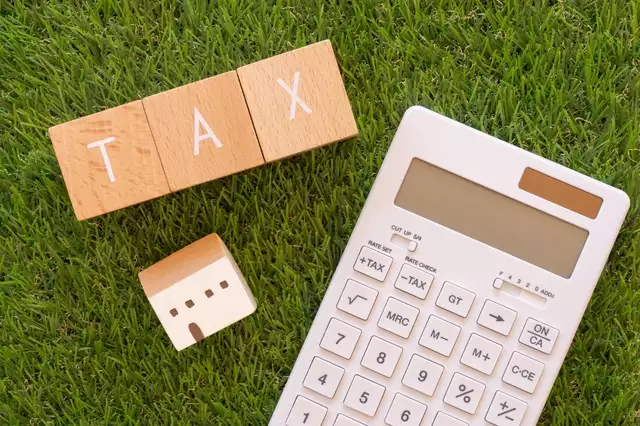
今回の暦年課税の改正で最も注目されているのが、「生前贈与加算」というルールの変更です。これまで、亡くなった日からさかのぼって3年以内に行われた贈与は、相続財産に加算され、相続税の対象になっていました。
たとえ、年間110万円以内の贈与税の非課税枠を使った贈与であっても、この3年以内の贈与は相続税の加算の対象でした。すでに贈与税を払っている場合は、相続税額からその贈与税額が差し引かれる(贈与税額控除)ことで、二重に税金がかからないように配慮はされていました。しかし、税金計算上は「なかったこと」にされてしまい、相続税の対象となるという仕組みでした。
この「3年以内加算」のルールが、2024年1月1日以降の贈与から「7年以内加算」へと変更されました。つまり、亡くなった日からさかのぼって最大7年以内に行われた贈与が、相続財産に加算される可能性があるということになります。
ただし、注意が必要なのは、この「7年」というのは2024年以降に贈与された財産から徐々に延長されていくということです。例えば、2024年に贈与した人が2027年に亡くなった場合、さかのぼるのは3年(2024年まで)です。2024年に贈与した人が2031年に亡くなった場合、さかのぼりは7年(2024年まで)となります。あくまで2024年1月1日以降の贈与が新しい7年ルールの対象となり、2023年12月31日までの贈与は3年ルールのままです。
この改正により、生前贈与で相続財産を減らしておこうとする場合に加算される期間が、これまでの3年から7年へと倍以上に長くなったため、「実質的な増税」とも言われています。

では、この7年以内加算ルールは、誰への贈与でも適用されるのでしょうか。実は、このルールの対象となる人は限定されています。7年以内加算の対象となるのは、「相続又は遺贈により財産を取得した者」と定義されています。これはどういうことかというと、贈与をしてくれた人が亡くなった際に、その人の「相続人」となる人への生前贈与が、原則としてこの7年ルールの対象になるということです。
裏を返せば、亡くなった人から見て、将来、「相続人」にならない人への贈与は、基本的にこの7年ルールの対象外となります。具体的には、お孫さんやひ孫さんへの贈与です。極端な例として、亡くなる直前にお孫さんやひ孫さんに贈与したとしても、このルールが適用されないため、相続税の対象にならないということです。これは、3年内加算の時代から変わらない取り扱いです。そのため、税金対策としては、原則として相続人とならない人(お孫さんなど)への贈与を積極的に検討することが有効だと考えられています。
ただし、例外もあります。例えば、相続人であっても「相続放棄」をして財産を一切取得しない場合は、7年内加算の対象外となることがあります。逆に、孫など相続人ではない人が、遺言によって財産を受け取ったり、生命保険の受取人になったりした場合は、「相続又は遺贈により財産を取得した者」に該当するため、その人への生前贈与は7年内加算の対象となります。

改正によって使い勝手が悪くなったと言われる暦年課税制度ですが、それでも利用をおすすめできるケースがあります。それは、主に以下の2つのケースです。
「相続人以外」へ贈与する場合:先ほども触れましたが、お孫さんなど、亡くなった人の相続人ではない人への贈与は、原則として7年以内加算の対象外となります。したがって、相続税対策として有効な手段であり、暦年課税制度を利用するメリットは引き続き大きいといえます。
「7年以上生きると見込まれる」人:贈与をした人が、贈与から7年以上経過してから亡くなれば、その贈与は7年以内加算の対象外となります。特に、まだ若い人(例えば60代など)で、今後7年以上健康でいられる見込みが高い人にとっては、暦年課税制度は有効な選択肢となり得ます。
これらのケースに当てはまらない、つまり「相続人に対して贈与する」かつ「7年以内に相続が発生する可能性がある」といった場合は、「相続時精算課税制度」の利用を検討したほうが有利になる可能性があります。

暦年課税制度を利用する場合、多くの人が「年間110万円以内なら税金がかからないから、毎年110万円ずつ贈与すればいい」と考えがちです。もちろん、これも有効な手段の一つですが、実は贈与税をあえて払ってでも、年間110万円を超える金額を贈与したほうが、最終的な手残りが多くなる可能性があるという考え方があります。
なぜそうなるのでしょうか。これは、贈与税と相続税の「税率構造」の違いに関係しています。税率表を比べると、一般的に贈与税率のほうが高く見えるかもしれません。しかし、相続は人生で一度しか発生しないのに対し、生前贈与は何年にもわたって「小分け」に行うことができます。
そして、最も重要なポイントは、生前贈与によって財産が減ると、将来かかる相続税は「一番税率の高い部分」から減少していくということです。一方、贈与税は、一度に大きな金額を贈与すると税率が高くなりますが(累進課税)、金額を抑えれば比較的低い税率で済む場合があります。
例えば、相続財産が多い人ほど、適用される相続税の最高税率が高くなります。もし、その最高税率よりも低い税率で贈与税を支払いながら生前贈与を行えれば、将来減る相続税額(高い税率)が、今払う贈与税額(低い税率)を上回り、結果として税負担の合計を減らすことができるのです。
具体的なシミュレーションによると、相続税が多額にかかる人の場合、年間110万円の非課税贈与だけを行うよりも、年間数百万円など、あえて贈与税が発生する金額を贈与し続けたほうが、最終的な節税効果が大きくなることが示されています。
では、いくら贈与するのが「最適」なのでしょうか。これは、贈与する人の財産状況や将来の相続人の数によって、適用される相続税の最高税率が変わるため、一律には言えません。最適な贈与額を知るためには、まず「今の財産状況で相続が発生した場合、相続税がいくらかかるか」「適用される相続税の最高税率は何%か」を計算する、つまり「相続税の試算(現状分析)」を行うことが大前提となります。

2024年の税制改正(*)により、生前贈与のルール、特に暦年課税制度の「7年以内加算」が始まり、適用対象者にも注意が必要となりました。相続人以外への贈与や、贈与から7年以上存命が見込まれる人にとっては、引き続き暦年課税が有効な手段となり得ます。さらに、相続税が多くかかる人にとっては、あえて贈与税を払ってでも年間110万円を超える金額を贈与したほうが、全体の税負担を減らせる可能性があることをご紹介しました。
効果的な生前贈与を含む相続税対策を行うためには、まずは現状で相続税がどのくらいかかるのかを把握し(現状分析)、どのように遺産を分けるのがよいかを考える(遺産分割対策)といった、基本的なステップを踏むことが非常に重要ですし、生前贈与についてはこれらの検討を踏まえた上で、最適な金額を計画的に行うのがおすすめです。
お盆などでご家族が集まる機会に、こうした税金の話をするのは難しいと感じるかもしれませんが、将来のためには避けて通れないテーマです。今回の改正を機に、「そういえば贈与のルールが変わったらしいよ」といった形で、親御さんと少しずつ話し合いを始めてみるのもよいかもしれません。
漠然とした不安を具体的な対策につなげるためには、専門家である税理士に相談するのが一番確実です。現状分析や遺産分割シミュレーション、最適な生前贈与額の計算など、専門的なアドバイスを受けることで、ご家族にとって最適な対策が見えてくるでしょう。
*2024年の税制改正・・・令和5年度相続税及び贈与税の税制改正(令和6年1月1日施行)のこと
構成:研友企画出版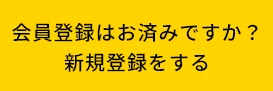

著者:橘 慶太(たちばな けいた)
税理士、円満相続税理士法人代表
前職の税理士法人山田&パートナーズでは相続専門の部署で6年間、相続税に専念。これまで手がけた相続税申告は、上場企業の創業家や芸能人を含め、通算500件以上。相続税の相談実績は5,000人を超える。また、全国の銀行や証券会社を中心に通算500回以上の相続税セミナーの講師を務める。2017年1月に独立開業。現在、東京・大阪・名古屋・大宮の4拠点で相続専門税理士が多数在籍する円満相続税理士法人の代表を務める。「最高の相続税対策は、円満な家族関係を構築すること」をモットーに、依頼者に徹底的に寄り添い、円満相続実現のために日々尽力する。2019年から始めたYouTubeは2025年現在、チャンネル登録者17万人を突破。2020年に出版した『ぶっちゃけ相続』(ダイヤモンド社)はシリーズ累計21万部を超えAmazonベストセラー1位を獲得する。https://osd-souzoku.jp/