相続は、いつか誰にでも起こり得る出来事です。しかし、「うちには関係ない」「まだ早い」と考えて、何も準備をしていないという人も多いのではないでしょうか。何も対策をせずにいると、いざという時に残された家族が困ってしまったり、思わぬ多額の税金がかかってしまったりする可能性があります。この記事では、相続対策を始めるにあたって大切な「4つのステップ」を税理士が解説します。お盆など、家族が集まる機会に、相続について話し合うきっかけにしていただけたらうれしいです。

相続対策と聞くと、遺言書や生前贈与、不動産の活用など、さまざまな方法があって難しく感じるかもしれません。一体何から始めればよいのでしょう。
相続対策にはさまざまな方法がありますが、最も重要なことは「順番」を守ることです。やみくもに個別の対策に手を出すのではなく、「何を、どの順番で行っていくか」が、相続対策を成功させる鍵となるのです。
今回ご紹介するのは、「相続対策4つのステップ」です。このステップを正しく踏むことが、相続対策の第一歩となります。

相続対策の第一歩は、「現状分析」です。これは、例えるなら、体の「健康診断」と同じ。もし、突然相続が発生してしまった場合に、一体何が起こるのかを正確に把握することから始めます。具体的には、次のような点を洗い出します。
・お父さんやお母さんがどのような財産(不動産、預貯金、株式など)をどれくらい持っているのか
・もし今、相続が発生したら、どれくらいの相続税がかかるのか
・その相続税を支払うための資金(納税資金)は足りるのか
・家族の間で遺産を円満に分けることができるのか
現状を正確に把握することで、どのような対策が本当に必要なのか、その方向性が見えてきます。この現状分析をしっかりと行うことは、当たり前のことのように聞こえるかもしれませんが、実は最も大切なのです。
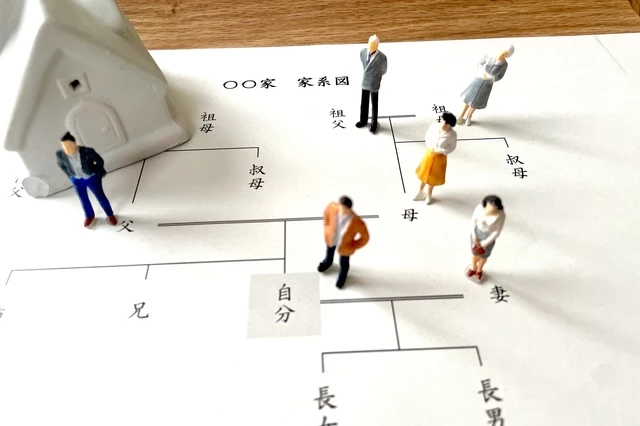
現状分析で問題点が把握できたら、次に考えるべきは「遺産分割対策」です。これは、もし今相続が発生した場合に、残された財産を家族でどのように分けるかをあらかじめ決めておく対策です。必要に応じて、遺言書の作成もここで行います。
この遺産分割対策がなぜ重要かというと、遺産の「分け方」次第で、かかる相続税の額が何倍にも変わってしまうことがあるからです。特に、以下の特別なルールを上手に活用できるかどうかは、遺産の分け方にかかっています。
・配偶者の税額軽減:配偶者が相続する場合に、一定の金額まで相続税がかからないという制度。
・小規模宅地等の特例:自宅や事業用の土地などについて、一定の要件を満たす場合に、評価額を最大80%減額できるという制度。
さらに、考えるべきは相続税だけではありません。相続人が遺産を相続した後に、それを売却する場合にかかる税金(譲渡所得税)など、相続人の所得税や住民税の負担も考慮する必要があります。
中小企業の経営者の場合は、相続税や所得税に加えて、法人税まで影響することもあります。税理士などの専門家は、これらの税金全体で最も負担が少なくなる分け方(最適解)を探る役割を担います。ただし、専門家が提案する分け方はあくまで税金面で最も有利になる分け方であり、最終的には家族それぞれの「お気持ち」を反映させて、納得のいく分け方を決めることが大切です。
このように、遺産分割対策は、税負担を軽くするためだけでなく、家族が円満に相続手続きを進めるためにも非常に重要なステップなのです。後で説明する「生前贈与」よりも先に、この遺産分割の方針をしっかり決めておくことが、失敗しないためのポイントです。

遺産分割対策の次に考えるのが、「評価の引き下げ対策」です。これは、お持ちの財産の種類を組み替えたり、定期的に入ってくる収入(家賃など)が誰のものになるかを変えたりすることで、相続税の計算のもとになる「財産評価額」そのものを小さくするアプローチです。具体的には、次のような方法があります。
現金を生命保険に変える:生命保険金は、法定相続人の人数×500万円まで非課税になる枠があります。現金をこの非課税枠の範囲内で生命保険にしておくことで、その分だけ相続財産を減らすことができます。
現金を不動産に変える:現金で不動産を購入すると、その不動産の評価額は、購入した金額よりも低くなることが一般的です。これにより、財産の評価額を圧縮する効果が得られます。
家をリフォームする:自宅などをリフォームすることでも、評価額を下げる効果がある場合があります。
生前にお墓を買っておく:お墓は相続税がかからない非課税の財産です。現金を使い生前にお墓を購入しておくことで、相続財産を減らすことができます。
収入の帰属先を変える:例えば、アパートを経営していて家賃収入がある場合、アパートの所有権をあらかじめ相続人(子どもなど)に移しておくことで、その後の家賃収入が子どもの財産として貯まることになります。これは、本来、親の財産になるはずだった収入を将来の相続人の財産にすることで、親の財産が増えるのを抑え、将来の相続税負担を軽減する対策です。
これらの対策は、財産の性質を利用して相続税の対象となる評価額を小さくし、結果として相続税そのものを小さくすることを目指します。

評価の引き下げ対策の後に検討するのが、「生前贈与対策」です。これは、被相続人となる人(親など)が生きているうちに、将来相続人になる可能性のある人(子どもや孫など)に財産を贈与することで、相続が発生した時の財産を減らし、将来の相続税負担を軽減する対策です。生前贈与にはいくつかの方法がありますが、多く利用されるのは暦年課税制度です。暦年課税では、年間110万円までの贈与であれば贈与税がかからない「非課税枠」があります。
2024年からは、この生前贈与のルールが大きく変わりました。特に注目すべきは、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」という2つの制度を、以前よりも上手に組み合わせて使えるようになった点です。例えば、お父さんから相続時精算課税制度を使って110万円、お母さんから暦年課税制度を使って110万円の贈与を受けた場合、合計220万円まで非課税で贈与を受けられる可能性があります。これは2023年までにはできなかったことです。
このように、2024年以降は両制度の長所を最大限に活かしたプランニングが重要になります。生前贈与は、計画的に長期間行うことでより効果が高まる対策です。
ただし、先に述べた通り「順番」が大切です。生前贈与対策は、遺産分割対策や評価の引き下げ対策が固まった後に行うのが望ましいとされています。もし遺産分割の方針が決まる前に生前贈与だけを進めてしまうと、かえって家族の間で不公平感が生まれたり、本来受けられたはずの税制上の特例が使えなくなったりして、結果的に相続税負担が増えてしまうといった事態になりかねません。

相続対策を考える上で、もう一つ非常に大切なことがあります。それは「相続税の税務調査対策」です。相続税の申告書を税務署に提出した後、1年から2年後に「税務調査をさせてほしい」と連絡が来ることがあります。
日本の相続税申告(2021年度)は年間134,275件行われていますが、そのうち約6.3%にあたる8,556件で税務調査が実施されています。さらに、税務調査ほど本格的ではないものの、「簡易な接触」と呼ばれる簡単な調査も18,781件(約13.9%)行われています。つまり、申告をした人のうち約5人に1人が何らかの形で税務署から問い合わせや調査を受けているのが現状です。そして、一度税務調査の対象になると、約84.2%のケースで追加で税金を納めるよう求められています。これを「追徴課税」といいます。
相続税の申告は、所得税のように毎年行うものではなく、人生で一度きりの場合がほとんどです。そのため、税務署は特にしっかりと調査を行い、見逃さないようにしています。ですから、相続対策を検討する際には、将来の税務調査に備え、誤りのない、根拠を明確に示せる申告書を作成することが極めて重要です。信頼できる税理士に依頼する場合も、税務調査の立ち会いの経験があり、最後まで責任を持って対応してくれる専門家を選ぶことが推奨されます。

ここまで、相続対策の4つのステップと税務調査対策について解説してきました。これらの対策は、円満な相続を目指す上で非常に有効です。しかし、実はこれらの対策がスムーズに進むためには、最も根本的な「前提条件」があります。それは、「家族の仲が良い」ということです。
遺産分割にしても、評価の引き下げにしても、生前贈与にしても、ご家族の間で意思疎通ができており、協力的な関係にある場合に、これらの対策は効果を発揮します。もし家族仲が悪い場合、遺産の分け方でもめてしまったり、生前贈与を受けた、受けないでトラブルになったりして、せっかくの対策も思うように進められないことが多いのです。
ですから、相続対策における究極の、そして最も大切な税金対策は、実は「家族仲を円満にしておくこと」だといえます。日頃から家族でコミュニケーションを取り、お互いを思いやる気持ちを持つことが、何よりも重要です。お盆などで家族が集まる機会は、まさにこうした大切なことを話し合う絶好のチャンスといえるでしょう。
そして、良い相続対策は、専門家が一方的に進めるものではありません。依頼する側であるご自身が、専門家からの説明をしっかりと理解し、納得した上で進めていくことが大切です。専門家を選ぶ際には、難しい専門用語を避け、誰にでも分かりやすく説明してくれるかどうかも、腕の良さを判断する重要な指標になります。税理士などの専門家の知識や経験を借りながら、家族みんなで話し合い、納得のいく形で相続の準備を進めていくことが、将来の安心につながるのです。

相続は「争族」とも言われるように、何も準備をしないままでは、残された家族の間でトラブルになってしまうことも少なくありません。また、本来払う必要のない多額の税金がかかってしまう可能性もあります。今回ご紹介した「現状分析」→「遺産分割対策」→「評価の引き下げ対策」→「生前贈与対策」という正しい順番で対策を進めること、そして税務調査に備えることは非常に重要です。
しかし、その大前提として、家族の円満な関係があることを忘れてはいけません。そして、専門家と協力しながら、ご自身が理解した上で対策を進めることが大切です。この記事が、皆さんがご家族と相続について話し合い、より良い未来への一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。
構成:研友企画出版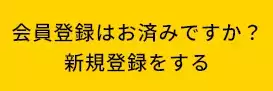

著者:橘 慶太(たちばな けいた)
税理士、円満相続税理士法人代表
前職の税理士法人山田&パートナーズでは相続専門の部署で6年間、相続税に専念。これまで手がけた相続税申告は、上場企業の創業家や芸能人を含め、通算500件以上。相続税の相談実績は5,000人を超える。また、全国の銀行や証券会社を中心に通算500回以上の相続税セミナーの講師を務める。2017年1月に独立開業。現在、東京・大阪・名古屋・大宮の4拠点で相続専門税理士が多数在籍する円満相続税理士法人の代表を務める。「最高の相続税対策は、円満な家族関係を構築すること」をモットーに、依頼者に徹底的に寄り添い、円満相続実現のために日々尽力する。2019年から始めたYouTubeは2025年現在、チャンネル登録者17万人を突破。2020年に出版した『ぶっちゃけ相続』(ダイヤモンド社)はシリーズ累計21万部を超えAmazonベストセラー1位を獲得する。https://osd-souzoku.jp/