「父が祖父から引き継いだ土地が田舎にある」ということは知っていても、それがどのくらいの広さで、管理するのにどのくらいの費用が掛かっているのか、そもそも父はその土地をどうしたいのか、私はまったく知らなかった。親との「ケア活」を怠ったことによる後悔と、なんとか親の財産の整理をやり遂げるまでのお話です。
突然ですが、みなさんは親が所有している財産(土地や金融商品なども含む)について、どこまで知っていますか?
私は、「父さんって、先祖から引き継いだ田舎の土地を持っているよねー」くらいのざっくりとした情報しかわかっていませんでした。でも、さまざまな事情でその田舎の土地を処分することになったとき、「ざっくりとした情報」だけでは、対応できないアレやコレがモリモリと現れて、そのためにお金や時間が想像以上に掛かってしまいました。
そんな私のような後悔をしないために、親との「ケア活」において「こんな大変な思いをした人がいるみたいだけど、うちはどうなの?」と私の話を引き合いに出して、親が元気なうちに、後悔のない親との「ケア活」をするきっかけになればと思い、このコラムを書いています。そして、1人でも「岡崎さんの話が役に立ったよ」と言ってもらえたならば、「なんで、教えてくれなかったのよー」と恨み節ばかりだった、当時の私も救わることでしょう(そもそも親との「ケア活」を怠った自分も悪いのだけど……)。
その始まりは突然でした。今から5年前の冬、母が自宅のお風呂から天国に旅立ってしまったのです(詳細は「親の介護をする前に知っておきたかった12のこと【その10とその11 】」をお読みください)。
父親は50代から若年性認知症になってしまったのですが、母もガンを患うなど大病を繰り返していました。それなのになぜか母は「私が父さんより先に逝くことは、絶対ない!」と信じて疑っていませんでした。それ故母は、「父さんに何かあったら話す」と私に実家の財産について語ろうとしませんでした。一方で介護仲間などからは「介護が終わったあとも、相続とかいろいろ大変だよ」という話を聞いていた私は、少しでも情報を得ようと保険のことなどでお世話になっているファイナンシャルプランナー(FP)に頼んで実家に同行してもらったりしたのですが、「そのことは私が父さんを見送ったあとでいい!」と拒絶されてしまいました。
結果、実家の財産状況について何も知らされないまま母は逝ってしまったので、介護仲間が言っていたように「介護が終わったあとも、相続とかいろいろ大変だよ」を経験することになってしまったのです。
まず行ったのは、母親の財産の相続に関する手続き。期限である10ヶ月以内(みなさん、この期限を知っていましたか?)に相続に関する手続きを終えました(このあたりもまたいつか書ければと……)。その後には、当然ではあるのですが、それまで母が管理していた父の財産の管理がマルっと私に降ってきたのです。そこで、冒頭に挙げた質問を思い出していただきたいのです。
もし、あの質問に答えられなかったり、なんとなくの答えしか知らないのであれば、きっとあなたにも、以下で語るようなことが起きると覚悟をしてください。
母が亡くなった翌年の6月頃、父の所有している田舎の土地のある市町村から「固定資産税」のお知らせが実家に届きました。それを見て「そういえば、父さんが先祖から引き継いだ田舎の土地があったね」ということを思い出しました。きっとこれまでこういった支払いの対応も、施設に入所している父に代わって母がしてきたのでしょう。母亡きいま、その役目は一人娘である私に自動的に降りかかってきました。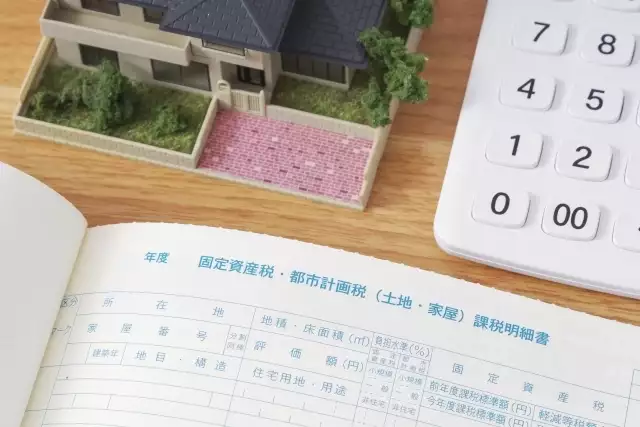
同じ頃、その土地のある町の草刈り業者からまた実家に手紙が届きました。そこには「奥様の電話が繋がらないので、手紙にて…」と書かれていました。どうやら、更地になっているその土地には雑草が生い茂っていたため、そこに火でも点いて燃え広がると危ないと、以前に地元の消防署から連絡を受けていたようなのです。
そこで両親は雑草が伸びるたびに手紙をくれた業者に草刈りを依頼していたようなのです。手紙には、「今年は連絡がないけれど、どうしますか?」といった内容が書かれていました。すぐにその業者に電話をし、母が亡くなったことを伝えると、業者の方はひどく驚き、お悔やみの言葉をいただきました。
しかしその後、「で、今年はどうします?」という話の流れになりました。私にとっては「?」な展開ではありますが、お願いしないと地元の消防署から注意を受けることは確実だったため、とりあえずは毎年恒例ということで、手紙をくれた業者に今年もお願いすることにしました。
しばらくして再び草刈り業者から私に電話が入りました。その土地の周辺には住宅が立ち並びはじめており、数年ほど前から、約2日かかる草刈りの作業音に苦情を言う人が出てきたというのです。業者は作業の前にその人に菓子折りを持って挨拶に行っており、その費用も両親は出していたということで、今年もその費用を計上してもいいか、という質問でした。
なんとなく「NO」とは言えない話なので、「では、例年通りで」とお願いしました。行ったことも見たこともない土地のため、広さもわかりませんでしたが、数日後に草刈り業者から送られてきた草を刈った土地のビフォーとアフターの写真、見積書には約4万円という金額が (ネットでいろいろ調べましたが、土地の広さ的に妥当でした)!
ここで、私はこう思ったのです。「何十年も誰も住んでいない土地に、両親はいったいいくら費やしてきたの?」「この費用や、やり取りの手間は、本当に必要なの?」
さらに、それまで私はまったく知らなかったのですが、田舎の土地の草刈は夏と秋に2回行っているということでした。つまり、草刈だけで年間で約8万円! それに固定資産税が加わると年間で約10万円が父の貯えから田舎の土地のために消えていくというわけです。母はめんどくさがり、父とこの問題と向き合わなかったようですが、今後、マイナスにしかならない父の貯えを少しでもキープするために、私はこの問題と向き合うことにしました。
イラスト(下):日野あかね

少し話が逸れますが、当たり前と言えば当たりまえで、たとえ親の銀行口座の暗証番号を知っていても、そこから子どもが勝手にどういうすることはできません。
【この話、ちょっと難しいので専門家(司法書士 村山先生)が解説!】
親の暗証番号を使って子どもがATMでお金を引き出すのは、本来は法律上認められていません。各種金融機関の取引規定には、『キャッシュカードを他人に貸与・使用させることはできない』と明記されており、名義人本人以外がカードや暗証番号を用いて取引を行うことは契約違反になります。
そのため契約違反や刑法上の問題となる可能性があり、後々の相続時などでトラブルの火種になります。実際の対応は代理人登録制度や任意後見など、正しい方法を利用するのが安心です。
親の代わりに親の口座から代金などを支払うには、親が元気、あるいは意思判断能力があれば、代理人カードや予約型代理人サービスのほか、任意後見や家族信託などの方法もあります。もし何も準備しないまま親が認知症(意思判断能力がない)になってしまったら、原則として、家庭裁判所に法定後見を申し立てることになります。また、子どもが自分の口座から親の費用を立て替えること自体は可能ですが、領収書を残して後日親の財産から清算しないと「贈与」とみなされる恐れがあるため、注意が必要です。
※成年後見制度や家族信託については「財産整理編②」で詳しく解説します
村山先生の解説にあるように、固定資産税や草刈代を私が施設に入所している父の代わりに父の銀行口座から振り込むわけですが、それを行うには親の口座のある銀行で代理人カードや指定代理人制度(私と父はコレ!)活用するなど、ここでも事前の手続きが必要となります。思った以上に!?個人の財産は守られているため、親が元気なうち(判断能力のあるうち)に対応しておくと、のちのち子どもが大変な思いをしなくて済むというわけです。
そこで私は施設に行き、父に「田舎の土地のことなんだけど…」と相談すると、はじめのうち父は「先祖代々の土地だから」と言い出しました(認知症になってもこのあたりの記憶はしっかりしている)。そこで私は、「父さんはあそこにもう住むつもりはないでしょう? 周りに住んでいた親戚もみんな亡くなってしまい誰もいないよ。今は管理費ばかりが掛かる感じになっているんだけど」と現実を伝えました。父と娘による、財産に関する遅すぎる「ケア活」が始まったのでした。
※ブライバシー保護の観点から、一部フィクションが含まれています
監修、アドバイス:村山澄江
写真:PIXTA、写真AC
【監修者プロフィール】
村山澄江(むらやま・すみえ)…民事信託・成年後見の専門家、司法書士。生前対策の対応実績は1500件以上。民事信託と成年後見の専門家として全国でセミナー等も行っている。日本経済新聞、朝日新聞などでの取材記事多数。著書に『今日から成年後見人になりました』(児島 明日美氏との共著)、『認知症に備える』(中澤まゆみ氏との共著)(ともに自由国民社)がある。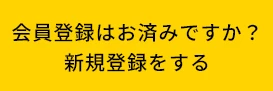

著者:岡崎 杏里
大学卒業後、編集プロダクション、出版社に勤務。23歳のときに若年性認知症になった父親の介護と、その3年後に卵巣がんになった母親の看病をひとり娘として背負うことに。宣伝会議主催の「編集・ライター講座」の卒業制作(父親の介護に関わる人々へのインタビューなど)が優秀賞を受賞。『笑う介護。』の出版を機に、2007年より介護ライター&介護エッセイストとして、介護に関する記事やエッセイの執筆などを行っている。著書に『みんなの認知症』(ともに、成美堂出版)、『わんこも介護』(朝日新聞出版)などがある。2013年に長男を出産し、ダブルケアラー(介護と育児など複数のケアをする人)となった。訪問介護員2級養成研修課程修了(ホームヘルパー2級)
https://anriokazaki.net/