全国的に高齢化が進む日本の地域社会において、高齢者の孤独死や急病への対応は大きな課題となっています。そんな中、滋賀県大津市・仰木の里(おおぎのさと)で2024年6月から半年に渡ってある社会実験が行われました。見守りの機能を備えた象印マホービンの電気ポット「みまもりほっとライン」を用いて11世帯の方の見守りを協議会が中心となって行ったのです。日常的に使う電気ポットを介して自然で抵抗感の少ない見守りを可能にする同商品の特長を活用しながら、住民・協議会・メーカーが協力して行ったこの試みについて、当事者である仰木の里学区まちづくり協議会の運営者の方々への取材をもとに、その有効性と課題を考えました。そこで見えてきた地域の声、そして取材者が感じた“人と人が支え合う”未来像について、お伝えします。
象印の「みまもりほっとライン」は、安否確認機能を備えた電気ポットを利用した見守りサービスです。その商品特長には以下のようなものがあります。
●自然な見守り:利用者がポットでお湯を沸かす、給湯するなど日々の操作をすると、そのデータ履歴が離れて暮らす家族や見守る人に自動通知。一定時間操作がない場合は異変として知らせます。
●抵抗感の少ない仕組み:カメラやセンサーによる監視ではなく、生活の延長線上で行えるため、見守られる側も心理的負担が小さいのが特長です。
●実績と信頼性:20年以上の運用実績があり、契約者は1万4,000人超(2025年9月時点)。
●導入の手軽さ:初期費用5,500円、月々のレンタルで月額3,300円(初月無料)。工事不要でオンライン申し込みのみで設置できます。
※レンタルでも新品をお届けします。
多くの家庭で見守りに活用されてきたこの「みまもりほっとライン」。この商品の社会実験モニターを象印マホービンで募集していたところ、仰木の里学区まちづくり協議会運営者の知人からの情報を得て、同団体がモニターとして実験に参加することになったということです。
滋賀県大津市のニュータウン「仰木の里」は、1980年代にURによって開発され、現在まで50年近い歴史があります。2022年10月時点での住民数は約1万3000人、世帯数は5400弱という規模で、琵琶湖のほど近くの緑豊かな山間に戸建てを中心とした住宅が立ち並ぶ閑静な住宅地です。
日本のどの郊外の都市にも共通することですが、現在では65歳以上が3割を超えるなど住民の高齢化が進み、一人暮らしの高齢者の方も増え、孤独死への対応の問題も抱えていました。そこで協議会が主体となって対応に乗り出し、その一環が「みまもりほっとライン」を用いた社会実験となっています。以下は、仰木の里学区まちづくり協議会会長の林勉様、同協議会副会長の山本弘道様、同副会長の足立純造様とのやりとりです。
2-1 導入の経緯
–導入の経緯について教えてください。
林様 「令和6年に発足した「まちづくり協議会」のテーマのひとつが福祉のまちづくりというもので、そのための方法を模索していた時に住民の方を通じて象印様の“みまもりほっとライン”を紹介されました。独居の方が一人で亡くなられるケースもあり、徘徊する高齢者の方の見守りも課題でした。ポットを通じて自然に安否確認できる点が、地域のニーズに合致したんです」
仰木の里学区まちづくり協議会会長の林勉様
2-2 実験の概要と参加者
–-実験に参加された方々の年代や家族構成などを教えてください。
山本様 「11世帯の方が参加してくれたのですが、最年長は94歳、最年少は68歳の方でした。利用者の方の情報は林会長が受信する形で運用していました。終了後も2名が契約を継続しており、そのうちの1名の方はご家族が見守りをするという形を取っていると聞いています」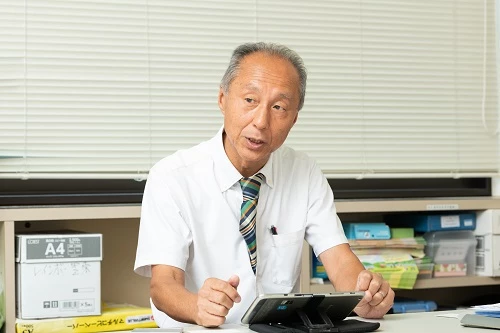
仰木の里学区まちづくり協議会副会長の山本弘道様
2-3 運用する中での課題
--実験の際のご苦労や気づかれたことはありましたか?
林様 「夏場にポットでお湯を沸かす習慣がない方もいますので、そのことはまずハードルになりました。また、ポットの利用がなく変化がない場合、どこでその方々の異変を判断するのかというところは管理者として非常に苦労したところです。また、夫婦世帯はポットの使用頻度が少なく、独居の方に向いている商品だということも感じました。
今回の参加者は11世帯でしたから、1日1回11世帯分の結果が一気に来て、何時間使用されていないなどの情報が一目瞭然で出ますから、確認すること自体にそれほど苦労はなかったです。世帯数がもっと多くなっても一人が見守る場合にどう対処するのかというところは課題だと思います。
通常の見守りについてはご家族がされると思いますが、今回の実験では利用者のご家族との通報システムについては構築できていませんでした。今後の利用形態によっては信頼をもってお互いの個人情報を扱うことが必要になってくるのではないかと思います。
参加者の中で独居の方がいたのですが、お湯を飲んだり使ったりする習慣がその方の生活の中でマッチしたというご感想がありました。夏場ですとすぐに冷たいものに手を出しがちなんですが、高齢になってくればくるほど、お湯を飲んで水分補給をするということも有効なんです。そういった健康上の面でも気づきがありました」
2-4 住民の実感と気づき
–この「みまもりほっとライン」について、他の商品と比べての感想や社会実験を終えて思われたことなどがありましたら教えてください。
足立様「商品によっては、「こんな便利なものがこんなに安いですよ」というように売り込まれるものもありますが、そういうものはいわゆる『便利グッズ』なわけです。ですが、見守りにはまず、理屈じゃない気づきがあって、その後にどう動くかが重要なわけですが、最初の気づきのところが非常に難しい。ある意味、人間的なことですから。変に出しゃばったら嫌がられるし、かといって長いこと放っておけば手遅れになってしまう。いずれにせよ、相手に対してのあったかい気持ちがないと、気づきなんてないんですよね。無関心では無理です。ですからそういう気持ちでやっていける人を作っていく、そういうまちづくりをしていかなあかんと思ってるんです。まちづくりの中に高齢者の見守りを入れるのではなくて、高齢者を見守るという中でまちづくりそのものを考えていきたいと思っています。
気づきというところは非常に難しいのですが、そこに1つIT機器があることで、動きやすくなるということがあるんです。また、重大な災害がいつ起こるかわからんような状況ですし、孤独死をなくすという意味でも、見守りには地域の活動との連携が絶対に必要なんです。そんな中で、この象印様の取り組みの価値を伝えていきたいと思っています」
仰木の里学区まちづくり協議会副会長の足立純造様
山本様 「福祉のまちづくりをやっていくということも、住民の方にはまだまだ十分に広がっていないのが現状なので、風土作りは大事ですね。見守られる方もこの町だったら自分のことちゃんと見守ってくれるという思いがあれば、それは子供たちにも伝わって、子供たちもそういう形で支援してもらおうかというふうに思うと思うんですよね。
見守りは家族がせなあかんのですが、実際には一人暮らしの方の中では親戚のない方とかもいらっしゃるんです。そうなった時にどう見守っていくかというのは、課題でもあります。今後はそういうケースが増えてくると思うんです。子世代などに費用や手間を負担してもらうことができない場合、国や地方や自治体から支援していくことも1つの考えとして出てくると思うんですよね。そういうことも考えながら、風土作りを進めていかなければと思っています」
どの地域でも課題となっている少子高齢化。その中で見守りはますます重要なテーマになりつつあります。取材を終えて感じたのは、見守りにおいては手法や機器そのもの以上に“人が人を気づかう文化”が不可欠だということでした。「みまもりほっとライン」は、見守りにおけるそういったデリケートな部分で使う人、見守る人に寄り添える機器なのだということも改めて感じました。
また、取材の中で聞かれた「理屈じゃない気づき」「無関心では無理」ということ、そして取材に立ち会った象印マホービンの小倉秀雄様が「みまもりほっとライン」の事業に対する思いを「〝社会に貢献したい〟という思いからのもの」と表現されたことが印象的でした。
「みまもりほっとライン」は、離れて暮らす家族が親を思う気持ち、地域の人たちが互いを思いやる温かさ、その両方をそっと後押しします。技術は使い方次第で地域の信頼関係を深める“触媒”になり得る。他の多くの地域にとっても、ポット一つが“人と人を結ぶインフラ”となる可能性を感じました。
写真:三上 富之

著者:MySCUE編集部
MySCUE (マイスキュー)は、家族や親しい方のシニアケアや介護をするケアラーに役立つ情報を提供しています。シニアケアをスマートに。誰もが笑顔で歳を重ね長生きを喜べる国となることを願っています。