介護の現場は日々変化しています。近年、福祉用具の選択肢は驚くほど広がり、「こんな便利なものが介護保険で使えるのか」と目を見張る機会も少なくありません。
けれども、必要な情報を自力で探し、適切な用具やサービスを選び取ることは簡単ではありません。情報が行き届かずに「これは無理だ」「使えないだろう」と思い込んでしまい、可能性を閉ざしてしまうこともあるのです。
私自身、要介護5の寝たきりの母を在宅で介護していた頃、今のような製品や仕組みを知ることができていたら――と思う場面が何度もありました。一人で抱え込まず、専門職や支援者とつながることで、見えてくる道があります。
関西在住のSさん(60代女性・パート従業員)は、90代の父親と二人暮らし。昨年までは、近くの山に登ったり、ハイキングを楽しむほど元気だった父親ですが、脊椎の圧迫骨折をきっかけに、今年に入ってからは歩行が困難になってしまいました。
一度目の入院後は杖を使って歩けるまでに回復しましたが、半年後に再び激しい痛みを訴え、寝返りも打てないほどに。受診の結果、新たな脊椎の骨折が見つかって再入院となり、回復期リハビリ病院に入院してのリハビリが始まりました。
父親は、歩けなくなったことで「俺はもうダメだ……」と弱音を口にすることが増えています。Sさんは「また元気に歩けるようになるよ! リハビリを頑張ろう!」と励ましますが、父は俯いたまま黙りこむばかり。リハビリも「今日は腰が痛くて休みたい」と休んでしまうことが多いようです。
回復期リハビリ病院で集中的にリハビリを受けられる期間には限りがあります。Sさんの父親の場合、最大2ヶ月間入院できる予定ですが、このままでは十分回復できないままで退院を迎えてしまうのではないかと、Sさんは焦りを感じていました。
「また家で一緒に暮らしたい」――その強い思いから、Sさんはつい口調が厳しくなってしまいます。「もっと頑張って! 弱気になってちゃダメ! しっかりして!!」と声を荒げると、父親は「うるさい!」と怒鳴り返し、喧嘩になることもしばしばです。
Sさんが強く励まさずにいられないのには理由がありました。実家はエレベーターのないマンションの5階です。「もし父が車椅子生活になれば、もう家には戻れない。最低でも杖で歩けるようにならないと」と考えていたからです。
退院日が迫るにつれ、Sさんは「帰宅は難しいかもしれない。もう施設しか方法がないのだろうか……」と、落ち込むようになりました。
父親のリハビリの進行状況や今後について話し合うカンファレンスの場で、Sさんは「マンションにはエレベーターがないから、今の状態では自宅復帰は無理ですよね。電動の昇降機をマンションの階段に取り付けることはできないですし」と、不安を打ち明けました。
そのとき、リハビリの専門家である作業療法士さんが口を開きました。
「福祉用具のレンタルで解決できる可能性が高いですよ。 階段昇降機もいろんなタイプがあって、車椅子に取り付けて介助者が操作するものなら使えるかもしれません。介護保険のレンタル対象になっていたはずです」
福祉用具のパンフレットで説明を受けたSさんは、施設以外の選択肢があることを初めて知りました。さらに、相談員から「お父様がどこまで回復できるかはまだ分かりませんし、不安も大きいかもしれません。でも一緒に考えていきましょう。今は介護保険の申請中ですから、利用できるサービスや回数、どんな福祉用具が使えるかは、はっきりしたことは言えません。ケアマネジャーが決まれば、どんどん具体的に進みますから」と声をかけられ、Sさんはようやく心が軽くなりました。
その日から、Sさんの焦りは次第に和らいでいきました。見舞いの際には、父親が好きな野球の話をしたり、「山登り仲間のAさんが、寂しいから早く戻ってきてって言ってたよ」と伝えたりと、リハビリを促すのではなく、父親が興味を持ちそうな話題を積極的に投げかけられるようになりました。リハビリでも、作業療法士や理学療法士が「どこの山が印象的でしたか? 私も登ってみたいです」と、話題を広げ、盛り上げてくれたそうです。
それでも父親は、「また歩けるようになるのだろうか」「家に戻れる日は来るのだろうか」と、不安を隠しきれない様子でした。そのたびに、リハビリスタッフが「退院直後に階段を上がる自信がなければ、階段の昇降を手助けする機器を使う方法もあります。退院後もリハビリを続けながら、少しずつ足腰を鍛えましょう」と声をかけてくれました。
そうしたやりとりを重ねるうちに、父親は退院後の生活に明確な目標を持つようになり、リハビリへの意欲も高まっていきました。ちょうど、脊椎圧迫骨折の痛みも和らぎはじめた頃で、前向きな姿勢を取り戻していったのです。
その後、父親は要介護3と判定され、ポータブルトイレなど在宅で過ごす環境を整えたのち、退院して自宅に戻ることができました。退院直後は車椅子の利用が必要でしたが、階段昇降機をレンタルし、デイサービスの送迎スタッフも利用方法を一緒に学んでくれました。スタッフが「小型で使いやすくて、こんなにいいものがあるんですね。勉強になります!」と感心してくれたとき、父親は嬉しそうに微笑んでいたそうです。
Sさんは「施設しかないと思い込んで、他の手段があるなんて想像もつかなかった」と振り返ります。父親自身も、多くの専門家が自分のために尽力してくれることに感激し、「俺が頑張らないと意味ないよな」と、ますますリハビリに熱心に取り組むようになりました。
退院から半年後、父親は杖を使いながらも階段を上がれるまでに回復しました。階段昇降機のレンタルは終了し、介護度も、要介護3から要介護2へと改善しました。
「介護は情報戦」と言われるように、福祉用具や介護サービス事業所に関する情報は多岐にわたります。事業所の数は増減することもあり、個人で必要な情報を把握し続けるには限界があります。
私自身も、限られた知識の中で「これは無理だ」「使えないかもしれない」と思い込み、サービスや福祉用具の利用に目が向かず、一人で悩みを抱え込んだことが何度もありました。そんな時に助けてくれたのが、ケアマネジャーや介護スタッフ、入院相談員の方からのアドバイスや情報です。
情報はパンフレットを探すだけでは得られません。人を介した「生の声」として届くときにこそ、真価を発揮すると実感しています。よく勉強されていて、介護専門職以上の情報をお持ちの家族介護者さんの中には、「専門家なのに、こんなことも知らないの!」と責める人もいます。けれども、私個人としては、お互いに情報を共有し、知識を深めながら協力できるのが理想的だと思います。
丁寧な仕事が印象的だったスタッフさんが「これは知りませんでした、助かります!」と素直に言ってくださったこともありました。専門職と家族介護者が情報を共有し合い、学び合い、協力し合うことが、介護をより良くする確かな力になるのです。
「まだ介護というほどではないけれど、いざという時に備えて情報が欲しい」「福祉用具を実際に手にとって見てみたい」
そんな時は、お住まいの都道府県名と「福祉用具センター」で検索してみてください。福祉用具の展示だけでなく、介護に関する研修や講座を開催しているところもあります。
また最近では、大型量販店などでも、杖や車椅子のほか、見守りカメラ、音声拡張機、AIロボットなど、さまざまな便利グッズが展示・紹介されるようになってきました。
たとえば、東京・品川シーサイド駅直結の「イオンスタイル品川シーサイド」1階にある「MySCUE」では、最新の福祉用具や、生活の質を高めるツールが多数展示されています。私も訪れるたびに新しい商品に出会い、情報を得る貴重な機会となっています。専任スタッフの方による商品説明やデモ体験も可能ですので、お近くにお住まいの方は、ぜひ一度足を運んでみてください。
写真:写真AC、PIXTA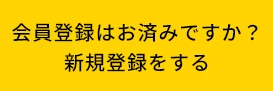

著者:橋中 今日子
介護者メンタルケア協会代表・理学療法士・公認心理師。認知症の祖母、重度身体障がいの母、知的障害の弟の3人を、働きながら21年間介護。2000件以上の介護相談に対応するほか、医療介護従事者のメンタルケアにも取り組む。