地震、台風、豪雨など、災害はある日突然やってきます。大切なのは、命を守る行動をとること、その後の生活再建に備えておくことです。知っておきたいのが、「公的支援制度」や「罹災証明書」といった、被災後に役立つ仕組みです。うまく活用すれば、避難生活や住まいの再建、金銭的な支援を受けるための支えになります。イラストレーターであり防災士でもある草野かおるさんが4コママンガとともに解説します。
阪神・淡路大震災では、建物や家具などの倒壊による窒息・圧死が、死者の大きな割合を占めました。まずは、自宅の安全性を確認することが重要です。「旧耐震基準」(1981年5月31日以前)の建物にお住まいの場合は、大地震に備えて耐震診断を受けることが大切です。旧耐震でなくても、築年数の経過や建物のゆがみが気になる場合は、専門家への相談を検討しましょう。自治体によっては、耐震診断や補強工事の補助制度、減税制度を設けているので、お住まいの自治体の窓口で相談しましょう。
また、「倒壊の危険がある」と危機感や不安感をあおり、契約を急がせる悪徳業者も存在するので用心してください。工事を依頼する際は、複数の業者から見積もりを取り、慎重に検討しましょう。
いざ、地震が起きた際の安全の場所の確保も重要です。地震発生時、自宅で安全な場所といえば、ひと昔前はトイレといわれていました。しかし、建物がゆがみ、トイレのドアが開かなくなってしまう危険性もあります。もし、トイレの使用中に地震が起きたら、ドアを開けて脱出路を確保しましょう。現在、家の中で比較的安全な場所は、構造的に頑丈に造られている場合が多い「玄関」といわれています。また、慌てて外に飛び出すと、落下物・倒壊物で大けがをする危険もあります。地震が起きたら、まず玄関のドアを開け、その場で待機するとよい場合もあります。
東日本大震災では、多くの被災者が住宅ローンを抱えたまま家を失いました。ローン返済の見通しが立たない、自宅再建のために二重ローンを抱えた、こうした人たちが自己破産に追い込まれないためにできたのが、「被災ローン減免制度」です。返済ができなくなった住宅ローンなど、債務の減額や免除を受けることができます。自己破産とは異なり、一定の財産を残すことができて、信用情報にも傷はつきません。また、原則として保証人へ支払請求が行くことはありません。利用要件があるため、全員が利用できるわけではありませんが、生活再建に大いに役立つ制度です。
大まかな申請の流れは、まず借入金額が最大の金融機関に被災ローン減免制度利用の申し出をします。金融機関から同意書が届いたら、「登録支援専門家(弁護士)」に依頼し、弁護士のサポートを受けながら、全対象債権者に債務整理の申し出を行います。債権者からの回答後、被災者が簡易裁判所に出向いて特定調停の申し立てを行い、裁判所で調停条項が確定します。このとき、必要書類のやりとりなどに若干の費用はかかるものの、弁護士への相談料金はかかりません。
そのほか、以下のような制度があります。
●被災者生活再建支援制度:住宅の損壊状況に応じて、最大300万円の個人補償が、都道府県拠出による基金から支給されます。
●災害弔慰金、災害障害見舞金:自然災害で亡くなった人の遺族、重度の障害を受けた被災者に対して支給されます。災害弔慰金は最大500万円です。
●災害援護資金:所得が一定以下の被災者に対して、震災で負傷または住居・家財に被害を受けた人に、生活再建のための資金貸付が行われます。
これらの制度は、多くの被災者の犠牲を背景に、その後の努力の結晶としてできたものといえます。いつ誰が被災するかわからない現在、いろいろな救済措置があることを覚えておき、自分が被災者となった場合には、しっかり活用しましょう。
災害に見舞われたとき、その後の生活を支えるために非常に重要な書類が「罹災証明書」です。罹災証明書とは、地震や風水害などの災害により家屋などが被害を受けた場合に、その被害の程度を証明する公的な書類です。
被災者の申請に基づき、各市区町村の職員が家屋などの被害状況を調査し、全壊、大規模半壊、半壊などの被害程度の認定を行います。この証明書は、被災者生活再建支援金の申請、仮設住宅への入居、税金や公共料金の減免、融資など、さまざまな支援を受けるために必要不可欠な書類となります。いわば、罹災証明書は、被災者支援を受けるための「パスポート」のようなものといえるでしょう。災害が発生し住宅が損壊したら、いち早く罹災証明書の発行手続きを行うことがポイントになります。
想像してください。大型台風から逃れ、避難所から自宅に戻ると、変わり果てたわが家が……。1階は浸水し、部屋の中は泥だらけ。まさに、呆然自失の状態。われに返り「早く片付けよう」と思ったときは、ちょっと待ってください。いの一番にやるべきは「被害状況を撮影すること」です。罹災証明書の申請手続きにはこの写真が必要になるのです。写真を撮らないまま片付けてしまった場合、正確な被害状況を示すことができず、認定されなかったり、軽い区分での認定となってしまったりする可能性もあります。
家の全景、屋根、室内、水回り、家電、ガレージ、庭、自動車など、あらゆる場所をいろいろな角度から撮影しましょう。浸水時には、その深さもわかるように撮影します。撮影のポイントは、被害部分が明確にわかるように複数方向から撮ること。たとえば水害では、床下浸水か床上浸水かが大きなポイントになるので、浸水した位置がわかるように撮影します。地震では壁の亀裂がどの場所にあるのか、柱の傾斜なども大きな判断材料になります。壁や天井などは、あとで見返して水もれなどを発見することもあります。目立った被害箇所だけでなく、家の内外をチェックしながらできる限り多くの箇所を撮っておきましょう。被害状況の写真は、保険金の請求時などにも必要になります。「被災したら、とりあえず写真で記録!」と覚えておくとよいでしょう。
また、被災後しばらくたって、支援対象が広がる場合もあります。復旧にかかった工事費等の領収書は保管しておきましょう。
この著者の他の記事
・いざというときのために用意しておくべきものは?【4コマ防災図鑑】で学ぶおうち避難テクニック!
・ 高齢の家族がいる家庭こそ必見!「4コマ防災図鑑」でわかる防災の備えと対策 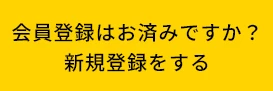

著者:草野 かおる(くさの・かおる)
防災士、イラストレーター。
PTA、自治会で16年にわたり防災活動にかかわった経験を生かし、東日本大震災の数日後にブログ配信を開始。防災についての講演会、執筆、SNS配信なども精力的に行っている。著書に『おうち避難のためのマンガ防災図鑑』(飛鳥新社)、『家族や大切な人を守る 書き込む!防災ノート』(東京ニュース通信社・講談社)など。2025年秋には、ぴあよりシニア防災の新刊発売。