杖は、転倒を防いだり歩行を助けたりする便利な歩行補助具のひとつです。ただし、正しく使わなければかえってバランスを崩してしまい、けがにつながる恐れもあります。
今回はシニアが安全に杖を使えるように、その役割と正しい使い方をわかりやすく解説します。
杖には主に次の3つの役割があります。
①バランスを安定させる
人が倒れないためには、身体の重心が足で支えている範囲内に収まっている必要があります。立っているときは両足で囲まれた面が「身体を支える土台」となり、片足立ちでグラグラするのは、この土台が小さくなってバランスが取りにくくなるためです。
杖を使うことで、支えるポイントが「足2本+杖1本」の3点になり、カメラの三脚のように安定します。支える土台が広がるため、少し重心がズレても倒れにくくなるのです。
②足への負担を軽くする
人が立っているとき、体重はすべて両足で支えています。しかし、痛みや筋力の低下などにより足に不安がある場合、無理に体重をかけると力を発揮できず転倒する恐れがあります。
杖を使えば体重の一部を預けられるため、不自由な足への負担を軽減し、安全な歩行が可能になるのです。
③前に進む力と止まる力を助ける
杖は、歩くときに身体を前に押し出す力を補い、途中で止まりたいときにはブレーキの役割を果たします。足の筋力が低下して、地面をしっかり蹴るのが難しい場合でも、杖で身体を押し出すようにすればスムーズな前進が可能です。
さらに、止まりたいときには杖をつっかえ棒のように使って身体を支えることで、減速し、転倒を防ぐこともできます。
ここからは、実際に杖を使って歩行する際のポイントを紹介します。①~④の順に確認しながら進めてください。
①長さを調整する
杖は、使う方の身体に合った長さで使うことが大前提です。長すぎたり短すぎたりすると、姿勢が崩れたり、うまく体重をかけられなかったりして、かえって転倒のリスクを高めてしまいます。
◾️長さ調整の目安(以下のいずれかの方法を参考)
・気を付けの姿勢での、床から手首までの長さ
・床から太もも付け根の外側にある骨の出っ張りまでの長さ
・足の小指から外側15~20cmの位置に杖を突き、握ったときに肘が30°曲がる長さ
・身長の半分+2~3cm
②悪い足の反対の手で持つ
杖は悪い足(※1)の反対の手で持つことで、体重が良い足(※2)にのりやすくなり、痛みや筋力低下のある足への負担を軽減できます。
イラスト:イラストAC
たとえば、左足に骨折や関節痛、筋力低下、麻痺などがある場合は、右手で持つのが正しい使い方です。
※1:痛み、麻痺、筋力低下などの症状がある足
※2:良い足:痛みや運動への支障がなく、体重をかけても問題のない足
③3ステップ歩行から始める
初めて杖を使う方には、「3ステップ歩行(3動作歩行)」がおすすめです。ゆっくりではありますが、安定感があり安全に歩ける方法です。
〈手順〉
1.杖を出す
2.悪い足を出す
3.良い足を出す
この歩き方では常に2点で身体を支えられるため、まだ杖の使用に慣れていない方に適しています。特に、半身に麻痺がある方や、しっかり身体が安定してから次の一歩を出したいという方にはこの方法が安心です。はじめは動きがぎこちない場合もあるので、ケアラーは近くで見守ってください。
④慣れたら「2ステップ」で歩く
杖の使い方に慣れてきたら、「2ステップ歩行(2動作歩行)」にチャレンジしましょう。
〈手順〉
1.杖と悪い足を同時に出す
2.良い足を出す
この歩き方は、3ステップよりもスムーズで歩行スピードも上がるため、より自然な動作での歩行が可能です。
ただし、誤って「杖と良い足」を同時に出してしまうと「悪い足だけ」に体重がかかり、転倒しやすくなります。また、正しい手順でも、①の動作で身体が前に進み始めるため、つまずいた際に勢いで転倒するリスクもあります。
そのため、まずは3ステップ歩行で感覚を十分に身に付けてから、2ステップに移行することが重要です。

階段の昇り降りでは、平地とは異なる使い方をします。手順を誤ると、痛みの悪化や転倒・転落につながるリスクがあるため、「昇るとき」と「降りるとき」それぞれの動きを押さえておきましょう。
〈階段の昇り降りの手順〉
階段を昇るとき
1.杖を段に置く
2.良い足を上げる
3.悪い足を上げる
階段を降りるとき
1.杖を一段下ろす
2.悪い足を下ろす
3.良い足を下ろす
この順番になる理由は、「体重を支えるのは必ず良い足でなければならない」からです。
■ポイント①階段を昇るときは身体を持ち上げる動作になる
階段を昇るときには、上の段へと身体を持ち上げる必要があります。このとき先に悪い足をのせてしまうと、その足で持ち上げなければなりません。
そのため、まずは杖をのせ、次にしっかり身体を支えられる良い足をのせたうえで、悪い足をのせましょう。
■ポイント②階段を降りるときはゆっくりと身体を下ろす動作になる
階段を降りるときは、身体を支えながら、ブレーキをかけるようにして足を下ろす動きをとります。もし先に良い足を下ろしてしまうと、上に残った悪い足に体重がかかり、非常に不安定になります。
そのため、まずは杖を下ろし、次に悪い足を下ろしたうえで良い足を下ろしましょう。
■覚え方のコツ
理屈で覚えるのが難しいという方は「行きはよいよい、帰りはこわい」で覚えましょう。
・上り(行き)は「良い足から」
・下り(帰り)は「悪い足から」
このフレーズを思い出せば、迷わず正しい順番で動けますので、初めは近くで声をかけてサポートしてください。
杖は歩行を助ける便利な補助具ですが、使い方を間違えるとかえって転倒のリスクが高まります。
正しい方法で使えば、自信をもって歩けるようになり、より活動的に過ごすことが可能になります。
長さ調整や持ち方、歩き方の手順を正しく理解し、安全に杖を活用しましょう。
写真:PIXTA、写真AC
監修:中谷ミホ
関連記事
・理学療法士が解説!杖(ステッキ)の機能や種類・選び方のポイント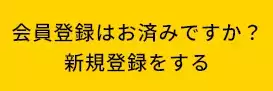

著者:鈴木康峻
2008年理学療法士免許取得。長野県の介護老人保健施設にて入所・通所・訪問リハビリに携わる。
リハビリテーション業務の傍ら、介護認定調査員・介護認定審査員・自立支援型個別地域ケア会議の委員なども経験。
医療・介護の現場で働きながら得られる一次情報を強みに、読者の悩みに寄り添った執筆をしている。
得意分野:介護保険制度・認知症やフレイルといった高齢者の疾患・リハビリテーションなど
保有資格:理学療法士・ケアマネジャー・福祉住環境コーディネーター2級