「父が祖父から引き継いだ田舎の土地」の維持管理をするためには思った以上にお金が必要でした。その出費がもったいないと思った私は父親に土地を売る提案をし、何とか受け入れてもらうことに。そこで役に立ったのが、以前行っていた「家族信託」でした。
「お父さんは、先祖から引き継いだ田舎の土地を持っているよねー」くらいのざっくりした情報しか知らなかった家族の財産。その管理のアレコレが、施設に入所している父に代わって対応していた母が亡くなったことで、自動的に一人娘の私に降りかかってきました。
そもそも、その田舎の土地の詳細な場所や、どのくらいの広さなのかもわからないうちに、固定資産税、防災のための草刈代+草刈の音へのクレーム対応代(約4万円! だが、土地の広さ的に妥当な金額だった)と、これまで知らなかったことがわかってきました。
父の父(私の祖父)はその田舎の出身ですが、父は生まれも育ちも都会で、その土地で暮らす気などはありませんでしたが、「先祖代々の土地だから…」という理由で、祖父亡き後、誰も住むことのない土地を何十年も管理し続けていたのです。
母は言うことができなかったかもしれない「その土地って、本当に必要なの?」という疑問を、私は父に突き付けました。そして、認知症の父に「今は母さんや父さんのこれまでの貯えで、この施設にいることができるけど、それもいつまで続くか…」という切実な真実も正直に話しました。「認知症の人になんてことを!」と思う方がいるかもしれませんが、長い間自営業をしていた父は、認知症になってもお金に関することは意外にクリアなままのです。
ここで、親との「ケア活」がうまくできなかった我が家の唯一の救いが、父の認知症が軽度だったころに私が「家族信託」を利用していたことです。通常、親が認知症になると、認知症になった人の財産は凍結されてしまうことがあり、たとえ配偶者や子どもであってもそれらを自由に動かすことができなくなります。日本の法律では個人の財産は思った以上にしっかり守られています。そのために、個人の財産を守るための次のような制度があるのです。
・成年後見制度
知的障害・精神障害・認知症などによってひとりで物事を決めることに不安があったり心配な人が いろいろな契約や手続をしたりする際に、家族や、同じ地域に暮らすさまざまな人によって本人の思いを分かち合い、いっしょに考え、お手伝いする制度。
成年後見制度にはさらに、「任意後見制度」「法定後見制度」があります。
・任意後見制度
ひとりで決められるうちに、認知症になったり障害を持ったりした場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ人(任意後見人)に、将来的に本人の代理人となってしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度。
・法定後見制度
本人がひとりで決めることが困難になったとき、家庭裁判所によって、本人の代理人となる成年後見人等が選ばれる制度。本人の状態に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています。
(参考:厚生労働省「その人らしい暮らしをいっしょにつくる 成年後見制度」)
・家族信託
委託者(親)から受託者(子どもや家族等、信頼できる人)に託した財産を、家族信託契約によって託された人が親に代わって管理・運用できます。
成年後見制度は個人の財産を守る大切な制度ですが、家族にとってはデメリットとなりうるケースがあることも親との「ケア活」のための知識として知っておきたいところです。
たとえば、「法定後見制度」では、財産を所有する人のお金を使うことや土地の売買をするためには家庭裁判所の関与があり、事前に家裁の了承を得る必要があります。
これに対し、我が家が利用した「家族信託」は、委託者(親)が元気なうちに話し合い、受託者(子や家族など)に「私の財産のうち、この部分は君に管理を任せるよ」という契約を公正証書等で交わします。我が家を例にすると、父(委託者)の土地を売るための契約については私(受託者)に管理・処分権限を移しているため、私が契約の当事者となり、土地を売ることができます。売却の対価として得たお金は、委託者と受託者の名前が記載された信託口座(信託の専用口座)で、委託者の財産として管理していきます。
ただし、この家族信託にもデメリットがあり、委託者に意思判断能力があるときでないと、家族信託契約を結ぶことができません。だからこそ、親が元気なうちに親との「ケア活」をすることが望ましいのです。
以降は我が家の「田舎の土地」問題を例に挙げてみます。
「法定後見制度」で「田舎の土地を売りたい」と希望しても、「まだ親の貯金が残っているうちは必要ない」と家庭裁判所に判断されてしまうと、私がその土地を相続するまで土地に関する管理費用を払い続けなければなりません。
「家族信託」ならば、「親の貯金が少しになってきて心配」だと思った私が(受託者:子どもや家族)が、父の施設費用の足しにするために父(委託者:親)に代わって、土地の売買などを行うことができるのです。
【この話、ちょっと難しいので専門家(司法書士 村山先生)が解説!】
■親の財産に子が対応するには…
「ケア活1」に登場した「代理人カード」「指定代理人制度(予約型代理人サービス)」以外に考えられるのは、
〈親に意思判断能力あり〉
・任意後見契約(親が元気なうちに契約し、判断力が低下したら裁判所が監督人を選任してスタート)
・家族信託(信託財産を受託者に移して管理する仕組み。信託専用口座を作って管理する)
〈親に意思判断能力なし〉
・法定後見制度(親の判断能力がすでに失われている場合に、家庭裁判所に申立てる)
などの方法が代表的です。
→つまり、親との「ケア活」をまったくしていなければ、「家庭裁判所で法定後見制度を利用する」流れになる。
家族信託にかかる費用は以下の通り。
■専門家へ支払う報酬部分(30~100万円など 資産に応じて)
■不動産の名義変更にかかる実費(登録免許税、公正証書にした場合の公証役場費用)
ちなみに、我が家も数十万円の費用がかかりました。

■まったく親との「ケア活」をしていない場合の対応
・すでに認知症が進んでいる場合、代理人カードも作れず、家族信託もできないため、法定後見人選任を家庭裁判所に申立てるしかない。
・後見人が選任されると、銀行は後見人を「本人の代理人」として認め、本人口座から支払いが可能になる。
以前、家族信託契約をしているといえども、娘と父の「ケア活」を施設で行い(というか、これからも無駄に払い続ける必要のある土地の管理費用と、今後の施設の費用問題を切実に訴え続けた)、父は翌日には忘れているかもしれませんが、改めて「田舎の土地を売ってもいい」という決断をしてくれました。しかし、この「田舎の土地」には、さらなる問題があったのです(涙)。
※ブライバシー保護の観点から、一部フィクションが含まれています。
イラスト:日野あかね
写真(トップ):PIXTA
監修、アドバイス:村山澄江
写真:PIXTA
【監修者プロフィール】
村山澄江(むらやま・すみえ)…民事信託・成年後見の専門家、司法書士。
生前対策の対応実績1500件以上。民事信託と成年後見の専門家として全国でセミナー等も行っている。日本経済新聞・朝日新聞等、取材記事多数。著書に、「今日から成年後見人になりました(自由国民社)」「認知症に備える(自由国民社)」がある。
この著者の前の記事
・こんなことも「ケア活」なのです!? 財産整理編①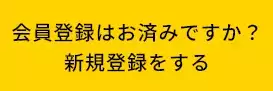

著者:岡崎 杏里
大学卒業後、編集プロダクション、出版社に勤務。23歳のときに若年性認知症になった父親の介護と、その3年後に卵巣がんになった母親の看病をひとり娘として背負うことに。宣伝会議主催の「編集・ライター講座」の卒業制作(父親の介護に関わる人々へのインタビューなど)が優秀賞を受賞。『笑う介護。』の出版を機に、2007年より介護ライター&介護エッセイストとして、介護に関する記事やエッセイの執筆などを行っている。著書に『みんなの認知症』(ともに、成美堂出版)、『わんこも介護』(朝日新聞出版)などがある。2013年に長男を出産し、ダブルケアラー(介護と育児など複数のケアをする人)となった。訪問介護員2級養成研修課程修了(ホームヘルパー2級)
https://anriokazaki.net/