使う予定もないのにそれなりに管理費用がかかることがわかった「父が祖父から引き継いだ田舎の土地」。なんとかその売却を決め、知り合いの不動産屋さんに仲介をお願いする過程で、これまた想定外の費用と時間が掛かることになってしまい……。
いよいよ、父が祖父から受け継いだ何十年間も活用されることのなかった「田舎の土地」を売却することになりました。不動産に関して、右も左もわからない私は、知り合いの不動産屋さんに売却の仲介をお願いすることに。父の田舎にある不動産屋さんにお願いすれば、現地まで行く担当者の交通費代などを抑えることができるかもしれませんが、そもそも知らない土地の不動産屋さんを探すのも大変だと考え、以前から交流のある、話しやすい不動産屋さんに仲介をお願いすることにしたのです。
ある日、その不動産屋さんから1本の電話がありました。なんでも「岡崎さんのお父様の田舎の土地ですが、ずっと活用されていなかったので、お隣との境界線がわかりづらくなっておりまして……」と言うのです。
不動産に関する知識のない私は「それではどうなるんですか?」と質問すると、「境界線の測量をし直す必要があるため、さらに時間とお金が掛かってしまいます」と、なぜか済まなさそうに話すのです。
「ぬー。一筋縄ではいかない、田舎の土地ぃー」と叫びそうになるのをグッと堪えて(早くから財産管理の「ケア活」をしなかった父と私がいけなのだけれど)、不動産屋さんに私がすべきことを教えてもらいました。

なかなかスムーズに売却にまで至らない田舎の土地ですが、このまま保有していても、税金やら草刈代やら苦情対応やらで、費用ばかりが嵩んでいきます。父の施設代の足しにするためにも一刻も早く売却したい私は、不動産屋さんからアドバイスを受けて測量をお願いすることにしました。こうした経緯で、想定外の手間とお金が必要となったわけです。
まず、不動産屋さんが田舎の土地の近くの土地家屋調査士さんを探し、測量の段取りをしてくれました。土地家屋調査士さんとは、私が遠方で現地へ足を運ぶことがなかなか難しいため、主に電話やメールでやり取りをすることに(通信手段が発達した時代で良かった)。ほかにも、資料を取り寄せるなど追加の手間が増え、「なんで私が……」と行き場のない怒りを深呼吸で鎮める日々を送りました。
亡くなった母親に届いた“草刈り業者からの手紙”から始まった「父が所有する田舎の土地」問題。家族信託で受託者となった私が父に代わって買い手との手続きなどを行い、幸いにもなんとか買い手が見つかって、無事に売却(整理)することができました。ちなみに、この時点でも司法書士さんに売却のための書類や手続きのお願いをしました。
ここまでに要した時間は、あの手紙を受け取ってから約8ヶ月。売却しづらい土地だったということで、この期間が長いのか短いのか、私には正直、わかりません。しかしながら、仕事や育児をしながらだったために、私にとっては思った以上に負担となりました。最後に忘れてはいけないのが、土地を売却して得たお金は父の収入となり、確定申告が必要となるため、その手続きをしてやっと任務完了となります。余談ですが、売却で得たお金は希望額よりも低かったのですが、不動産屋さんへの仲介料などの諸々に掛かった費用を差し引いても、多少は父の施設代の足しになりました。
「田舎の土地」は幸いにも建物が建てられていなかったため、建物解体の手配や費用が掛からなかったという点は幸いでした。そう思えたのは、実はこのあと、より大変な実家の片付け(というか、空き家になった実家の家財道具の処分)と家屋の解体などがあったためでして…(このあたりのお話も、また、いつか!)。
空き家に関しては、条件はありますが解体のための補助金や売却で得た収入に関する税金の一部が控除されるという制度があります。つまり、親の体力があるうちなど早くから動いておければ、親自らがいろいろと調べて動くことができますし、経済的にも大きなメリットがあるのです。そういった点から考えても親との財産管理に関する「ケア活」は、非常に重要となります。
そんなこんなで親の財産整理で紆余曲折の経験をしたからこそ、脅しでもなんでもなく素直にお伝えしたいのですが、介護だけでなく、親に何かがあった場合、財産整理のために時間やお金がそれなりに掛かります。本当に大切なことだからちょっとしつこく繰り返しますが、可能であれば親が元気なうちから親と一緒にさまざまな「ケア活」ができれば、親子ともども負担が少なくなるのではないでしょうか。どうか、読者の皆さんが、私のように行き場のない怒りを深呼吸で鎮める日々を過ごしませんように。
【監修の村山先生からの「ケア活」アドバイス!】
岡崎さんが利用した家族信託は、親が認知症になった場合の財産整理の対策として非常に有効です。ただし、地目が「田」や「畑」となっている農地の場合は、農業委員会の許可等がないと家族信託ができないため、要注意です。手遅れにならないように、親が元気なうちに祖父母から継いだ土地がないかどうか、一緒に確認しておくといいでしょう。
※ブライバシー保護の観点から、一部フィクションが含まれています。
イラスト:日野あかね
写真(トップ):PIXTA
監修、アドバイス:村山澄江
【監修者プロフィール】
村山澄江(むらやま・すみえ)…民事信託・成年後見の専門家、司法書士、認知症サポーター。生前対策の対応実績1500件以上。日経新聞等取材多数。民事信託と成年後見の専門家として全国でセミナー等も行っている。著書に『今日から成年認になりました』『認知症に備える』いずれも自由国民社。
この著者の前の記事
・こんなことも「ケア活」なんです!? 財産整理編①
・こんなことも「ケア活」なんです!? 財産整理編②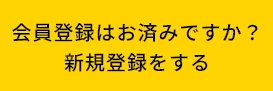

著者:岡崎 杏里
大学卒業後、編集プロダクション、出版社に勤務。23歳のときに若年性認知症になった父親の介護と、その3年後に卵巣がんになった母親の看病をひとり娘として背負うことに。宣伝会議主催の「編集・ライター講座」の卒業制作(父親の介護に関わる人々へのインタビューなど)が優秀賞を受賞。『笑う介護。』の出版を機に、2007年より介護ライター&介護エッセイストとして、介護に関する記事やエッセイの執筆などを行っている。著書に『みんなの認知症』(ともに、成美堂出版)、『わんこも介護』(朝日新聞出版)などがある。2013年に長男を出産し、ダブルケアラー(介護と育児など複数のケアをする人)となった。訪問介護員2級養成研修課程修了(ホームヘルパー2級)
https://anriokazaki.net/