家族の突然の病気やケガによって介護トラブルに直面するパニック期、介護保険などの制度を申請して住まいを整える環境調整期を経て、実際の介護生活が始まるのが「生活期」です。この記事では、介護生活で起きやすいトラブルと、負担を軽減するための対策について、介護者メンタルケア協会代表橋中今日子が解説いたします。
前回ご紹介した環境調整期を経て、実際の介護生活がスタートする生活期は、介護者の疲れがピークに達する時期です。本来、自分自身が休むべき時期なのですが、休息を取る間もなく、24時間365日にわたる介護へと突入していきます。
仕事をしている人であれば「これまでの遅れを取り戻さないと!」と意気込む時期でもあります。しかし、心身はもう限界を迎えていることが多いのです。私自身も「家族が退院できた、さあ仕事に集中しよう」と思った途端、自分が動けなくなるという経験を何度もしています。
介護で直面するトラブルは、要介護者の状態の変化だけではありません。介護者自身の疲れや体調不良も介護トラブルに含まれるのです。
体調を崩す介護者の中には、「今はトラブルが起きていないのに」、「こんなことぐらいで疲れるなんて」、「もっとしっかりしなきゃ」と、自分を叱咤激励する方が多くいます。しかし、生活期に体調を崩すのは、自己管理ができていないからではありません。
生活期に直面する負担は、実はパニック期、環境調整期から続いている身体的な負担、時間的な制約、精神的な疲れが表れているだけです。そのため、ここで自分を奮い立たせてさらに頑張ろうとするのは、利息の高い借金をするようなものです。
生活期は、介護に時間は取られるものの、要介護者の状態は比較的落ち着いていることが多いため、介護者は、この時期にご自身の休息時間を意識して取る必要があります。
生活期に介護者に掛かりやすい負担を、細かく見てみましょう。
精神的な負担
・いつも時間に追われ、介護漬けの毎日。長期化する介護、見通しの立たない不安で「いつまでこんな状況が続くの?」と、自分の人生を犠牲にしている感覚がつきまとう
・周囲の人に介護の大変さが伝わらず、理解されない孤独感
・仕事をしながら介護をしている場合は「周囲に迷惑をかけている」と、常に負い目を感じる
・要介護者が、病気や障害、老いと向き合う悲しみ、嘆き、不安感を暴言という形で吐き出すこともあり、自宅が休養・息抜きの場として機能しない
身体的な負担
・慢性的な睡眠不足
・身体介護の負担による腰痛、肩こり、ストレスを原因とした冷え性などの身体症状の発症
・介護者自身が通院するための時間を確保できず、体調不良時でも我慢してしまう
時間的な負担
・「名もなき介護」と呼ばれる身体介護以外のさまざまな生活支援に時間が取られ、介護者自身の余暇がなくなる
・要介護者に常に見守りが必要な場合は、仕事や買い物の際に家族間で調整が必要
対人関係の負担
・要介護者の理不尽な言動に苦しむ。ケアマネジャーや介護スタッフ、たまに来る家族や親族には愛想が良い要介護者の場合は、「何が大変なの?」と、病状の進行度合や介護負担の認識にズレが生じる
・日々の細々とした介護負担は、体験したことのない人には理解しにくいため、職場の人間関係に軋轢が発生する
経済的な負担
・ 介護費用
・ショートステイ(短期間入所サービス)利用時の費用
・おむつや尿パット、お尻拭きなどの消耗品の費用
・食べやすい食材や加工品の購入費用
・通院時の移動
など
40代会社員男性Cさんは、妻(40代)、小学生の子供二人と暮らしています。 Cさんからの相談は、当初「トイレ介助が楽になる福祉用具はありませんか?」というものでした。
私が相談を受ける時の鉄則は、「見かけの問題の背景にある、真の問題を探る」ことです。この場合でも、トイレ介助が楽になる方法をいきなりお伝えすることが、真の問題解決につながるとは限り ません。そこで、Cさんが相談に至るまでの経緯をお伺いしました。
Cさんは、もともと北海道出身で、現在は都内に在住しています。そして、長男が誕生したタイミングで、父親が脳出血で急死しました。ひざを痛めていた母親は、実家で一人暮らしを続けることが難しくなったため、その後Cさんは母親をすぐに東京に呼び寄せ同居を開始しました。妻の協力を得ながらの在宅介護は8年に及び、その間に母親は車椅子生活になりました。
3ヶ月前、母親が脊柱圧迫骨折で入院し(パニック期)、要介護度は2から3へ。リハビリを受けて退院したものの、ベッドから車椅子への移動や、トイレでのズボンの上げ下ろしにも介助が必要になりました(環境調整期)。リハビリを兼ねたデイサービスに週5回通っているものの、ショートステイは本人が嫌がるので利用していません。
Cさん自身は、大したことをしているつもりはなかったのですが、 朝の慌ただしい時間帯や深夜にトイレ介助が必要になってきました。母親はポータブルトイレの利用を拒むため、自宅のトイレまで毎回時間をかけて移動させなくてはいけません。就寝中に毎夜たたき起こされるため、介助に手間取り失敗することも多く、その度に着替えの介助も必要になりました。
「トイレ介助を楽にしたい」という相談に至るまでには 、このような経緯があったのです。
私は、Cさんの状況に福祉用具だけで対応するのは難しいと判断し、夜の介助回数を減らすためショートステイの利用を提案しました。しかし、Cさんは「嫌がる母親に申し訳ない」と躊躇していました。
それから1ヶ月ほど経ったころ、Cさんは仕事でミスを連発するようになりました。そしてある日、車の運転時に判断が遅れ、あわや事故を起こすところでした 。ここでようやく疲れを自覚したCさんは、母親にショートステイの利用を再び切り出してみたのです。母親は、渋々ではあるものの「あんたのためならいいよ」と受け入れて くれ、2週間に1度、3泊4日のショートステイの利用が実現しました。
Cさんは、ショートステイ利用時は気兼ねなく残業ができるようになったほか、夜も起こされずにぐっすり眠れるようになりました。睡眠が取れるようになったことで、仕事のミスも減ったそうです。
嫌がっていた母親の様子にも変化が表れました。ショートステイ先に馴染みのスタッフができたことで、「この日はショートステイね」と自分のカレンダーに書き込むほど習慣化しているそうです。
Cさんは、「自分のためにショートステイを利用させるなんて申し訳ないと思っていました。でも、イライラして母親に八つ当たりすることもあったんです。自分でも体力の限界だということは頭のどこかで自覚していたのですが、認めたくなくて、大丈夫だと言い聞かせていたような気がします。誰かに指摘してもらうって大事ですね」と話してくれました。
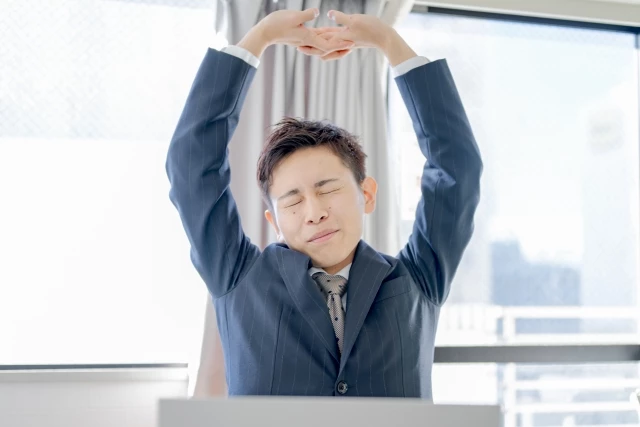
生活期のポイントは、何よりも「介護者の休息時間の確保」です。介護は長期戦。愛情や思いやり、責任感などの精神力や気力だけでは乗り切れません。物理的に休む時間を作らなければ、必ず介護者が破綻してしまいます。そのため、デイサービスやショートステイを上手く活用し、介護者が休息できる時間や、仕事や趣味に没頭できる時間を確保することをお勧めします。
私も、祖母や母親がデイサービスやショートステイを利用するタイミングで、普段できない残業をこなしたり、有休を使って起こされずに眠れる日を作ったり、録り溜めていたドラマを深夜まで観たり、外食をする時間を確保するようにしていました。実際に、この「自分ファースト」の時間を意識的に作るようになってからは、体調を崩すことも劇的に減りました。
要介護者のトラブルだけではなく、自分自身が休息するため、ホッと一息つくために有休を使うことに対し、罪悪感を持つ必要はありません。
生活期は、介護者自身が休息する時間を意識してつくるようにしましょう。

この著者の関連記事
・親が倒れた…! 次々と起こるトラブルに対して混乱しないために知っておきたい「介護の4つの時期」とは?
・介護の4つの時期|パニック期
・介護の4つの時期|環境調整期

著者:橋中 今日子
介護者メンタルケア協会代表・理学療法士・公認心理師。認知症の祖母、重度身体障がいの母、知的障害の弟の3人を、働きながら21年間介護。2000件以上の介護相談に対応するほか、医療介護従事者のメンタルケアにも取り組む。