今のシニア世代の中には、「介護は家族がするべき」「他所様の手を借りたくない」「迷惑をかけるのは申し訳ない」と、介護保険サービスの利用をためらうケースがあります。けれども、その思いの強さによって、結果として本人や家族が、より苦しい状況に追い込まれてしまうことがあります。
関東在住のBさん(50代・会社員)は、妻と二人暮らし。一方、Bさんの両親(ともに80代)は東北地方で二人暮らしをしています。父親は数年前から物忘れが目立つようになり、アルツハイマー型認知症と診断されました。最近ではトイレの失敗が増えているようです。
母親一人では対応が難しい状況になるだろうとBさんは予想していますが、母親は「介護だなんて、お父さんが傷ついてしまう」と、介護保険の申請には後ろ向きでした。Bさんは、その気持ちを尊重して、あえて口出しをしてきませんでした。ところが、ある猛暑の日、散歩に出た父親は自宅に戻れず、道にうずくまっていたところを警察に保護されたのです。
「いつか取り返しのつかないことになる」と感じたBさんは、両親が安心して過ごせる環境を整えるために、介護保険の申請をしてサービスを利用しようと母親の説得を試みました。しかし母親は「私がちゃんと見るから」と、耳を貸そうとしません。やむを得ず、Bさんは毎週のように東北の実家へ通い、両親の様子を見守っています。
ここで、思いもよらないことが起きました。母親が転倒して骨折し、緊急入院したのです。
Bさんは、母親の入院手続きや一人残された父親の世話のために、10日ほど仕事を休みました。入院先の主治医と医療ソーシャルワーカーからは「手術後はリハビリが必要です。入院期間は3~6ヶ月ほどを見ておいてください」と説明を受けました。
次に考えねばならないのは、自宅に一人残された父親の暮らしをどうするかです。Bさんは実家近くの地域包括支援センターに相談。父親の様子を確認した職員から「介護保険の申請を行い、緊急ショートステイを利用しましょう」と提案され、すぐに手続きを行いました。運よく、近くの介護老人保健施設に空きが見つかり、父親の受け入れが決まりました。
しかし父親は、突然の環境の変化に馴染めないのか「家に帰る!」と声を荒げ、食事や入浴を拒みます。施設の相談員からは、「スタッフや他の利用者に影響が及ぶ行動が続く場合は、ショートステイの継続が難しくなることもあります」と言われてしまいました。
母親の入院に父親の混乱、いつまでも休めるわけではない仕事。自分一人の力では無理だと、Bさんは頭を抱えてしまいました。
介護では、思いがけないことが次々に起こります。要介護者の容態の変化だけでなく、家族の不調や災害など、どうしようもない出来事が重なることだってあります。Bさんのケースのように、家族だけでは手に負えない状況が突然起きるのは、珍しいことではないのです。
Bさんの父親の場合、長年、妻以外との関わりをほとんど持たずに過ごしてきました。その妻が突然不在になり、知らない場所で見知らぬ人に囲まれる――。混乱して大声を出したり、介護を拒んだりするような言動があったとしても無理はないでしょう。人として自然な反応です。
例えば、数時間程度のデイサービスに通うだけでも、慣れるには時間がかかります。ましてや宿泊を伴うショートステイとなると、ハードルはぐんと高くなるものです。もちろん、デイサービスの経験があったからといって、ショートステイがスムーズにいくとは限りません。それでも、他者からケアを受けた経験があるかないかで、混乱の度合いや慣れるまでの時間は大きく違ってくるものです。
余裕がある段階で、介護保険サービスや家族以外との関わりを少しずつ試しておくと、心の備えになります。一時的には負担になる場合もありますが、「慣れる力」を育てておくことが、のちの安心につながるのです。
最初の1週間ほどは、連日のように施設から「お父様が暴れています」との連絡が入り、そのたびに足を運んだBさんでしたが、父親は次第に落ち着きを取り戻し、ショートステイを継続できそうな見通しが立ちました。
4ヶ月後、リハビリを受けて杖を使って歩けるまでに回復した母親も、無事に退院。母親が自宅での生活に慣れた頃、父親も自宅へ戻り、現在はデイサービスに週4回通っています。
これまで、父親の介護保険の申請やサービス利用を強く拒んでいた母親でしたが、入院とリハビリで自分がケアを受ける経験をしたことで気持ちが変わったようです。「お父さんもデイサービスで体を動かしてもらわないとね!」と、サービス利用に前向きになり、Bさんの訪問も、月1回ほどで済むようになりました。
介護保険サービスの利用を一度拒まれると「自分が我慢すればいいのだから」と、無理を重ねる家族がいます。
けれども、初回は「もう行かない!」と嫌がっていた人でも、2回目には表情が和らいだり、少し時間をおいて再び利用を始めたり、別の施設に通うようになったりすることがあります。利用経験を重ねるうちにサービスへの安心感が生まれ、継続利用へとつながっていくケースは意外と多いものです。支援者は、そんな変化が起きることを見越しています。
サービスを利用したいのに、要介護者が拒む、あるいは他の家族が拒むなど悩んでいる方は、ケアマネジャーや地域包括支援センターに繰り返し相談してみてください。劇的な変化がすぐに起きるわけではありませんが、支援者とつながりながら、小さな安心を積み重ねていくと、道は少しずつひらけていくでしょう。
写真:写真AC、PIXTA
この著者のこれまでの記事
・「負けたくない!」が教えてくれた、本当の気持ち――心を守る介護の知恵
・情報が介護を変える──福祉用具と専門家の力で父娘がつかんだ在宅復帰
・私だけが損してる? 介護にまつわるきょうだいのモヤモヤに向き合う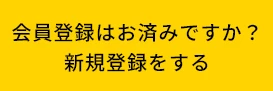

著者:橋中 今日子
介護者メンタルケア協会代表・理学療法士・公認心理師。認知症の祖母、重度身体障がいの母、知的障害の弟の3人を、働きながら21年間介護。2000件以上の介護相談に対応するほか、医療介護従事者のメンタルケアにも取り組む。