介護は、家族だけで、ましてやひとりで抱えきれるものではありません。けれども、きょうだいや親族がいても、支えてくれる人は誰もいない――そんな「孤独な介護」に直面している方は少なくありません。
ときには、手を差し伸べてもらえないばかりか、理不尽な批判を浴びせられることすらあります。「どうして私だけが……」という思いは、声に出せないまま、じわじわと心に積もっていくものです。
本当は助けてほしいのに、うまく頼れない。頼んでも断られる。責められる。それでも介護は待ってくれない。
そんな状況に置かれている方にこそ、知っておいてほしい視点があります。怒りや諦めに飲み込まれてしまう前に、自分自身の心と暮らしを守るためにできることがあるのです。
関西在住のMさん(40代女性・パートタイマー)は、夫と中学生の息子との3人暮らしです。Mさんの両親(70代)は中部地方で2人暮らしをしています。
両親は、認知症の父親を母親が介護する老老介護世帯です。昨年の6月、両親ともに熱中症で緊急入院をしました。この1年ほど、週末は片道3時間以上かけて実家に通っているため、夫や息子とはほとんど一緒に過ごせていません。暑い日が続くようになってからは、毎日電話で安否確認もしています。
Mさんには実家の近くに住んでいる3つ違いの兄がいます。しかし、義姉と両親は以前トラブルがあり、兄夫婦は実家から足が遠のいています。
先日Mさんは、週末に息子のクラブ活動の試合があるため、兄に「実家に顔を出して様子を見てきてほしい。できれば、熱中症対策のスポーツドリンクの在庫を確認してくれないか」とお願いをしてみました。
しかし兄からは「忙しい」と断られてしまいます。さらに、「お前が手取り足取り世話をするから、親父たちが依存的になるんだ」と、Mさんの対応を責めるような言葉をかけられました。
Mさんはこれまで、両親と兄夫婦との間には、本人たちにしかわからない事情があるのだろうからと、立ち入らないようにしていました。しかし、兄の家を建てる際には両親が多額の援助をしたことを知っています。Mさんは両親から経済的な援助を受けたことがなく、お金の話をすることに抵抗があります。母親からの申し出がないため、実家に通う交通費も買い物の費用も、当然のようにMさんが支払ってきました。最近では、パート収入のほとんどを実家のために使っている状況です。夫は、実家への出費について不満を口にすることはありませんが、子どもの教育費など今後の生活への影響についての不安は抱えていました。
兄夫婦の家から実家までは、車で10分もかかりません。毎週末片道3時間以上かけて実家に通っているMさんとしては、「私は損してばっかりなのに、批判されるなんて!」と、納得がいきません。
Mさんのように、家族の介護のために犠牲を払っているのに、全く介護に関わらないどころか、批判だけしてくる親族や家族との関係に悩んでいる人はとても多いです。
このようなご相談の際、私が必ずお伝えしているのは「相手の言葉通りに受け取らなくていい」ということです。介護をしている家族への言動の背景には、本人も気がついていない不安や恐れの気持ちが隠れていることが多く、自分の心を守るための言動である可能性が高いからです。
理不尽な言動や過剰な批判は、以下の5つの要因が複雑に絡み合って起きていることがあります。責めているように見えても、その深層には「理解されたい」「見捨てられたくない」「無力な自分を認めたくない」といった思いが隠れていることがあります。そうした心の声には、本人すら気づいていないことが多いのです。
【否定的な言動の5つの要因】
1. 自己防衛
介護に関わっていない後ろめたさや劣等感から、相手を批判して自分を保とうとする。否定的な言動の裏には、強い自己否定や恥の感情が潜んでいることも。
2. 認知(物事の捉え方)や価値観の偏り
物事を「正しいか間違いか」で決めつけ、自分は正しい側にいると思い込むことで安心しようとする傾向。他人の欠点ばかりに目が向き、自分の課題から目をそらしていることもある。
3. 自己肯定感の低さと優越感の追求
自己肯定感が低く、劣等感を隠すために他者のミスや弱さに注目し、自分の方が上だと感じることで一時的に自尊心を保とうとする。
4. 親との関係における未解決の感情の投影
幼少期に感じた親へのわだかまりや承認欲求が心に残っている。本来は親に向かうはずの怒りや悲しみが、無意識に介護に関わるきょうだいに対して向く。
5. 期待に応えられない不安
子どもの頃から、「長男(女)だから、一人っ子だから、〇〇すべき」というように言われて育った人によくあるケース。強い期待に押しつぶされまいと、無関心や批判で距離を取り、関与しないことに理由をつける。
このように、心の奥底に不安や恐れを抱えた人が攻撃的な言動をする場合、実際は相手を傷つける意図はないことがほとんどです。その場しのぎの言動も多く、一貫性がないようにも見えます。
だからといって、無理に相手を許す必要はありません。ただ、「これは私への攻撃ではなく、相手自身の不安や混乱の表れかもしれない」と受け止めてみることで、心の緊張を少し緩ませることができるかもしれません。
Mさんには、お兄さんの言動は、介護に関わろうとしないことへの罪悪感や、Mさんやご両親からの要望を「批判や攻撃」と捉えていることに起因する可能性があることをお伝えました。そのうえで、今は協力を期待せず、ケアマネジャーに相談し、Mさんのサポートを代替できるサービスの利用を提案しました。
加えて、交通費や食材・衣類の買い出しを代行した際の費用についても、精算するようお話ししました。お兄さんへの不満の背景には、ご両親に金銭面で遠慮しているMさん自身の心理状態も影響していると感じたからです。
Mさんは、お兄さんが両親から住宅資金の援助を受けていたことが心に引っ掛かっていたようでした。「自分は親に負担をかけたくない」という思いから、介護に関わる費用も黙って自腹を切っていました。しかし、1回ごとの支出は少額でも、1年以上続くと相当な金額になります。「私だけが苦労している」「こんなの不公平だ」という思いは、実際の介護負担以上に大きなストレスとなることがあります。
Mさんはまず、熱中症対策のために届けていたスポーツドリンクを、ネット通販の「定期便」に切り替えました。毎週末に在庫確認をする手間をなくし、「ストックが多くなっても構わない」と気持ちを緩めたことで、精神的な負担を減らすことができました。
また、毎週末だった実家への訪問頻度を減らし、安否確認にはタブレット端末を使ったテレビ電話を活用することにしました。画面越しでも両親の様子は十分に伝わります。息子も参加するようになり、音声通話だけのときよりも会話が弾むようになりました。
費用の件についても、Mさんが勇気を出して切り出してみたところ、母親は「それもそうだったね。なんでもっと早く言わなかったの」と、すぐに応じてくれました。交通費や買い出しの費用だけでなく、心付けも添えてくれるようになったそうです。Mさんは、「金額よりも、母が自分の働きかけをちゃんと見ていてくれたことがうれしかった」と話してくれました。
写真:著作者:shurkin_son/出典:freepik
少し気持ちに余裕が出てきたMさんは、当時を振り返りながらこう話してくれました。
「兄の言動は今も受け入れがたいです。でも、長男として期待を背負ってきたことが、実は苦しかったのかもしれません。両親からの金銭的な支援があったとしても、兄が本当に求めていたものは違っていたのかもしれないですね」。「否定された」と感じていた心の痛みも、少しずつ和らいでいったようです。
協力してほしい相手から理不尽な言葉をかけられれば、腹が立つのは当然です。けれども、そうしたときこそ、「自分の負担を減らすために、新たな手段を試すタイミング」ではないかと私は思います。
繰り返しますが、相手を無理に許す必要はありません。ただ、相手に対する怒りや「自分の方が正しい」という考えにとらわれすぎると、自分を楽にするための工夫や、新たなサービスを利用することへ意識が向かなくなってしまいます。相手の誤りを指摘したところで、介護の負担が軽くなるわけではありません。
だからこそ、家族との関係がこじれたときには、介護環境や自分の関わり方を変えるタイミングだと考えてみましょう。意外なところに、これまでにない選択肢が見えてくることもあるのです。
写真:Freepik、写真AC
この著者の以前の記事
・疲れ切ってしまう前に──仕事と介護に挟まれた私が見つけた「回復の順番」
・親がサービスを拒むとき、どうする?“スムージー”が開いた意外な突破口
・義父との心の距離と葛藤……“家族”を理由に自分を犠牲にしない介護の選択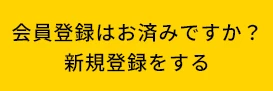

著者:橋中 今日子
介護者メンタルケア協会代表・理学療法士・公認心理師。認知症の祖母、重度身体障がいの母、知的障害の弟の3人を、働きながら21年間介護。2000件以上の介護相談に対応するほか、医療介護従事者のメンタルケアにも取り組む。