家族が病気やけがで介護が必要になった直後、介護者は回復を望む一心で驚くほど介護に没頭することがあります。しかし、介護は長期化することが多く、初期と同じエネルギーを保ち続けるのは難しいものです。
関東地方に住むAさんは、2年前に脳梗塞を発症し片麻痺になった母親(70代・要介護2)と一緒に暮らしています。母親は、家の中では杖を使って歩けるまでに回復しましたが、外出時は車椅子が欠かせません。通院や買い物などには、Aさんが毎回付き添っています。
倒れた直後は「死にたい」と悲観的になっていた母親の笑顔を取り戻したいと、Aさんは懸命にサポートを続けました。今では母親はデイサービスに週に3回通い、リハビリにも積極的に取り組んでいます。週末には「友人に会いたい」「買い物に行きたい」と活動的になりました。母親が元気になってくれたのは嬉しいことですが、Aさんの週末は母親の予定で埋まっています。Aさんが「その日は都合が悪い」と希望を断ると、母親は「私のことなんて、どうでもいいのね」と拗ね、不機嫌になってしまいます。
母親が倒れてから2年間、Aさんの生活は母親が中心でした。しかし最近「どうして私がこんなことをしなければいけないの?」と、些細なことで苛立つようになりました。
先日は、母親が食事を残したのを見て、突然怒りが込み上げ「せっかく作ったのに、なんで残すの?」と怒鳴ってしまいました。さらに「好き嫌いなんて言える立場なの? 人の世話になっている身でいい気なものね!」と母親をなじる言葉が止まらなくなったのです。「一番辛いのはお母さんなんだから、私がしっかりしないと」と気持ちを切り替えようとしますが、どうしても優しくできません。母親を無視するような態度をとってしまうこともあります。Aさんは「私は最低だ……」と自己嫌悪に陥ってしまいました。

私はこれまで、家族を介護する方々から延べ2000件以上のご相談をいただいてきました。その中でも「優しくできない」「些細なことでイライラしてしまう」という悩みは非常に多いのです。それぞれの状況を詳しく伺うと、家族をケアするために、自分の時間をほとんど取っておられません。また、深夜や早朝の介護トラブルに対応するため、慢性的な睡眠不足に悩んでいる方も少なくありません。
長期的なストレスに晒されたり、十分に休息する時間が取れない状態が続くと、燃え尽き症候群が起きやすくなります。
以下は、燃え尽き症候群の代表的な症状です。
・電池が切れたかのように突然動けなくなる
・やる気や意欲が低下する
・嬉しい、楽しいといった感情の動きが鈍くなる(情緒的消耗感)
・人への思いやりや共感力が低下する(脱人格化)
自分のことを後回しにして母親のケアを優先してきたAさんは、心も体も限界に近づき、「脱人格化」と呼ばれる燃え尽き症候群の症状が現れている可能性がありました。
Aさんには、「自分を責める必要はありません。イライラしたり優しくできないと感じるときは、それは心身からの『休息が欲しい!』というサインですよ」とお伝えしました。
介護は長期化しやすいものです。最初のうちは気力で乗り切れても、年単位で続く介護生活の負担は大きくなり、多くの人が疲労困憊(こんぱい)の状態に陥っています。
いつ倒れてもおかしくないほど疲れ切っているのに「私はダメな人間だ」「ちゃんとできていない」と自分を責め、「もっと頑張らなければ!」と自分で自分に無理を強いてしまうこともあります。Aさんもまさにその状況でした。
燃え尽き症候群の状態から回復するには、まずは質の良い睡眠を取ることが第一です。一人でリラックスできる時間を意識的に確保し、しっかりと休息を取ることも必要です。
そこで私は、Aさんに「お母様に、疲れていることや休みたい気持ちを伝えることはできますか?」と尋ねてみました。
Aさんは「我慢してきた、疲れたと言ったら、母は傷つき、怒るのでは……」と戸惑われていましたが、母親への共感や優しい気持ちを取り戻すには、この2年間抱え続けてきた「我慢」という名の重荷を、少しずつ手放していくことが必要です。
意を決したAさんが「今度の週末は友人と買い物に行きたい」と切り出したところ、母親は「行ってきなさい! 楽しんできて!」と意外にも喜んで送り出してくれたそうです。Aさんは2年ぶりに美容院に行き、友人とのんびり買い物を楽しめたと報告してくれました。
また、Aさんは「これまで私は、自分の予定を先に伝えていなかったんです。母が出かけたい、何かをしたいと言われてはじめて、『その日は予定がある』と断ろうとしていたから、母はがっかりして拗ねていたのかも」と振り返られました。そこで、自分の予定や都合を積極的に母親に伝え、お互いの予定を調整する時間を意識的に作るようになったそうです。罪悪感がゼロになったわけではないものの「母への優しい気持ちを取り戻すためにも、自分の時間が必要なんだ」と考えることで、気持ちは楽になったとのことでした。
要介護者が安心して過ごせる環境づくりやケアはもちろん大切です。しかし、介護者が休息し、自分の時間を取れない環境での介護は必ず破綻します。
自分のためにコーヒーを淹れる、回り道をして家に帰る、空を見上げるなどの「小さな自分ファースト時間」を意識的に取り入れたことで「ストレスが減った」「気持ちが楽になった」という方はたくさんおられます。
介護そのものの負担やストレスをゼロにすることはできなくても、自分の時間を取り戻すための取り組みは、私たちの心身の健康を守ってくれるのです。
そして、生活が落ち着いた時期にこそ、介護環境の改善に目を向けましょう。要介護者がサービスの利用を嫌がったり、週末にサービスを提供している事業所が見つからなかったりと、今すぐに望む状況を作れないこともあるでしょう。
そんな時にこそ一人で悩まず、ケアマネジャーや地域包括支援センターに「疲れ切っている。介護環境を変える方法を一緒に考えてほしい」と相談してください。問題がすぐに解決できなくても、共に考えてくれる人や相談できる場所があることそのものが、心理的ストレスを減らすことに繋がるからです。
介護でイライラして優しくできないときは、休息を取るタイミングであり、支援者に相談する時期の訪れだと覚えておいてください。
写真(トップ):ピクスタ
▼この著者の他の記事
・経験者にしかわからない辛さは家族会やSNSでシェア! 介護の精神的負担を軽くする
・ケアマネジャーが「頼れる味方」になる伝え方のコツ
・周囲とのトラブルが起きやすい「前頭側頭型認知症」の介護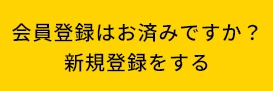

著者:橋中 今日子
介護者メンタルケア協会代表・理学療法士・公認心理師。認知症の祖母、重度身体障がいの母、知的障害の弟の3人を、働きながら21年間介護。2000件以上の介護相談に対応するほか、医療介護従事者のメンタルケアにも取り組む。