これは、50代の息子(著者・久保研二〈ケンジ〉)と80代の父親(久保治司〈ハルシ〉)が交わした日々の断片の記録です。数年前、息子は関西に住む父親を引き取って、2人で田舎暮らしを始めました。舞台は、山口県の萩市と山口市のほぼ真ん中に位置する山間部・佐々並(ささなみ)にある築100年の古民家です。ここで、歌や曲や文章を書くことを生業(なりわい)とするバツイチの息子と、アルツハイマー型認知症を患っているバツイチの父親が、関西人独特の「ボケ」と「ツッコミ」を繰り返しながら、ドタバタの介護の日々を送っています。
ハルシが着ている服は、すべて私のお下がりです。なので、年齢の割には派手なファッションとなっております。
「研二、ワシなあ、このアジダスのシャツが好きやねん、覚えといてくれや」
「そうか、わかった。ちょうどその服が着やすいんやな、サイズとか肌触りとかがな」
「そうやねん、それとな、もう1着、黄色いシャツがあるやろ、あれも好きやねん」
「黄色って、これのことか」
「そや、それや」
「これはどう見てもオレンジ色やけど……まあ、黄色でもええわ、これもハルシのお気に入りやな」
「そやねん、そやから、あとの服全部いらんわ、捨ててくれ」
「そんなわけにいくかいや。こっちも洗濯する都合があるがな」
「1着が汚れてから洗濯して、それが乾くまでのあいだ、もう1着を着てたら、全部で2着あったらじゅうぶんやないか」
「なんでやねん。今着てるシャツ……それ着たまま、ハルシ寝てるやろ? ええか、よう聞いとけよ。それで毎朝病院(ディサービス)行って、風呂に入って、上から下まで全部着替えて、脱いだやつを持って帰ってくるやろ。それをその日のうちにすぐに洗濯しても、朝までには乾かんから、どうしてもあと1着か2着は、替わりがいる計算にならんか?」
「そやから、いちいち洗濯せんでもええと、ワシは言うとんねん」
「洗濯せな、1回着て脱いだもん、汚いやないかい」
「汚なないとゆうとるやろが、別に表で仕事するわけでもないねんから……ずっと一日中部屋の中で、チイチイパッパゆうてて、なんで服が汚れるねん」
「ほんなら、その胸についてるパン屑(くず)はいったい何や?」
「これか? 何やろなあ、これはいったい……………あっ、これ、パン屑やがな」
「最初から、パン屑やとワシが言うてるやないか。それはいったいどうしたのかな、と、治(はる)っさんにワシが聞いてるんやがな」
「これはなあ、たまたまやな。こんなことは、年に1回か2回、あるかないかのことやで」
「とにかく、風呂に入る時に1回脱いだもんを、風呂からあがってからもっぺん着るのん嫌やろ」
「全然ワシは嫌やない」
「真面目に言うてんのんか? でも、なんぼなんでも、パンツは履き替えたいやろ」
「パンツも汚れてへん」
「たいがいにせえよ」
「何がや」
「汚れるも何も、治っさんのパンツは紙オムツやないかい。使い捨てや。毎回捨てるもんなんやで」
「そんなこと知らん」
「知らんことあるかいな」
「忘れた」
「何でも、忘れたゆうたら済むと思ったら、大間違いやぞ」
「…………」
「なあ治っさん、神さんは、ちゃんと治っさんを見てるねんで。治っさんの行いを、一から十まで、全部、お見通しなんやで」
「神さんかて、ちゃんとわかってくれるわい」
「何をわかってくれるんや」
「そんなもん、ワシのパンツのことに決まってるがな」
「パンツがどないしたんや」
「いいや、オマエには言わへん」
「気になるやないか。………、あっ、まさか、漏らしたんちゃうやろな」
「言わへんゆうたら、言わへんのや、ワシもう寝るで」
「ちょっと待て。言うてくれや」
「知らんほうが、オマエのためや」
「そんなこと聞いたら、めっちゃ心配になるやないかい」
「心配なんかせんでもええ。大船に乗った気分で、どっしりと構えとったらええで」
「そうか、今度病院(ディサービス)の看護婦(介護士)さんに聞くわ」
「そんなもん、わざわざ聞かんでもええ」
「…………」
「ちょっと、パンツが重たいだけや……」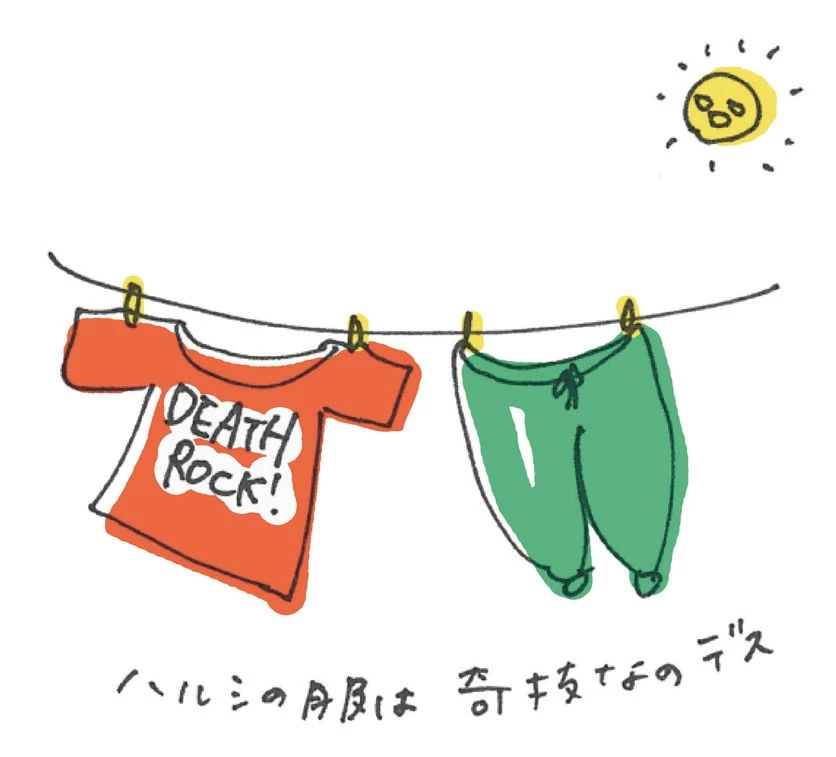
病院(ディサービス)のきれいなおねえさんが、ハルシに尋ねます。
「ハルシさん、若い頃は、何の仕事をしておられたんですか?」
「ボク? ボクは、洋服屋」
「へえ~、洋服の仕立て屋さんだったんですか?」
「仕立てとちゃうねん。売ってたんは既製品や。もちろん裾上げとかはするけどな」
「そうだったんですか」
「その、洋服を売った金で、こいつをおっきい(大きく)したんや」
若き日のハルシは、尼崎市出屋敷にある中通り商店街というところで、ウース洋服店という、小さな小さな店を営んでいました。世の中に、まだまだ良質の洋服が行き届いていなかった時代でしたから、そこそこ繫盛していたようです。
ハルシは長期にわたり、商店街の人たちから「ウース兄(にい)ちゃん」と呼ばれ、後に結婚した私の母は、自動的に「ウース姉(ねえ)ちゃん」になりました。
やがて、世の男性は、洋服よりも、車にお金を使うようになり、いわゆる、糸へん業界の陰りが見えてきた頃、ハルシは洋服屋を見切り、タクシーの運転手に“とらばーゆ”したのでした。
無学だったハルシは、たまたま幼い頃から人一倍利発だった息子を、いい学校に行かせようと必死になりました。そして、中学から、髙い月謝が必要な私学に、背伸びをして息子を入れました。
その息子は、曲がりなりにも成人して、紆余曲折を経て、学生時代に身につけた特技を活かして、親の晩年の生き様を文章にして、食い物にしているのですから、世の中は実に不思議なものです。
「なっ、治(はる)っさん?」
「はぁっ? なんも聞いてなかった」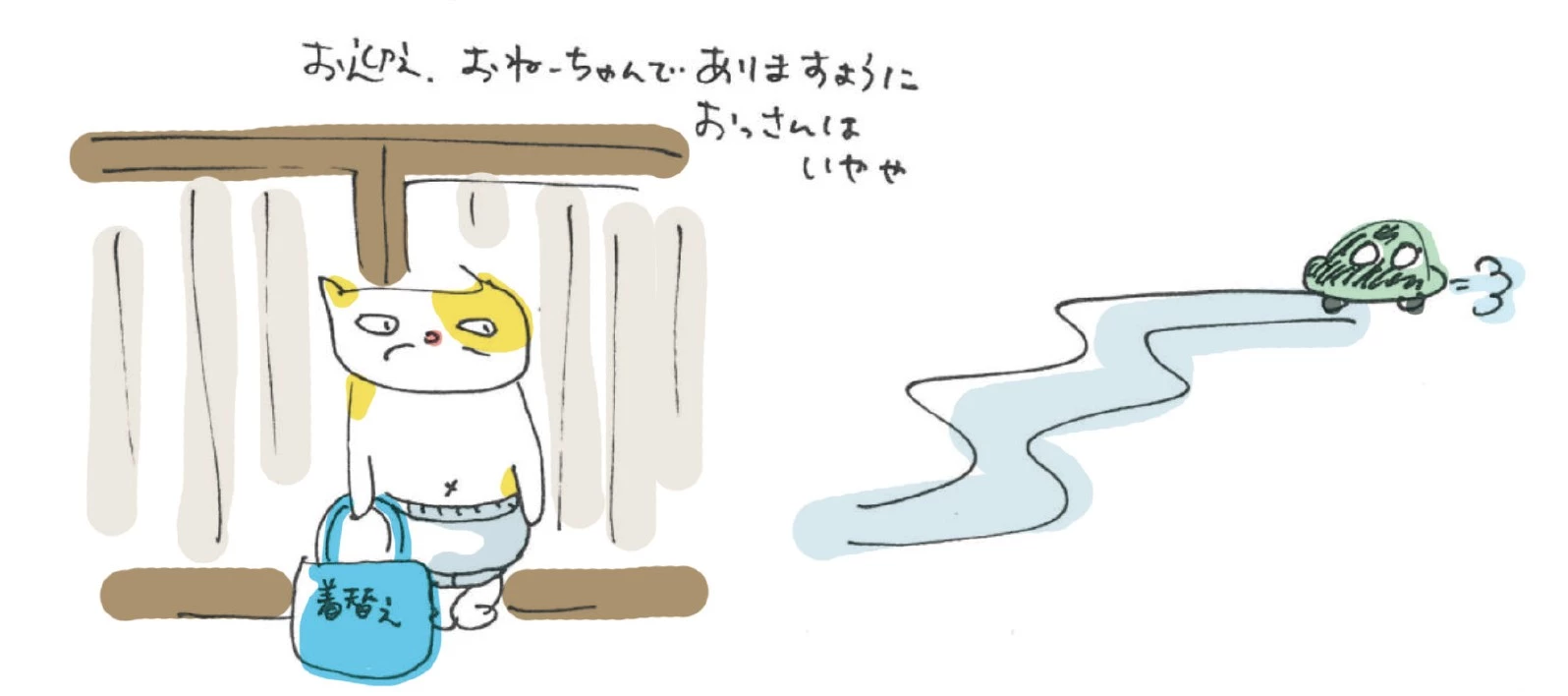
写真(トップ):PIXTA
この著者のこれまでの記事
・音楽、そして歌が呼び覚ますハルシの記憶|父と息子の漫才介護⑫
・今日もスカたん上等! 父と息子の高品質な掛け合い|父と息子の漫才介護⑪
・シュッポシュッポの鍋と最強菜っ葉のずっこけ食卓トーク|父と息子の漫才介護⑩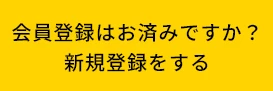

著者:久保研二
久保研二(くぼ・けんじ)
作家(作詞・作曲・小説・エッセイ・評論)、音楽プロデューサー、ラジオパーソナリティ
1960年、兵庫県尼崎市生まれ。関西学院中学部・高等部卒。サブカルチャー系大型リサイクルショップの草創期の中核を担う。2007年より山口県に移住、豊かな自然の中で父親の介護をしつつ作家業に専念。地元テレビ局の歌番組『山口でうまれた歌』に100曲近い楽曲を提供。また、ノンジャンルの幅広い知識と経験をダミ声の関西弁で語るそのキャラクターから、ラジオパーソナリティや講演などでも活躍中。2022年、CD『ギターで歌う童謡唱歌』を監修。
プロフィール・本文イラスト:落合さとこ
https://lit.link/kubokenji