母と娘の関係性とその介護について考える連載。今回は、5歳のときに母親が指定難病のALSと診断を受けたという経験をもつカヨコさん(会社員・40代)に話を伺いました。病気が進行する中、母親は「最重度の障害を持つ女性が公的なサービスを使って一人で生きていけるかを体現する」という、前例のない生き方を希望し、独り暮らしを始めたのですが……。
カヨコさんが5歳の時、当時32歳の母親が指定難病の筋萎縮性側索硬化症(ALS)(*)という診断を受けました。当時のカヨコさんは母親の病気を理解するにはあまりにも幼く、親子関係を構築しながら徐々に母親の病気を受け入れていったそうです。小学3年生までは仕事が忙しい父親と離れ、母親の実家の漁師町で漁師の親戚たちと賑やかに生活をしていました。その後、再び家族3人の生活に戻りましたが、母親の症状は進行していき、カヨコさんが小学6年生の時に気管切開、中学1年生になるころには人工呼吸器をつける決断をし、24時間介護が必要な状態になりました。
しばらくの間、母親は、行政の難病支援制度や福祉系学科の大学生ボランティアなどを活用することで、家族以外が介護するシステムを構築し、自宅で生活をしていました。ところが、カヨコさんが23歳の時、母親は前例のない行動を起こします。
*筋萎縮性側索硬化症(ALS)…手足・のど・舌の筋肉や呼吸に必要な筋肉を動かすための脳からの指令を伝える「運動ニューロン」が障害されることで筋肉への指令が阻害され、手足や顔の筋肉が徐々にやせ衰えていく病気。
母親は「最重度障害を持つ女性が公的なサービスを使って一人で生きていけるかを体現する」ことをテーマとして自ら事業所を立ち上げ、家族と離れてアパートで独り暮らしを始めました。そこには、自分のことは自分で決める(呼吸器をつけて車椅子で大好きなアイドルの追っかけに行くことも含めて)、介護を家族に担わせないという、在宅での暮らしの当初からの母親のスタイルがあり、独り暮らしという選択は、その思いの集大成のようなものだったのです。
家族介護にはいろいろな考え方があり、身体介助や医療行為などの直接的な介護を家族がしないことを良く思わない人がいることもカヨコさんは承知しています。それでも、母親が選んだ道を受け入れ、直接的な介護はプロに任せ、気丈な母親を支える人たちのサポートを受けたり、円滑に介護してもらえる体制を考えたりなど、家族としてできることをしながら自分の人生も大切にするという、母娘介護を最期まで貫きました。
一方で、いくら自分の人生も大切にするといっても、カヨコさんは母親に「いつ、なにがあってもおかしくない」という危機感を常に持っていました。そのため、親が元気であれば躊躇なくできる決断も「自分の意志で好きなところに住める最初で最後のチャンスになるかも」との思いで決断し、希望していた地方の大学へ進学しました。離れて暮らしている時は「万が一の時は、母親のもとに急ぐ新幹線の時間だけ延命してもらおう」などと考えていたそうです。
その後、東京に戻り、母親が立ち上げた介護事業所の請求事務担当とOLの仕事の二足の草鞋生活を送っていましたが、結婚により再び、地方へ。しかし、結婚生活は長くは続かず、東京に戻ります。それからしばらくして新たなパートナーと出会い、現在は2人の娘の母親となりました。カヨコさんは自らの20~30代を振り返って「母親がALSだって、地方の大学に行ったり、結婚したり離婚したりもする」と自嘲気味に笑います。
カヨコさんは母親の筋力が衰えて話すことが難しくなってから、母親の口の動きから言葉を読み取る「口文字」で、母親と会話をするようになりました。1つひとつ文字を紡いて文章にしていくため、読み取りの途中で母親の言っていることがカヨコさんに対する文句であると気づくこともあったとか。自らが母親となった今、娘たちを怒っている時に、すぐに思いを伝えることができなかった母親は「すごいストレスを抱えていたのかもしれない」と、当時は考えもしなかったことが気になるようになりました。
カヨコさんと母親とのコミュニケーションの手段は「口文字」がスタンダードで、それ以外の方法を知らなかったため、カヨコさん自身がそこにフラストレーションは感じることはなかったそうです。また、友達の母娘関係と違うところがあっても、幼いころから自分と母親との関係しか知らなかったため、特に疑問に思うことはありませんでした。しかし、思春期になって初めてブラジャーを買う時、父親にそのことを言い出しにくく、友達のように母親と買いに行きたかったそうです。
今回、取材をする中で、カヨコさんは母親のことを「操さん」「みーちゃん」と名前やあだ名で呼んでいることが印象的でした。外向けに母親の話をする時はあえて親子のフィルターを掛けずに母親を名前で呼ぶことで、操さんという個人の思いを伝えたいという考えがそこにはあるそうです。
さらに、病気の当事者の気持ちを配偶者がその顔も見ずに話をする様子を見た時、それは違うと思ったのだそうです。きっと母親も同じ思いだったのでしょう。親子で講演会に登壇した際、カヨコさんが母親の言葉を代読していても、母親がカヨコさんを娘として紹介することはあまりありませんでした。ただし、厚労省へ陳情に行った際は、相手に印象付けるため、親子だということを猛アピールして「娘」と呼ばれていた、とカヨコさんは苦笑します。孫たちに「ばあば」と呼ばれると「操と呼べ」と怒るなど呼ばれ方に対して、操さんなりのこだわりがあったのかもしれません。
人口呼吸器をつけて29年、ALSと診断されて36年10か月となる2022年8月、母親はその生涯を終えました。カヨコさんはお別れの会を、東京国際フォーラムの母親がお気に入りだった部屋で開催し、約100人もの人が参列したそうです。気が強く、ワガママなところなど、反面教師的に母親から学んだこともありますが、そんなに多くの人が見送りに来てくれたことで、不思議と人を惹きつる魅力のある母親だったと、改めて尊敬の思いを抱くことができたといいます。
「他にはない独特な母娘関係なのでは?」とカヨコさんに質問をすると、親の介護をしていると忘れてしまいそうになる、母娘関係に関する大切な話を聞くことができました。カヨコさんが大人になり、母親に頼られるような立場になってから、母親が娘に甘えたがったり、周りを困らせるようなことをしたときは「あなたの方が私より長く生きているのだから、母親としてしっかりしてよ」と、母親を母親に戻すように仕向けてきたそうです。「病気だから」と大人になった自分が母親に何かしてあげることは簡単ですが、そうすることで母娘関係が逆転してしまうことがあります。しかし、カヨコさんは最期まで操さんは母親でカヨコさんは娘という、本来あるべき姿の母娘関係を保つように努めました。
約37年間という時をALSの母親と共に生きたカヨコさんですが、母親を失った喪失感はあまりなく、今もどこかで好き勝手に生きているのではないかという気がしているそうです。今では2人の娘の母親となったカヨコさんですが、母親と娘は子育てなど似たような人生をなぞることが多い傾向があるからこそ、「みーちゃんだったら、こういう時はどうしたんだろう」と思ったり、「私が、もし母親のようにALSになったらとしたら……」と考えた時、「母親と同じ決断ができただろうか…」とすぐには答えが見つからないところがあるといいます。それでも、母親の選択は最善策であり、そこまでの道のりを娘としてすべて見てきた自分は結局、同じ道を選ぶだろうと。そこには、2人の娘のことを思う母親の顔をしたカヨコさんの姿がありました。
写真提供(本文中):カヨコさん
写真(トップ):PIXTA
この著者のこれまでの記事
・後悔ばかりの認知症介護……それでも前を向く娘の選択|娘はつらいよ!?⑲
・夢を支えてくれた母を支えるという選択|娘はつらいよ!?⑱
・母と私、そしてヤングケアラーになった娘へ|娘はつらいよ!?⑰
・「ごめんね」を胸に、母を支え続ける娘|娘はつらいよ!?⑯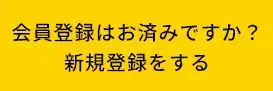

著者:岡崎 杏里
大学卒業後、編集プロダクション、出版社に勤務。23歳のときに若年性認知症になった父親の介護と、その3年後に卵巣がんになった母親の看病をひとり娘として背負うことに。宣伝会議主催の「編集・ライター講座」の卒業制作(父親の介護に関わる人々へのインタビューなど)が優秀賞を受賞。『笑う介護。』の出版を機に、2007年より介護ライター&介護エッセイストとして、介護に関する記事やエッセイの執筆などを行っている。著書に『みんなの認知症』(ともに、成美堂出版)、『わんこも介護』(朝日新聞出版)などがある。2013年に長男を出産し、ダブルケアラー(介護と育児など複数のケアをする人)となった。訪問介護員2級養成研修課程修了(ホームヘルパー2級)
https://anriokazaki.net/