岡崎家の「ケア活」問題、「財産整理」に続き、「墓じまい」のお話です。私は一人娘で跡を継ぐ人がいないため「いつかは墓じまいの問題をきちんとしなくては…」と家族で認識していても、両親の介護や育児などで、どんどん後回しに。そんな中、祖父の法事がきっかけとなり、「墓じまい問題」が進み始める!?
「ケア活」第一弾(!?)として「財産整理編」を3回に渡ってお話ししましたが、今回からは「ケア活」第二弾として我が家の「墓じまい」についてお話しさせていただきます。
「墓じまい」の体験談を友人などに話すと、思った以上に関心が高いことに気が付き、「もしかして、みんな気になるけれど、誰かに聞くことができない話」なのではないか、と感じたため、このテーマを取り上げることにしました。
このテーマについては、私のように娘という立場(一人娘や男きょうだいのいない娘)の方の関心が特に高い傾向があるようですが、それ以外の方も、私の体験談を通じて「墓じまい」のシミュレーションをしつつ、親が元気でみんなの心に余裕があるうちから「墓じまいに関するケア活」について話し合ってもらいたい、と考えています。なぜなら、脅すわけではありませんが、我が家のケースでは、非常にお金が掛かった(200万円以上)ためです。
【専門家(株式会社OAGウェルビーR 代表取締役 CEO 黒澤史津乃さん )が解説!】
※以下、グレー部分
従来型の墓地の「墓じまい」を行う場合に掛かる費用について、確認しておきましょう。
実際に墓から遺骨を取り出す時は、作業をしてくれる石材店への費用、閉眼供養料、不要になった墓石の撤去・処分費用などの名目の費用がかかります。
さらに、新しい永代供養の墓地または納骨堂に取り出した遺骨を納めるために、永代供養料として遺骨1体ごとに数万~数十万円の費用が掛かります。また、粉骨にして納骨するケースでは、取り出した遺骨を乾燥させ、粉骨にする費用として1体ごとに数万円がかかることもあります。
従来の墓地は菩提寺の境内にあったけれど、改葬先の墓地、または納骨堂が菩提寺とは関係のない場所になるとすれば、これまでの寺との関係を清算しなければならないので一筋縄ではいかず、高額な離檀料等を請求されるケースもあり、要注意です。
最近では、後継ぎがいなくてもひとまずは3回忌、7回忌までなどの期限付きで従来型の墓地に納骨させてもらい、その間の供養料を前払いする契約プランを導入している寺や霊園も増えています。期限が過ぎると、寺などの墓地管理者が墓石を撤去し、埋葬されている遺骨を敷地内の合祀墓などに移すため、そのための費用もすべて前払いしておきます。
このようなプランの場合、期限付きとはいえ、いったんは家族だけの墓に入れること、また、自分が生きている間に墓を畳まなくて済むというメリットがあります。
一人娘の私にとって、「財産整理編」で売却した祖父から父が引き継いだ”田舎の土地”の近くにある先祖代々のお墓も以前から気になる問題の1つでした。
なぜなら、一人娘の私がお嫁に行ってしまったら、あとを継ぐ人(墓守り)がいなくなってしまうからです。というのも、我が家の先祖代々のお墓は少し事情が複雑で、たくさんきょうだいがいた家に生まれた祖父が子どものいない親戚の家の養子になり、その家が絶えることをなんとか防いだという経緯があります。祖父には父という跡取り息子ができたのですが、その次の代は女の子の私となり、祖父の時代に勃発していた「家を継ぐ人がいない問題」が再燃したのです。
祖父の時代はきょうだいが多いなどの理由から養子という形でなんとか繋ぐことができましたが、令和の現代では、戦前のそんな解決策を取ることは難しいのです。私が婿をもらい継ぐという選択肢もあるかもしれませんが、正直なところ、それは私にとって荷が重く、ご先祖様には申し訳ないのですが親の世代で解決してもらいたい問題でした。祖父の世代の親戚からは「お前が婿をもらってでも家を守れ」と言われたこともありましたが、その下の世代(父の世代)の人たちは、「あなたの住んでいるところも遠いし、どこも跡取り問題で苦労しているからね…」とこちらの立場を理解してくれ、両親は「お墓のことは私たちの世代でなんとかする」と言っていたのです。
一方で、「お墓のことは私たちの世代でなんとかする」と言いながらも、両親は立て続けに病気になるなどで墓じまいどころではなくなってしまいました。また、「絶対、嫁に行く!」と言いつつ30歳を過ぎても嫁に行かない娘の私も両親も、「墓じまい問題は、まだ考えなくてもいいか…」と「ケア活」的な順位がどんどん下がっていたのは事実です。ところが、結婚を諦めかけていた頃、突然私にもご縁が巡ってきて、36歳で私は念願!?の結婚をすることになったのです。
【娘たちからの相談が増加】
男きょうだいのいない娘さん、しかも親の代で先祖代々のお墓のある地元からは出てしまっているため、お墓のある場所には住んだこともないという方からの相談が増えています。娘であり、自分の代までは何とかして墓守りをしようという気持ちがあっても、後継ぎがいなかったり、子どもがいても負担を掛けたくないため、お墓のある地方で生まれ育ち、菩提寺や近隣とも面識のある親世代が元気なうちに墓じまいを済ませておきたい、というご相談を受けることは多くあります。
イラスト(下):日野あかね

結婚後は「墓じまい問題」のことを考える余裕がないほど、父親の介護は大変になり、母親まで要介護状態になってしまいました。さらに私には、仕事、新しく築いた家庭のこと、息子の育児と日々いっぱいいっぱいです。お墓は日帰りで行くことが不可能な地方にあるため、それまでは春と秋のお彼岸のどちらかに家族の誰かが代表してお墓参りをしていましたが、両親が要介護状態になってからはそれも難しくなり、ご先祖様には心苦しいならがらも、事情を話してお寺に管理をお願いしていました。
ところがある日、お寺から祖父の法事についてのお知らせが届きました。そこで母親は自身がどんどん体力を失っていることもあり、「墓じまい問題をそろそろ真面目に考えなくては……」と思ったようです。認知症の父親に相談しても「お前たちに任せる~」と埒が明きません。そこで、娘の私に相談すると「あなたたちの介護に加えて、そんな問題まで残されたら困る!」と親子だから言えるような(今思えば要介護の母親に……)ひどい言葉をぶつけてしまいました。
だからと言って悩んで落ち込むようなタイプではない母親は、自分にすべてを押し付けられたことにキレて、「死んだあとのことなんて、私は知らない。あんたが勝手にすればいいでしょ」と投げやりになり、母娘バトルに発展。そんな様子を見ていた近所のオバちゃんが母親に対して「あんたが約束通り、親の最後の仕事としてきちんとしてあげなさいよ」と助言してくれたおかげで(オバちゃんは以前、母親が「自分たちが生きている間に墓じまいをする」と言っていたのを覚えていたのだった)、しぶしぶ母親は動き出すことになりました。
そして皮肉にも、この「墓じまい問題」が、母親が生前に行った私との最後の「ケア活」となったのです。母親が不慮の事故で亡くなる2日前、墓じまいについて、電話でお寺に相談をしていたのです。そして母親亡きあとは、最終的にはその意志を継いで私が最後まで墓じまいを成し遂げることになったのですが、そこで母親とご住職が話していたことで、その後の「墓じまい」は(お金のこと以外は…)スムーズに進めることができたのです。そのことについては母親には感謝しかありません。事がスムーズに進むきっかけとなった母親とご住職が何を話したかは、次回で!
【永代使用と永代供養の違いに注意!】
子供がいないご夫婦から終活のご相談を受け、お墓の話題になった時、「菩提寺に先祖代々の墓があるから大丈夫です」とか、「親が亡くなった時に霊園に墓を立てたので大丈夫です」という方が多くいらっしゃいます。結論から言うと、それだけでは大丈夫ではありません。夫が先に亡くなったとすると、妻がこの墓の使用権利者としての地位を承継した場合、亡き夫を納骨できますが、その後、妻が亡くなった時は、誰か他にこの墓の承継者がいなければ、妻は夫が眠るこの墓に入ることはできません。
そもそも寺の境内や霊園の一区画を占有し、「〇〇家」という墓石を立てている墓の場合、その区画を使用する権利を有する存命の権利者がいることが必要とされます。この「存命の」ということがポイントで、墓石というものは、〇〇家を代々承継していく後継ぎがいるという前提で立てられているのです。ところが、家族のカタチが多様化した昨今、そもそも後継ぎがいないという人も増えていますし、子どもがいるからといって当然墓の承継をしてくれるとは限りません。このような説明をしていると、「この墓を購入したときは、永代使用だと聞いていたのに」と首をかしげる方もいらっしゃいます。
実は、ここで言う「永代使用」とは、存命の権利者がいる限りにおいては永代使用ができるという意味であり、使用する権利を継いでくれる後継ぎがいなければ、そもそも最後のひとりはその墓に入ることすらできないのです。
多くの方はこの「永代使用」について、後を継いでくれる人がいなくても供養をし続けてくれる「永代供養」と勘違いしてしまうのだと思われます。「永代使用」と「永代供養」では、大きな違いがありますので、しっかり確認することが大切です。
写真:写真AC、PIXTA
監修、アドバイス:黒澤史津乃
【監修者プロフィール】
黒澤史津乃(くろさわ・しずの)…株式会社OAGウェルビーR 代表取締役 CEO
20年以上にわたり、家族に頼らずに老後とその先を迎える「おひとりさま」の支援に携わっている。2007年行政書士登録。2019年消費生活アドバイザー及び消費生活相談員(国家資格)登録。
一般社団法人全国高齢者等終身サポート事業者協会代表理事として業界のけん引役をつとめる他、一般社団法人横浜イノベーション推進機構代表理事として、横浜市内の多様で複雑化した広範囲の地域課題解決にも取り組む。
内閣官房「認知症と向き合う幸齢社会実現会議」構成員、厚生労働省「身寄りのない高齢者等の生活上の課題実態把握事業」有識者委員。社会福祉法人浴風会特別研究員として厚労科研「独居井認知症高齢者の権利利益の保護を推進するための調査研究」(25GB0101)における分担研究を担当。
この著者の前の記事
・こんなことも「ケア活」なんです!? 財産整理編①
・こんなことも「ケア活」なんです!? 財産整理編②
・こんなことも「ケア活」なんです!? 財産整理編③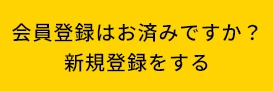

著者:岡崎 杏里
大学卒業後、編集プロダクション、出版社に勤務。23歳のときに若年性認知症になった父親の介護と、その3年後に卵巣がんになった母親の看病をひとり娘として背負うことに。宣伝会議主催の「編集・ライター講座」の卒業制作(父親の介護に関わる人々へのインタビューなど)が優秀賞を受賞。『笑う介護。』の出版を機に、2007年より介護ライター&介護エッセイストとして、介護に関する記事やエッセイの執筆などを行っている。著書に『みんなの認知症』(ともに、成美堂出版)、『わんこも介護』(朝日新聞出版)などがある。2013年に長男を出産し、ダブルケアラー(介護と育児など複数のケアをする人)となった。訪問介護員2級養成研修課程修了(ホームヘルパー2級)
https://anriokazaki.net/