介護は長期化しやすくなります。要介護者への介助量が次第に増すだけでなく、介護する家族自身も加齢や持病といった影響を受けます。以前は負担に感じなかった動作が辛くなるなど、さまざまな心身の変化に向き合わなければならず「この先、介護を続けられるだろうか」と揺らぐ局面が訪れます。こうした変化に合わせ、介護サービスや医療ケアを何度も見直していく必要があります。
関西在住のCさんは、母親(90代)との二人暮らしです。Cさんは15年前、父親の他界を機に、ひざの悪い母親を支えるために退職して帰郷しました。
最初は軽い家事程度だった母親のサポートでしたが、9年ほど前から認知症の症状が目立つようになり、本格的な介護と見守りがスタートしました。それでも近所のスーパーへ買い物に行けるほど元気だったものの、庭先で転倒して脊椎圧迫骨折を受傷。思うように回復が進まず、母親はほぼ寝たきり状態になってしまいました。
Cさんは地域の介護教室でベッドから車椅子への移乗介助や食事介助などを熱心に学び、母親の生活を支えてきました。
しかし、実家に戻った直後は50代だったCさんも、今や60代後半。これまで問題なくできていた移乗動作やおむつ交換が負担になり、先月は車椅子からベッドへの移乗の際にひざと腰を同時に痛めてしまいました。階段どころか、玄関の段差も越えられないほどの激痛で、介護どころではありません。
Cさんは、すぐにケアマネジャーに連絡して訪問介護と訪問看護の回数を増やしてもらいました。デイサービスの送迎時は、事業所スタッフが厚意で移乗を手伝ってくれたこともあって、なんとか急場を乗り切りました。
とはいっても、ひざと腰が完治したわけではなく、介護負担が軽くなったわけでもありません。さらに、食事介助の負担が増してきました。これまで車椅子ではまっすぐ座れていた母親が、最近は左に大きく傾くことが増え、Cさんは片手で母親を支えながら、片手でスプーンを口に運んでいます。その影響で、ひざや腰に加えて肩や腕まで痛めてしまいました。
「これでは、私が先にダメになってしまう」
Cさんは、在宅介護の限界を感じはじめていました。
要介護者の加齢や病状の変化で状況が変わり、介助量が増加した際に、強い味方になってくれるのが「訪問リハビリテーションサービス」です。Cさんから相談を受けた私は、この訪問リハビリという手段があることをお伝えしてみました。ところがCさんは表情を曇らせ、「それが、できないんです」と話しました。
1年前、母親の手足に拘縮(こうしゅく・関節が硬くなり動きづらくなる状態)がみられた際、Cさんは主治医へ訪問リハビリの相談をしたことがあったそうです。しかし、主治医から返ってきたのは「訪問リハビリは病気をしてすぐの人とか、退院直後の人が受けるもの。あなたのお母さんには適用外だよ」との言葉でした。
確かに主治医の言うように、訪問リハビリは病気やケガ、手術の直後、退院直後の「回復期」の方が受けるケースが多いです。Cさんの母親のように「生活期(けがや病気をしてから6ヶ月~1年以上経過)」の状態では、リハビリを受けられる機会は減ってしまいます。
しかし、「なぜ訪問リハビリが必要なのか」「どの程度の期間必要なのか」という具体的な課題と目的が明確であれば、生活期でも訪問リハビリが認められることがあります。
Cさんの場合、今回生じている問題は2点です。
・母親が座位(座る姿勢)を保てず、Cさんが片手で支えながらスプーンを口元に運んでいる状態で負担が増大し、食事介助に1時間以上かかっている
・Cさん自身も足腰を痛めていて、従来のやり方では安全な移乗動作ができない
そして、訪問リハビリを受ける目的は
・専門家であるリハビリスタッフから、座位姿勢と食事環境を整え、移乗方法の見直しをするために「期間限定で」指導を受けたい
ということです。
もう一つ大切なことがあります。それは、「主治医がOKを出してくれなくても、諦めずに何度も繰り返し相談する」ことです。詳しく説明したつもりでも、状況がうまく伝わらずに誤解やすれ違いが起きた――私たちのふだんの人間関係でもよく起きることです。ましてや、訪問リハビリの現場は慢性的な人手不足で枠が少なく、希望してもすぐには受けられないケースも珍しくありません。
Cさんは「一度断られたのに、またお願いしていいんですか!?」とびっくりされていましたが、私は「訪問リハビリの必要性が伝わるよう、具体的な目的と期間を、淡々とお願いし続けましょう」とアドバイスしました。
Cさんは早速、主治医への再度の相談にチャレンジしましたが、「今、訪問リハビリは人手が足りないから、すぐには無理だよ」と、再びつれない返事。しかし、Cさんはケアマネジャーにも相談し、「食事の際に座位が安定するよう、環境を整えたい」「私の腰とひざに負担がかからず、安全な移乗動作を再検討して専門家の指導を受けたい」と繰り返し説明しました。ケアマネジャーも状況を把握し、主治医へ提案してくれたそうです。
相談するたびに具体的な状況説明を重ねた結果、主治医も徐々に必要性を理解してくれたのでしょう。とうとう、3ヶ月間の期間限定で訪問リハビリ導入の指示書が出たのです。
Cさんは「介護負担がゼロになるわけではないし、劇的な変化はないかもしれません。でも、何度か相談をすることで状況をわかってもらえた、サービスが利用できたという体験をしたことが、今後の在宅介護を続ける上での大きな励みになりました」と報告してくれました。
要介護者の状態が変わっていく姿を目の当たりにすることそのものが、介護する家族にとっては大きな心理的負担です。それ以上に苦しいのが、必要な支援を使えない無力感です。「誰にも頼れない」「結局、私がやるしかない」と、助力を諦めたくなるのも、ごく自然な反応です。
しかし、そんな時こそ思い出してほしいのです。
たった今、暮らしのどの場面で何に困っているかを、具体的に言葉にすること。
そして、一度でうまくいかなくても、何度でも相談を続けていいということ。
制度やサービスは「目的」と「必要性」が具体的であるほど動きやすくなります。相談を重ねる中で状況が整理され、必要性が徐々に理解され、支援やサービスにつながった事例を、私は数え切れないほど見てきました。
状況が変わらず、心が折れそうな時ほど、「今は、相談を積み重ねる時期なんだ」と、思い出してみてください。粘り強い対話を重ねた先に、新しい扉が開くことがあります。
写真:写真AC
この著者のこれまでの記事
・介護サービスを嫌がる親にどう寄り添う? いざという時のために備える“頼る力”
・「負けたくない!」が教えてくれた、本当の気持ち――心を守る介護の知恵
・情報が介護を変える──福祉用具と専門家の力で父娘がつかんだ在宅復帰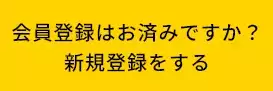

著者:橋中 今日子
介護者メンタルケア協会代表・理学療法士・公認心理師。認知症の祖母、重度身体障がいの母、知的障害の弟の3人を、働きながら21年間介護。2000件以上の介護相談に対応するほか、医療介護従事者のメンタルケアにも取り組む。