書店主で著述家としても活躍している辻山良雄さんによる、本と読書についての連載も初回から1年を迎えました。5回目の今回のテーマは、「はたらき」。昨今では仕事の場においても生活の場においても、人と人との関わり合いが効率化されつつあります。そのおかげでノイズやストレスは軽減されても、その実失うものも少なくないようです。人の流動性が高まる春、さまざまな仕事とその周辺についてのこの3冊の本から、皆さんは何を感じるでしょうか?
先日、最寄り駅近くの吉野家に行った。しばらく来ないあいだに店はリニューアルしたようで、席は壁に向かって一列に並び、一瞬別の店に入ったかと錯覚した。注文はすべてタッチパネルで行い、食べ終われば食器を返却口まで戻して、入口でお会計をして帰る。極力人との摩擦を減らしたシステムなのだろう。働いているスタッフには以前のようなピリピリした空気はなくて、ずいぶん穏やかな、あたらしく入った人でも働きやすそうな職場に思えた。
しかしわたしは朝の時間見かけるような、お新香や牛皿で瓶ビールをのむおじさんのことを思い出してしまった。ビールもお新香もタッチパネルで注文できるけど、自分で配膳口までビールを取りにいき、壁を前にのんだとしても、あまり美味しくはないだろう。
そのようにいまは街のどこに行っても、人間不在の光景に出くわしてしまう。その変化はあまりにもソフィスティケートされていて、少し恐いくらいだが、人間がいちばん非効率な存在ということなのかもしれない。しかしそんな状況の中でも、どうしたら人がその人らしく働くことができ、なおかつひとつの組織として存続していけるのか。そうしたチャレンジを続けているカフェが、東京の西国分寺にあった。
クルミドコーヒーは、JR中央線・西国分寺駅からほど近い、二〇〇八年開業のカフェ。経営者の影山知明さんが書いた『大きなシステムと小さなファンタジー』を読むと、クルミドコーヒーではレシピやマニュアルに基づいて仕事をするだけではなく、時にはそのときいる人にあわせた仕事のほうが優先されると知り驚いた(実際、長年料理を担当していたスタッフが退職することになったときも、無理をしてそのメニューを続けるのではなく、まずは一人一人が「自分を重ねることのできる仕事」のほうを伸ばしていったという)。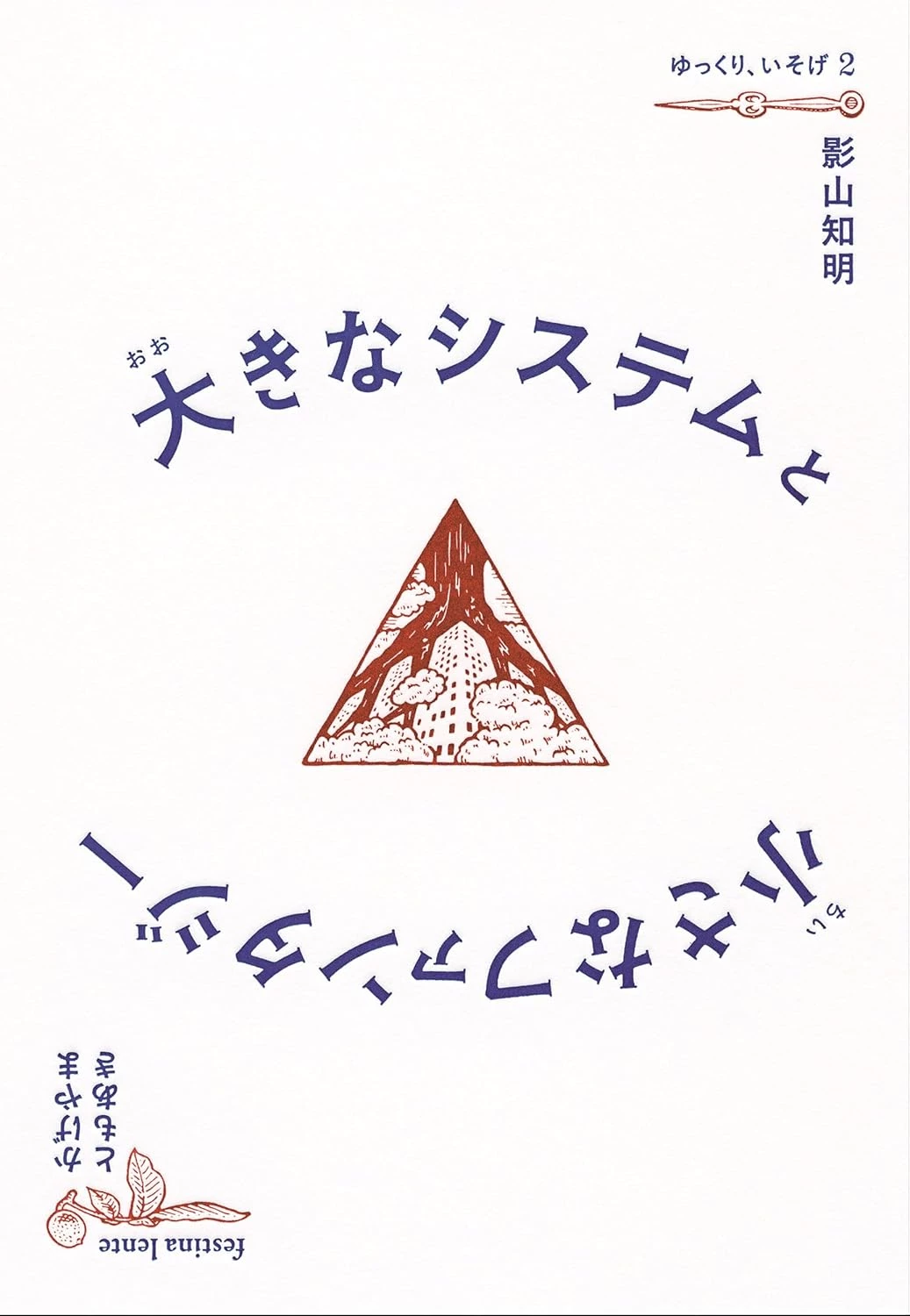
写真上:『大きなシステムと小さなファンタジー』影山知明著 クルミド出版
こうした柔軟さは、何かしら植物的なものを感じさせる。大きなシステムでは、システムに合わないものは捨てられ、あたらしいものに交換されるだけだが、一見弱そうな植物はそれぞれの姿のまま複雑な生態系をつくり、風や昆虫の力も借りながら種を遠くの場所まで飛ばす。クルミドコーヒーのような植物的な組織では、たとえ何か状況が変わったとしても、そこに〈人〉がいる限り、かたちを変えながらでも続いていくのだ。
影山さんは本書の中で、ミヒャエル・エンデの『モモ』(この本全体が『モモ』へのひとつのオマージュとなっている)に触れながら、「死んだ時間」を集めて効率的に利益を生み出す、いまの社会に疑問を呈する。
時間とは、いのち。
それは、ほんとうの持ち主のもとにある限りは生きていられるけど、そこからぬすまれ、切りはなされると死んでしまう。(中略)はたしてぼくらは本当に自分の時間を、生きた時間を、日々生きることができているのだろうか。
(『大きなシステムと小さなファンタジー』P.29より)
仕事をするうえで「効率」は、外すことのできない考えかたで、うまく使えば会社の経営を支えるよき道具となる。しかしいま起きている問題は、生活や人生といったほんらい効率で測るべきでないところにまで、そのものさしを使っていることだろう。自分の時間を切り詰めているうち、その人固有の時間は忘れ去られ、果てにはいったい何のために生きているのか、わからなくなってしまう人も多いのではないか。
そうした「効率」で行われた仕事は、それが最適化されたものであるといった性質上、誰が行っても同じになる。そこには、その人でなければといった必然性は生まれにくい。
だから「効率」を超えたその人固有の仕事に、人は心を動かされるのであり、人に合わせて仕事ができていくクルミドコーヒーの働きかたは、感動を与えるという意味において理に適っているのである。
写真家の吉田亮人さんが写真を撮り、画家で装丁家の矢萩多聞さんが文章を書いた、「写真絵本 はたらく」といったシリーズがある。いずれの本も、人がそれぞれの職場で働いている姿を、時間に沿って一冊の絵本にしたものだが、彼らにとってはありふれた、毎日行っている仕事でも、それを必要とする誰かがいる。そうした求めが満たされる瞬間は、考えてみれば奇跡のような時間だ。
シリーズの最新作『はたらく動物病院』では、夫婦二人で営んでいる、小さな動物病院の一日が描かれる。次々と来院する動物たちを手当てする二人の仕事では、自分の自意識にとらわれている余裕などない。治療を待つ動物たちが目のまえにいる以上、二人はそれに対し淡々と、最善のかたちで対応しなければならないのだ。
写真上:『はたらく動物病院』吉田亮人(写真)、矢萩多聞(文) 創元社
こうした「自らは選ばず、受け身の態勢でベストを尽くす」仕事には、働くことの本質が現れているように思う。外からやってくる働きかけに応じ、無心に体を動かしているうち、いつの間にかそれがその人にしかできない「はたらき」となる。それがはたらく=その場に作用する、ということではないだろうか。
そしてこのシリーズには「本屋」の巻もある。そこでは京都の水無瀬にある長谷川書店の長谷川稔さんが登場しているが、実はわたしも、『しぶとい十人の本屋 生きる手ごたえのある仕事をする』という本で、長谷川さんにインタビューしたことがあった。この本で彼は、次のように語っている。
一生懸命生きるというよりは、自分をちゃんと使いたいんです。自分が道具だとしたら、ちゃんと使って終わりにしたいと思っている。
(『しぶとい十人の本屋 生きる手ごたえのある仕事をする』P.104より)
写真上:『しぶとい十人の本屋 生きる手ごたえのある仕事をする』辻山良雄著 朝日出版社
マンガを買う子ども、宝くじを買うおじさん、算数のドリルを探す女の子……。「本屋」という場所では人の数だけ求めがあり、彼はその人に合った本を差し出すことで、その求めに応じることができる。長谷川さんは「本屋」という職を得て、自分がいちばん役に立つかたちを知ったのだ。そうして彼は「自分をちゃんと使う」あいだ、自分のやっている仕事が世界に小さな「はたらき」を起こすことができる、天職であることに気がついた。
「はたらき」が息づいた場所では、人はひとりの人としてあつかわれ、そこには生きた時間が循環している。それは人から時間を奪って生きのびようとする人間不在の場所では、決して起こり得ないことだ。そのような生きた時間の存在に意識的になれば、たとえそれが仕事というかたちをとっていなくても、人はその人らしい「はたらき」のほうへと向かっていけるだろう。
写真(トップ):freepik

著者:辻山良雄
辻山良雄(つじやま・よしお) 1972年兵庫県生まれ。大手書店チェーン〈リブロ〉を退社後、2016年、東京・荻窪に本屋とカフェとギャラリーの店Titleを開業。書評やNHK「ラジオ深夜便」で本の紹介、ブックセレクションもおこなう。著書に『本屋、はじめました』『365日のほん』『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』、画家のnakabanとの共著に『ことばの生まれる景色』がある。最新刊は『熱風』誌の連載をまとめた『しぶとい十人の本屋』(朝日出版社)。撮影:キッチンミノル