書店主で著述家としても活躍している辻山良雄さんによる、本と読書についての連載。今回は、〈いま〉をキーワードに2冊の本を紹介。その2冊とは、〈意志〉の不確実性や〈利他〉の成り立ちに分け入る本、そして、長年〈ケア〉を見つめてきた編集者によるの捉え方についての概念を揺るがす、挑戦的かつ寛容な本です。なんらかの違和感を抱えるケアラーはもちろん、日々の淀みを感じる人にとっても気づきのきっかけを与えてくれるのではないでしょうか。
よく「自分の意志が大事だ」とか、「自分で考えて行動しなさい」といった言葉を耳にする。わたし自身、振り返っても、これまで様々な場所でそう言ってきた。
しかしわたしは、「自分の意志って、そんなに大したものなのか? ときには自ら選ばないことだってあり得るのではないか」とも思いはじめている。自分で決めたように思っても、それは周りの空気に動かされただけということもあるだろうし、ほかの誰かの薦めに従うことが、返ってよい結果をもたらす場合だってあるからだ。
政治学者の中島岳志さんは『思いがけず利他』の中で、そうした自分と他人をめぐる不思議について考察している。
「利他」といえば、誰かほかの人に対し、何かをやってあげるというイメージだが、それは利他の表層的な一面にすぎない。利他とはそれを受け取る人がいてはじめて成り立つものだと、中島さんはいう。見返りを期待するのではなく、無心で何かを差し出した行為がめぐりめぐって、それを受け取った誰かの役に立っているようなこと。
そうした一連の流れは〈偶然〉の出来事かもしれないが、見方を変えれば〈運命〉であるともいえるだろう。この偶然と運命の関係について、本書で中島さんは「被贈与性を〈私〉として受け止めたとき、〈偶然〉は〈運命〉へと姿を変えます(※1)」と書いている。
ここで恐縮だが、わたしの話をしてみよう。
まだ会社員だったころ、勤めていた書店が無くなるかもしれないと聞いたとき、偶然にも、ずっと介護をしていたわたしの母が亡くなり、手元にはいくばくかのお金が残った。そのお金を見ていると、「これはわたしのためだけに残されたお金ではない」という気がして、次のような考えが不意にわたしを襲った。「自分にできる本のある場所(=本屋)を、そのお金でつくってみよう」。
お金が残ったのは〈偶然〉だったかもしれないが、わたしはそれを〈私〉の〈運命〉として受け取り、本屋をつくることにした。そうさせたのは、母の死に端を発した、「利他」の力だったかもしれないが、それで救われたのはわたしだけではなかっただろう。たとえその帰結を知らなくても、自分の行った行為が息子を救うはたらきとなった時点で、わたしの母もまた救われたのではなかったか。
そうした循環が、利他で回っている世界にはあると思う。
しかし、外から偶然がやってくることをただ待っているだけでは、偶然はやってこない。
「自力で頑張れるだけ頑張ってみると、私たちは必ず自己の能力の限界にぶつかります。そうして、自己の絶対的な無力に出会います。重要なのはその瞬間です。有限なる人間には、どうすることもできない次元が存在する。そのことを深く認識したとき、〈他力〉が働くのです(※2)」
利他がはたらくには、自分に与えられた〈いま〉を充分に生き、「私たちが偶然を呼び込む器になる(※3)」ことだ。わたしも毎日同じ仕事をしているあいだ、自分がからっぽになっていくように感じるときがあるが、仕事に何かしらの偶然が訪れるとすれば、それはそのような、器になっている時間だろう。
利己と利他は、事物の奥底で複雑に絡み合っている。それを考えるとき、わたしは世界の秘密を垣間見たような、深遠な気持ちになる。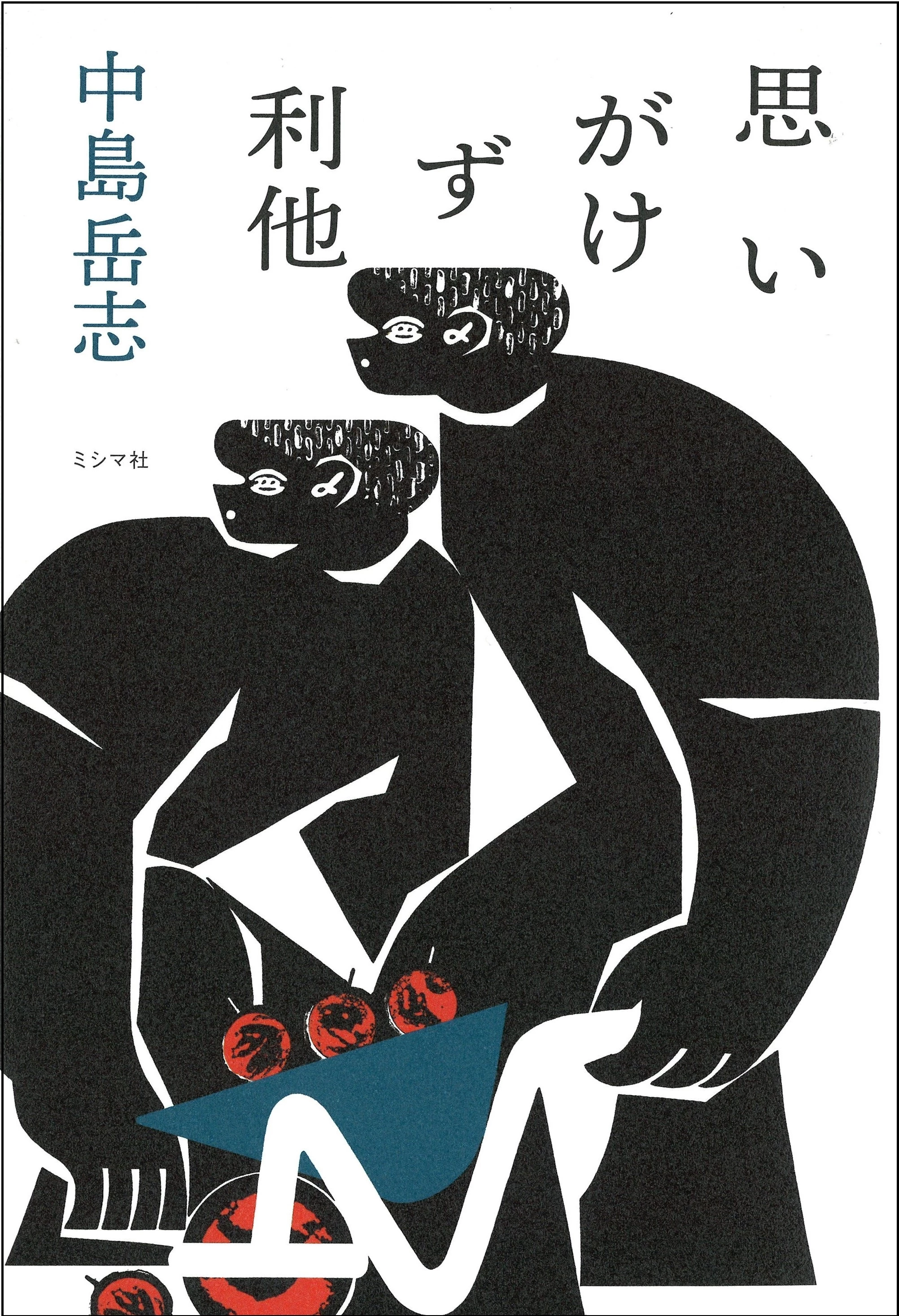
写真上:『思いがけず利他』中島岳志著 ミシマ社
文中引用箇所:※1 P.159, ※2、3 P.176
偶然性を愛し、そこに「やってきた」ものを、みなが受け取る面白い本へと変える人物。それが編集者の白石正明さんだ。白石さんはもう定年退職されたが、長年、医学書院という出版社に勤められ、2000年には「ケアをひらく」という、介護や看護に関する本のシリーズを立ち上げた。自身が編集した本をまな板にのせ、その読みどころや、ケアとは何かという話を語った本が、最近出版された『ケアと編集』である。
この本を読むと白石さんの編集術とは、人を変えるのではなく、その人のまま肯定するところにあるとわたしには思える。
「〈弱さ〉とか〈依存〉といった克服されるべき問題――なにより当人がもっとも〈克服すべき〉と思っている問題――に別の光を与えること。それは編集という仕事そのものだと思う(※4)」
「別の光を与える」と言うと、消極的だと感じる人もいるかもしれない。だがその病気が克服すべきものとなった時点で、治療をしている〈いま〉は、あるべき未来に対しての〈手段〉に成り下がってしまう。
実際本書や、白石さんの編集した本を読んでいると、「いまの豊かさをいかに味わい尽くすか」ということに、主眼が置かれていることがよくわかる。ただ会話するために、会話を続けるオープンダイアローグ、「もう今で完全なんだよね」と言う、躁鬱病を生きるアーティスト・坂口恭平さん、消費と違い浪費は、身体全体でそれを味わうことだという哲学者の國分功一郎さん。
ALS(筋萎縮性側索硬化症――全身の運動神経細胞が徐々に侵される難病)を発症した、寝たきりのお母さまの介護を続けていた川口有美子さんについて、白石さんは次のように書いている。
「ただ生きるために体が勝手にやっていることによってあふれ出るサインを読み取り、体が欲しているより快適な方向に母親を後押しする作業だ。サインを受け取る人がいなければ体の要求は空を切り、何もなかったことになるだろう(※5)」
生きようとする母の微かな声を聴こうとしているあいだ、川口さんとお母さんの体はぴったり同期している。だから川口さんは母親の死後、きっと彼女はこう感じていたのだろうと確信した。「ああ、生きるのに忙しい(※6)」と。
ベッドを離れることのできない、弱さの極みのような川口さんのお母さまの体にも、豊かな〈いま〉が流れ込んでいたのだ。それを発見することは、失われそうになっていた微かな世界を発見するにも等しい行為で、川口さんは母からのサインを受け取りながら、彼女が見せてくれた世界のありようを同時に生きていたのである。
「ケアをひらく」シリーズを読んでいると、きびきびと実務的に働く、看護師の姿が印象に残る。彼ら・彼女らは「治す」といった医学的アプローチとは別に、ときに非科学的とも言える寄り添いかたをして、患者の〈いま〉を励ましている。
現象学的な質的研究をする村上靖彦さんは、「主語がはっきりしない」「話があっちにいったりこっちにいったりする」(※7)看護師の語りに着目し、それはケアの現場の中で、患者に憑依しているからだと考えた。看護師は、ケアを必要とする患者に自分の体ごと没入し、何が苦しいのか・何がうれしいのかを、患者と一緒に探っている。
〈いま〉をステレオタイプな未来への手段とせず、それぞれの複雑さに留まること。それは、すでにその場にある豊かさを受け取ることで、白石さんの本が支持されているのも、そうした気づきを与えてくれるからにほかならない。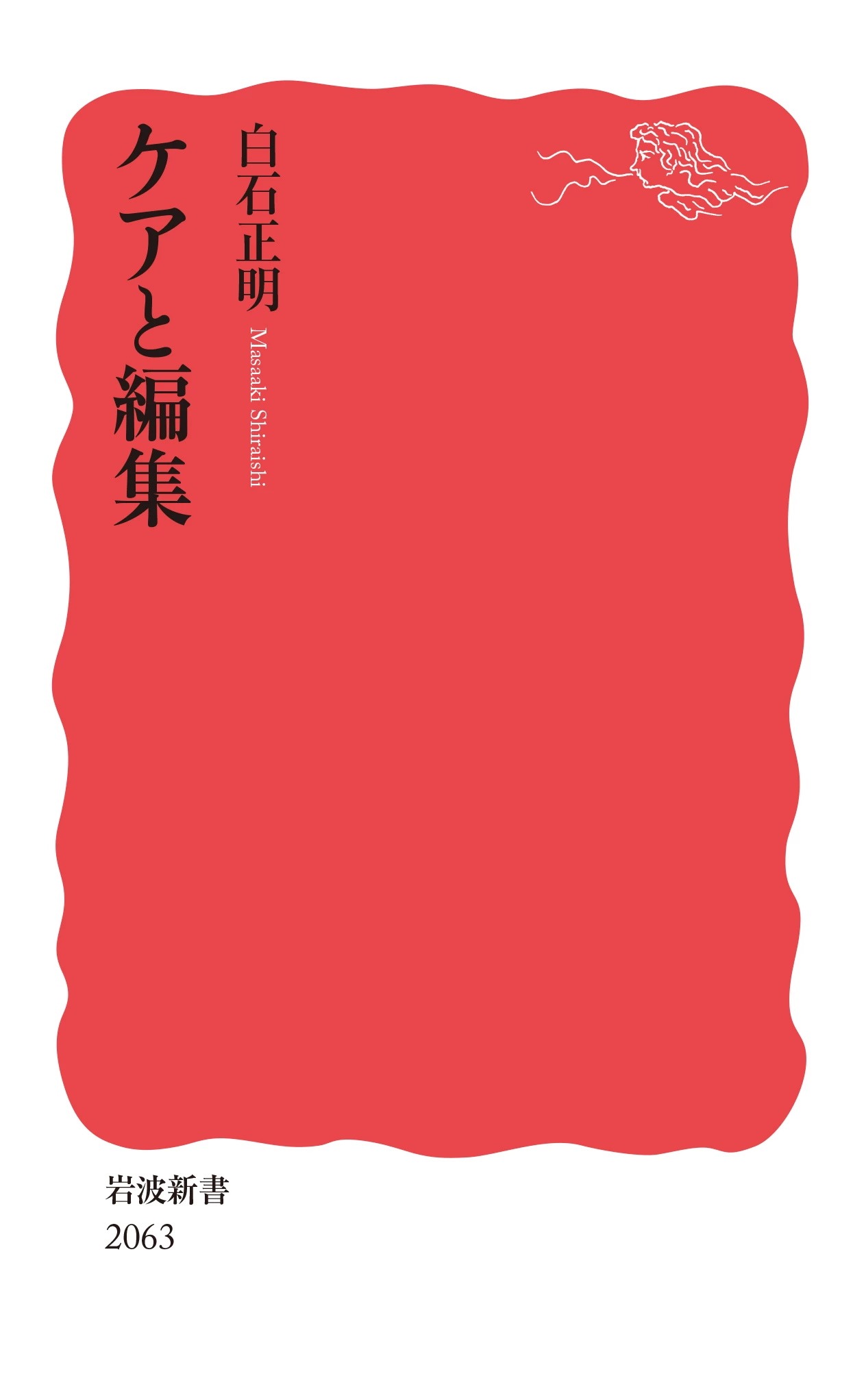 写真上:『ケアと編集』白石正明著 岩波新書
写真上:『ケアと編集』白石正明著 岩波新書
文中引用箇所:※4 P.64,※5 P.188、※6 P.191、※7 P.45
写真:著作者:freepik

著者:辻山良雄
辻山良雄(つじやま・よしお) 1972年兵庫県生まれ。大手書店チェーン〈リブロ〉を退社後、2016年、東京・荻窪に本屋とカフェとギャラリーの店Titleを開業。書評やNHK「ラジオ深夜便」で本の紹介、ブックセレクションもおこなう。著書に『本屋、はじめました』『365日のほん』『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』、画家のnakabanとの共著に『ことばの生まれる景色』がある。最新刊は『熱風』誌の連載をまとめた『しぶとい十人の本屋』(朝日出版社)。撮影:キッチンミノル