母と娘の関係性とその介護について考える連載。自身のブログやメディアなどで若年性認知症の母親との生活を発信しているフリーアナウンサーの岩佐まりさん。20年以上も在宅介護を続ける彼女に「なぜ、そこまできるのか?」と、その背景にある母娘の関係性について伺いました。
2009年から若年性認知症になった母親のことをブログに綴り、その様子についてテレビ番組で密着取材を受けるなど、メディアでも発信を続ける、フリーアナウンサーの岩佐まりさん。その背景には、「もの忘れや徘徊などが大変で認知症になるのは怖い」といった差別的な視点を覆したかった、という想いがありました。さらに、「認知症になっても楽しいことがあれば笑うし、いきなり子どものことを忘れたりはしない。母親以外にも、一生懸命に生きる何万人といる認知症の人たちを応援する視点があったらいいな」という思いから、母親との日々を包み隠さず公開しているのだそうです。
岩佐さんは夢であった芸能活動を本格的に行うため、18歳で大阪から上京しました。その翌年あたりから、母親に物忘れが目立つようになります。母親は若年性認知症(アルツハイマー病)だったのです。徐々に症状が進み、母親のことが心配になった岩佐さんは、自分のもとに母親を呼び寄せ、仕事を続けながら母親の介護をする決意をします。
自らの夢も叶い、フリーアナウンサーとして忙しく働く中で、仕事に邁進するために母親には施設に入所してもらうという選択もあったはずです。ましてや当時の岩佐さんは、まだ20代。「たとえ、娘であってもそこまでしなくても……」と思う人もいるかもしれません。それでも母親と一緒に暮らす選択をしたのはなぜだったのでしょうか。
あえていばらの道を選択した理由を聞くと「とにかく、母親のことが大好きなんです」と岩佐さんは答えます。友達と遊ぶよりも話の合う母親と一緒にいる方が楽しいと思うくらい、仲良し親子でした。岩佐さんに彼氏ができた際は一番に紹介したり、母親が元気だった頃は二人で朝から晩までテーマパークで一緒に遊んだこともあるそうです。
ほかの母娘にはないほど岩佐さんと母親の絆をより強固にしたのは、夢を2人で叶えたことが大きかったと振り返ります。その夢とは、芸能の道で生きていくということ。母親は若いころ、女優になるという夢を持っていました。しかし、諸事情でその夢が叶うことがありませんでした。不思議と母親と同じ夢を持つようになった娘の岩佐さんは、子どものころから児童劇団に入っていました。そんなふうに夢に向かって頑張る娘に対して、母親はいつも全力で応援してくれたのです。
夢が叶ったのは、どんなときも母親の大きなサポートがあったからだと岩佐さんは感じており、夢を叶えるために母親が自分にしてくれたサポートを、今度は母親にしてあげたいという思いを強くもっていました。それ故、認知症が進んで母親がどんな状態になっても母親の近くにいることを決めたのだそうです。
岩佐さんは母親の介護を担うと同時に、もう1つ自分の中で大きな決心をします。介護を続けながらも、2人で叶えた夢は諦めない、ということです。母親のことが大好きな自分同様、自分のことも大好きでいてくれる母親は、自分の介護のために娘が夢を諦めることを一番嫌がるであろうとわかっていました。テレビ番組の密着取材の様子などから献身的に母親の介護にあたる岩佐さんのイメージが強いかもしれませんが、「仕事のためならば、介護サービスをバンバン利用しますよ」と言い切ります。その一方、長きに渡り母親の介護をする中で介護関連の資格を取得した岩佐さんは、今は言葉を発することができなくなった母親が何を望んでいるかは空気で分かるし、誰よりも上手に介護をする自信がある、と笑います。
岩佐さんは自身の介護経験から、娘や息子などの子世代やビジネスケアラーに向けての個別相談や家族会などを開催しています。そこでは参加者から、「岩佐さんと同じような介護は私にはできない」という声もあるそうです。岩佐さんはそういう方たちに、介護にはそれまでの親子関係が大きく影響すること、岩佐さんがここまで母親の介護を頑張ることができるのはそれまでの母と娘の良好な関係性と強い絆があってのことだと話すそうです。また、介護の仕方は人それぞれだとも伝えています。介護ができる環境にあるかないかも重要な視点ですし、それまでの親子の関係性が悪ければ、自分と同じような介護が難しい人もいると考えているからです。
そして、夢ややりがいのある仕事を諦めて介護をするようなことは絶対にダメだと考えており、「それならば施設入所を考えてみては?」と勧めることもあるそうです。なぜなら、子どもの人生を犠牲にしてまで介護されることを望んでいない親の方が多いということをわかっているためです。この思いは自身が結婚し子どもを持ったことで、確信に変わったといいます。
岩佐さんは決して盲目的に母親の介護をしているのではなく、自分の中に母親の介護に対するしっかりとした指標を持ち、介護も夢も自分の人生も諦めない道を選択し続けた結果、今の岩佐さんがあるのだと考えられます。ここ数年はすっかり寝たきりのような状態になってしまったという母親に対して、少し意外な話をしてくれました。
20年以上も在宅介護をしている岩佐さんは「最期も自宅で……」と考えているのだろうと思いきや、そこにこだわりはないのだそうです。看取りに関しては状況によりけりで、「病院での看取りになっても仕方がない。一番の願いは母親の最期の瞬間に私が隣にいること」なのだそうです。
岩佐さんの母親は「胃ろうを設置しないと1か月も持たないだろう」と医師から言われたことがありました。一方、胃ろうをして年単位で生きている人を岩佐さんは知っていました。最終的に母親は胃ろうを設置しました。「一切の延命処置はしない」という選択をする人もいますが、いざ、その決断をする段になると、子どもの気持ちが揺らぐのは当たり前だと岩佐さんは考えています。たとえば、1、2時間しか延命できない処置は選択しないとしても、その処置により明日以降も迎えることができて、一緒にいる時間が延ばせるのであれば、全ての延命処置を拒否するのは違うのでは、と考えているそうです。そこには、「少しでも母親と一緒にいたい」「少しでも長く生きていて欲しい」と思う、娘の正直な気持ちがあるからです。
母親のことが大好きであり、母親の介護と真正面から向き合ってきた岩佐さんだからこそ、きれい事ではない最期についての率直な考えのように思えました。
写真: 岩佐さんより提供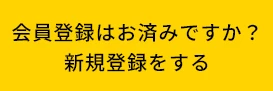
この著者のこれまでの記事
・母と私、そしてヤングケアラーになった娘へ|娘はつらいよ!?⑰
・「ごめんね」を胸に、母を支え続ける娘|娘はつらいよ!?⑯
・二拠点生活で見えてきた、母の孤独と私の変化|娘はつらいよ!?⑮
・父親の介護で表面化する母親との確執|娘はつらいよ!?⑭
・突然の別れ─完璧すぎた母と娘の後悔|娘はつらいよ!?⑬
・サザエさんとカツオのような母娘関係、その葛藤と成長|娘はつらいよ!?⑫
・約20年間、母親を在宅介護する娘|娘はつらいよ!?⑪
・50代になって反抗期を迎えた娘|娘はつらいよ!?⑩
・どんなに嫌でも母親と縁を切らないと決めた娘|娘はつらいよ!?⑨
・書店員が選ぶノンフィクション大賞2024候補『母がゼロになるまで』著者に聞く|娘はつらいよ!?⑧
・「母娘介護」研究者に聴く!|娘はつらいよ!?⑦
・障がいのある母親に育てられた娘|娘はつらいよ!?⑥
・超エリートの母親との関係に苦しむ娘|娘はつらいよ!?⑤
・絶対に同居を選ばなかった娘 |娘はつらいよ!?④

著者:岡崎 杏里
大学卒業後、編集プロダクション、出版社に勤務。23歳のときに若年性認知症になった父親の介護と、その3年後に卵巣がんになった母親の看病をひとり娘として背負うことに。宣伝会議主催の「編集・ライター講座」の卒業制作(父親の介護に関わる人々へのインタビューなど)が優秀賞を受賞。『笑う介護。』の出版を機に、2007年より介護ライター&介護エッセイストとして、介護に関する記事やエッセイの執筆などを行っている。著書に『みんなの認知症』(ともに、成美堂出版)、『わんこも介護』(朝日新聞出版)などがある。2013年に長男を出産し、ダブルケアラー(介護と育児など複数のケアをする人)となった。訪問介護員2級養成研修課程修了(ホームヘルパー2級)
https://anriokazaki.net/