母と娘の関係性とその介護について考える連載。房総半島の古民家に移住し、第二の人生を歩んでいた母親が認知症に。母親の介護で衝突した弟とは絶縁状態が続くなど、知識がなかったゆえの後悔を胸に、今、娘のMさんが思っていることとは……。
「今の知識を持ったまま、あの頃に戻れたら、こんなに後悔はしなかったと思う」
今回取材をしたMさん(50代、主婦)が発した印象的な言葉です。Mさんが戻りたいと思ったのは、東日本大震災後に母親がそれまで暮らしていた北海道から房総半島の土地付きの古民家に移住したころ。自然に関わる仕事をしているMさんの弟が房総半島のある町にキャンプ場を作ることを計画し、母親もそれに賛同したことが移住の経緯でした。定年まで勤め上げ、ガンを患った父親を看取り、新しい土地で第二の人生を生き始めた母親は、社交的な性格もあり、ご近所さんとの親睦を深めて地域にも馴染み、庭仕事に勤しむなど、しばらくは充実した日々を送っていました。
移住をして3年が過ぎたころ、母親は庭仕事を頑張り過ぎて腰を痛めて寝込んだことがありました。そのあたりから、もの忘れや同じことを何度も言うなど、認知症のような症状が気になったというMさん。弟に相談するもあまり気にしておらず、しばらく見守っていました。ところが、次第に弟も母親の変化に気づくようになります。
困ったMさんは、地域包括支援センターの存在を知らなかったため、移住先の町役場に助けを求めに行きました。町役場の福祉健康課が、地域包括支援センターと介護認定調査の実施も兼ねていたのは幸いでした。そこで車で1時間ほどの一番近いという認知症の人を診てくれる病院を紹介されました。受診を母親に勧めるも「自分は認知症なんかではない!」と拒絶。叔父から電話で助言してもらい、なんとか連れていくことができましたが、そこまでに2年を費やしました。診察は非常勤の脳神経外科医が対応し、アルツハイマー型認知症と診断され、薬を処方されます。Mさんは「病気だから薬をもらう」という流れになんの疑問を持ちませんでしたが、その後、認知症専門医の存在や関連書籍を読むなど知識を得ると、母親にはもっと適切な対応策があったはずだと考え、当時の自分は間違えていたのではないかと後悔しています。
その後、母親には要支援1の認定が下りますが、当初は介護サービスの利用にはあまり積極的ではありませんでした。Mさんや弟も「認知症になると、大変だ!」ということはぼんやりとわかっていても、「月イチで病院へ通い、薬を飲んでいれば、とりあえず大丈夫だろう」とひと安心していました。ところが、母親の病状は急速に悪化していき、あっという間に要介護2にまで到達してしまったのです。それでもまわりに認知症の介護をしている知人がいなかったため「こんなものなのか」と、どんどん変わっていく母親のことを嘆くしかなかったのです。
Mさんと弟はしばらくの間、通いの介護を続けていましたが、途中からは弟が同居をしてくれることになりました。弟の同居は見守りという意味では助かりましたが、彼の介護ペースと母親の生活にはズレがあったのです。母親の身体介護は1日1回の訪問ヘルパー頼みで、認知症の進行とともに身体の衛生管理と生活スペースの衛生環境は悪化していきました。その上、Mさんも弟も母親の薬の管理のサポートをしていなかったため、訪問ヘルパーから「(薬を)飲んでいない時があるようだ」と知らされます。また、母親は薬を飲んでいたとしても、ひどい副作用に悩まされていたという状況があったのです。
Mさんにとって母親は、祖父母の助けを借りつつも仕事と育児を両立し、家にいるときは料理や裁縫もそつなくこなす理想の女性でした。定年後も「女性の働き方」について短大で講演するなど、自慢の母親でもありました。そんな母親が、何度言ってもわからない、理解不能な行動してはMさんを失望させます。あんなに尊敬していた母親に、怒鳴っては自己嫌悪に陥る。それでも、変わりゆく母親を受け入れられない弟に代わり、Mさんがキーパーソンとなって介護サービスをフルで活用し、なんとか踏ん張って介護を続けていました。
過疎化の進む移住先には居宅介護支援事業所が1箇所しかなく、ケアマネジャーは1人しかいませんでした。そのうえ、当時のMさんは「ケアマネジャーって、病院にいる人でしょう?」という知識のなさ。そんなMさんにケアマネジャーは忙しい中でも親身になって寄り添ってくれたことが大きな救いとなったそうです。
都心から車で渋滞がなければ片道約1時間半の距離でも、房総半島の町に週1回通う生活はMさんの心身を疲弊させ、母親の介護により12㎏も痩せてしまいました。また、母親の介護に加えて、認知症介護に対して考え方が違ううえ、気が利かない性格の弟の存在も悩みのひとつでした。
たとえば、弟は「食パンを1斤買って、置いてきたから大丈夫だよ」というのでMさんが母親の家へ行き確認をすると、切られてもいないそのままの食パンが1斤ボンと冷凍庫にカチカチの状態で入っていました。食パンを切るどころか、解凍することもできなくなっている認知症の母親には、それを食べることは不可能です。ほかにも弟は訪問ヘルパーのことを家政婦と勘違いし、トラブルになったこともあります。それらの尻ぬぐいはすべてMさんに降りかかり、大きな負担となりました。弟なりにサポートしてくれていたことには感謝をしていましたが、的を得ない中途半端なサポートならば、ない方がマシだとケンカばかりするようになってしまいました。これも後悔の1つで、自分や弟に認知症や介護の知識がなかったために起きたことなのです。
そのうち母親に徘徊症状が表れ、Mさんはまったく眠れない状態となり、帰りの高速道路で睡魔に襲われ、「車を運転して帰るのがこわい」「いつか事故を起こしかねない」と、さまざまなことに限界を感じはじめます。そんなMさんを見かねたケアマネジャーは「キーパーソンは娘さんだから、娘さんがベストだと思う方法を考えて、選択してください」という助言をくれました。
Mさんは母親に施設へ入所してもらうことを決意します。自分が母親の家に移り住むことや自分の家に呼び寄せての介護は選択肢にはありませんでした。なぜなら、離れていた方が心の余裕を保てると最初から感じていたからです。さらに、母親にイライラする弟がいつか虐待をしてしまうのではないかということも心配でした。弟は当初から母親の施設入所に関しては反対でしたが、理由はハッキリとはわかりませんでした。そのためMさんは弟には一切の相談や連絡をすることなく、勝手に入所準備を進めます。一方でケアマネジャーには進捗状況を報告。弟はMさんと連絡を取り合わなくても、ケアマネジャーに問い合わせて情報を得ていたようでした。そのまま弟とは絶縁状態となってしまいましたが、大きな後悔はないとMさんはいいます。弟の方から何か言ってくることもないため、Mさんのストレスが1つ減ったことは、それはそれでよかったと思っており、弟との関係は、時間が解決してくれると考えています。
その後、母親はMさんの都内の自宅の近くの有料老人ホームへ入所しました。自宅の近所の老人ホームを選択したのは、これまで優しくできなかった母親に、毎日、会い行こうと思ったからです。ただし時はコロナ禍、面会が制限されてしまいました。すると、母親はたちまち車いすになり、蝋人形のように表情がなくなってしまいました。そんな母親を心配したMさんがいろいろ調べると、面会の可否の判断などは施設に丸投げされていることを知りました。Mさんは施設に掛け合い、ルールは守り、すべての責任を取るということで、短時間でも母親と会える許可を得ると、母親は徐々に表情を取り戻していったそうです。
母親が施設に入所して、心身ともに余裕が持てるようになったMさんは、地域の認知症カフェや困難を抱える人の支援にかかわるようになりました。そこから福祉の専門家や介護経験者との人脈が広がり、認知症や介護に関する知識をたくさん身に付けました。現在では自らが中心となって支援活動も行っています。それは、母親の介護でたくさんの後悔をした自分のような人を少しでも減らすためです。
「今、介護は無関係」だとしても、それが明日は自分の問題になるかもしれません。だからこそ、困っていないときから福祉に興味を持ち、知識を持つ人たちと繋がることの重要性をMさんは訴えます。「今の私みたいな人に、当時会いたかった」と自らの経験と後悔をもとに支援活動を行うMさんも、今は介護で困っている人を助ける一人なのでしょう。
この著者のこれまでの記事
・夢を支えてくれた母を支えるという選択|娘はつらいよ!?⑱
・母と私、そしてヤングケアラーになった娘へ|娘はつらいよ!?⑰
・「ごめんね」を胸に、母を支え続ける娘|娘はつらいよ!?⑯
・二拠点生活で見えてきた、母の孤独と私の変化|娘はつらいよ!?⑮
・父親の介護で表面化する母親との確執|娘はつらいよ!?⑭
・突然の別れ─完璧すぎた母と娘の後悔|娘はつらいよ!?⑬
・サザエさんとカツオのような母娘関係、その葛藤と成長|娘はつらいよ!?⑫
・約20年間、母親を在宅介護する娘|娘はつらいよ!?⑪
・50代になって反抗期を迎えた娘|娘はつらいよ!?⑩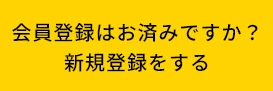

著者:岡崎 杏里
大学卒業後、編集プロダクション、出版社に勤務。23歳のときに若年性認知症になった父親の介護と、その3年後に卵巣がんになった母親の看病をひとり娘として背負うことに。宣伝会議主催の「編集・ライター講座」の卒業制作(父親の介護に関わる人々へのインタビューなど)が優秀賞を受賞。『笑う介護。』の出版を機に、2007年より介護ライター&介護エッセイストとして、介護に関する記事やエッセイの執筆などを行っている。著書に『みんなの認知症』(ともに、成美堂出版)、『わんこも介護』(朝日新聞出版)などがある。2013年に長男を出産し、ダブルケアラー(介護と育児など複数のケアをする人)となった。訪問介護員2級養成研修課程修了(ホームヘルパー2級)
https://anriokazaki.net/