母と娘の関係性とその介護について考える連載。自身がくも膜下出血で倒れ、退院した直後に母親が余命3ヶ月だと判明。最期まで自宅で過ごしたいと願う母親のために介護職としての経験を生かして母親を介護するも、介護職に就くことを反対した母親に対しては複雑な思いがあった。さらに、ヤングケアラーとなってしまった娘にも変化が起こり……。
祖父母と同居していたことから高齢者に親しみがあり、学生のころから福祉の仕事がしたいと考えていたKさん。しかし、高校ではトップクラスの成績であったため、進路相談の際、福祉関係の専門学校に進みたいと希望したところ、当時は介護職が“3K”と呼ばれて敬遠されていたこともあって担任と母親に強く反対されてしまい、福祉系の授業がある大学に進学することにしたという経緯がありました。
大学卒業後も介護職への関心は消えず、ケアハウスのスタッフとして働き、結婚後もその仕事を続けましたが、切迫流産のため退職。その後、3人の子どもに恵まれるも夫の不貞によりシングルマザーとなってしまいます。しばらくは生計を維持しながら育児も両立できる仕事をしていましたが、3.11(東日本大震災)をきっかけに「いつ、何が起きるかわからない。自分のやりたいことをやろう」と、再びホームヘルパーとして介護職に戻る決意をします。
その後、介護職としてのスキルアップと正社員への昇格などを目指してデイサービスに異動するも、2021年に40代にして自宅でくも膜下出血を起こし、救急搬送される事態となってしまいました。
幸いにも倒れたときに長女が家にいたため、迅速な対応を取ることができ、一命を取り留めたKさん。長時間の手術やリハビリを経て退院したKさんですが、その直後に母親が末期がんで余命3か月であることが判明します。自身の状況を把握した母親は最期まで家で過ごすことを強く希望しました。
実家には父親と妹がいましたが、在宅介護どころか、そもそも介護の経験が全くありません。そのため、後遺症によりスムーズに歩くことは難しくなっていたKさんですが、「これもリハビリ」と母親のために実家に通い、介護にあたりました。Kさんの子どもたちも祖母の介護に積極的に協力してくれたといいます。
3人きょうだいの一番上だったKさんは、その責任感から自分のことよりもきょうだいや家族の意見を優先してしまうところがありました。その傾向が大学進学にも大きく影響し、特に進路について反対した母親に対しては、心の中でずっと疼くしこりのような思いを抱いていました。
そんな複雑な思いを抱えながら、母親が反対した介護の道に進み、母親を介護するKさん。すると母親は「Kはすごいね、よくやってくれている」と介護の仕事を認める言葉を掛けてくれたのです。この言葉を聞いてKさんは「このために、介護の仕事をしてきたんだ」と、ずっと心に抱えていたしこりが消えていくのを感じたそうです。
介護職に就いていなければ、母親の最期の願いを叶えてあげることはできなかっただろうし、最後に母親とじっくり話せる時間を持つことができた在宅での看取りには後悔が少ないといいます。ただ、末期がんだった母親は介護をする期間がわかっていたからこそ出来たのであり、終わりが見えない状態であれば同じように出来たかどうかはわからないと、振り返ります。それは介護職ならではの視点なのかもしれません。
母親は最期まで自宅で過ごし、家族に見守られながら天国へ旅立ちました。くも膜下出血の後遺症で以前のようにバリバリと働くことは難しくなりましたが、介護の仕事を続けているKさん。シングルマザー、自らの病、母親の看取りと数々の試練を乗り超えてきましたが、今度は自分が母親として娘と向き合う日々がやってきました。
Kさんがくも膜下出血で倒れたとき、一番下の娘は高校1年生でした。朝は元気に自分を送り出してくれた母親が、「お母さんがくも膜下出血で倒れて、明朝、手術する」といきなり姉から言われ、突然家からいなくなってしまったことに加え、家の中は救急隊員がKさんを運び出したままの、あわただしくグチャグチャの状態。その混沌とした光景と母親の不在による不安が一番下の娘のトラウマになってしまったのです。さらに、生死をさまよう長時間の手術のあとの2ヶ月に及ぶ入院でヤングケアラー(18歳未満で家族の介護や家事を担う子ども)となり、家事や看病を上のきょうだいと担うことになりました。母親が退院したと思ったら、今度は祖母の看取り。希望する高校に入学するも、コロナ禍と重なり学校生活もうまくいっていなかったようなのです。
次々に重なる試練に、Kさんの3人の子どもの中でも特に繊細な性格だという一番下の娘はうつのような症状に悩まされるようになってしまいました。Kさんは母親になった瞬間から「本業は”母親”である」という姿勢で子どもたちを育ててきましたが、自分なりのペースで社会復帰を目指す娘に対し、これまで以上にしっかりと向き合うなど、態度でもその姿勢を示していくことを心に誓います。介護職にはやりがいを感じていますが、自分にとっての最優先事項は一番下の娘も含めて3人の子どもたちの母親であること。自分が母親という立場になったことで、介護職に就くことを反対した母親も母親なりの子どもを大切に思う気持ちからの行為だったのかもしれない、と思えるようになったそうです。
さまざまな出来事から、Kさんと母親、Kさんと娘=”母親と娘”という関係性について考え続けているKさんは、一番下の娘に”母親という存在”について質問したところ、娘から返ってきたのは「好きとか嫌いとかでなく、そういうものを超えた”お母さん”という特別な存在」という答えでした。その答えは、Kさんが母親に対して言語化できなかったことを見事に言い表していることに驚き、自分のことを“特別な存在”だと言う娘に対して、母親としての自信を取り戻した瞬間でもありました。
みなさんは“母親という存在”について問われたとき、どんなふうに答えますか? また、子どもがいる方の場合、子どもたちからはどんな答えが返ってくると思いますか?
写真:写真AC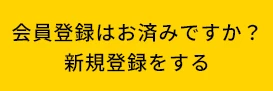
この著者のこれまでの記事
・「ごめんね」を胸に、母を支え続ける娘|娘はつらいよ!?⑯
・二拠点生活で見えてきた、母の孤独と私の変化|娘はつらいよ!?⑮
・父親の介護で表面化する母親との確執|娘はつらいよ!?⑭
・突然の別れ─完璧すぎた母と娘の後悔|娘はつらいよ!?⑬
・サザエさんとカツオのような母娘関係、その葛藤と成長|娘はつらいよ!?⑫
・約20年間、母親を在宅介護する娘|娘はつらいよ!?⑪
・50代になって反抗期を迎えた娘|娘はつらいよ!?⑩
・どんなに嫌でも母親と縁を切らないと決めた娘|娘はつらいよ!?⑨
・書店員が選ぶノンフィクション大賞2024候補『母がゼロになるまで』著者に聞く|娘はつらいよ!?⑧
・「母娘介護」研究者に聴く!|娘はつらいよ!?⑦
・障がいのある母親に育てられた娘|娘はつらいよ!?⑥
・超エリートの母親との関係に苦しむ娘|娘はつらいよ!?⑤
・絶対に同居を選ばなかった娘 |娘はつらいよ!?④

著者:岡崎 杏里
大学卒業後、編集プロダクション、出版社に勤務。23歳のときに若年性認知症になった父親の介護と、その3年後に卵巣がんになった母親の看病をひとり娘として背負うことに。宣伝会議主催の「編集・ライター講座」の卒業制作(父親の介護に関わる人々へのインタビューなど)が優秀賞を受賞。『笑う介護。』の出版を機に、2007年より介護ライター&介護エッセイストとして、介護に関する記事やエッセイの執筆などを行っている。著書に『みんなの認知症』(ともに、成美堂出版)、『わんこも介護』(朝日新聞出版)などがある。2013年に長男を出産し、ダブルケアラー(介護と育児など複数のケアをする人)となった。訪問介護員2級養成研修課程修了(ホームヘルパー2級)
https://anriokazaki.net/